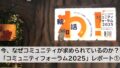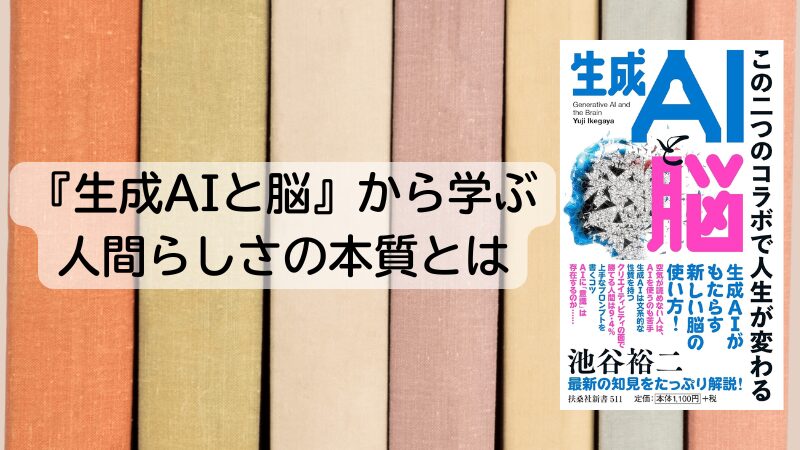
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
生成AIの進化…すごいですよね。僕らの働き方や生活に大きな変化をもたらそうとしています。
今回は、書籍『生成AIと脳』から、脳科学の視点から生成AIとの向き合い方を考えます。
ということで、今回は「『生成AIと脳』から学ぶ、人間らしさの本質とは」です。
では、行ってみましょう!
生成AIの進化と私たちへのインパクト
さて、最近、生成AIに関する話題をよく耳にするようになりました。
僕もノンプロ研で開講すべく、生成AI講座の準備を進めているのですが、その過程で、これは単なる技術的な話にとどまらない、もっと深いテーマだなと感じるようになりました。
当初は、生成AIの仕組みやプロンプトのテクニックといった内容を中心に講座を構成しようと考えていました。もちろん、それらも重要な要素です。
しかし、生成AIが人間社会に与えるインパクトは計り知れないものがあり、その備えとして、もっと「本質的な部分」に踏み込んだ内容が必要なのではないかと、考え始めたのです。
その上で、ノンプロ研らしい、ここにしかない講座にできればと考えています。
そこで、研究者の方が書かれた書籍をいくつか探していました。
以前は、栗原聡先生の『AIにはできない』をご紹介しました。
今回は、第二弾ということで、池谷裕二先生の『生成AIと脳~この二つのコラボで人生が変わる~』をご紹介します。
『生成AIと脳』書籍概要
本書は、扶桑社新書から2024年11月1日に出版されました。ページ数は280ページ。
著者の池谷裕二先生は、脳科学の分野で非常に著名な方です。書籍も多数出版されていますよね。
1970年生まれ、東京大学で薬学博士号を取得され、現在は東京大学大学院薬学系研究科で教授を務めていらっしゃいます。
専門は神経科学と薬理学で、特に海馬や大脳皮質の可塑性に関する研究で知られています。
『生成AIと脳』書籍の構成と各章のポイント
この書籍は、全6章で構成されています。各章の概要を簡単にご紹介しましょう。
第1章 生成AIとは何か
この章では、生成AIの基本的な概念から、ディープラーニングがどのように学習するのか、アノテーションとは何かといった技術的な側面まで、幅広く解説しています。
また、AIの歴史を第1次ブームから第3次ブームまで振り返り、現在の主要な生成AIについても詳しく触れています。
第2章 人生を変える生成AIを使いこなすスキル
ここでは、生成AIを使いこなすための具体的なスキル、特にプロンプトの技術について詳しく解説しています。
OpenAIのプロンプトのコツなど、実践的な情報も含まれています。
さらに、生成AIの特性を理解し、どのように付き合っていくべきかという、より広い視点からの考察も展開されています。
第3章 「私」よりも「私」のことを知る存在
この章は、非常に興味深いタイトルですよね。
「心」に関わる部分は、AIより人間のほうが得意のように見えますが、本当にそうでしょうか。
生成AIが人間の心をどこまで理解できるのか、カウンセリングや医療分野、教育などの領域での、意外な研究結果が紹介されています。
第4章 生成AIが抱える10の問題
生成AIが抱える課題、倫理的な問題、プライバシー、責任の所在など、様々な角度から議論を展開しています。
ここでは、生成AIの進化に伴い、今まで以上に人間の努力が必要になるという意見が述べられています。
第5章 「新しい道具」がもたらす新しい脳の使い方
この章では、生成AIの登場によって、人間の思考プロセスがどのように変化するのかを考察しています。
生成AIによって、人間が苦手なことから解放されるというメリットに焦点を当て、それが具体的に何を意味するのかを掘り下げています。
個人的に最も刺さった章でした。後ほど詳しく解説します。
第6章 生成AIは未来を導く「神」なのか?
最終章では、生成AIに意識や理解力はあるのか、社会にもたらす影響、そして共存のあり方について、深く考察しています。
AIとは何か、どう付き合っていくべきか、という根本的な問いに対する、著者なりの答えが示されています。
特に印象に残った点:人間らしいとはどういうことか
この本を読んで、特に印象に残った点を紹介します。
Google効果とは
「Google効果」をご存知でしょうか?
インターネットが生まれる前は、当然ながらGoogle検索もありませんでしたが、誕生とともに爆発的に普及しました。
それによって、私たちの脳はどのような影響を受けたのでしょうか。
研究によると、記憶力は低下する一方で、どこに情報が保管されているかという記憶力は上昇したというのです。
記憶という苦手なことから開放されて、より人間らしいことに脳のリソースを集中できるようになったということです。
では、生成AIの登場によって、どんな苦手なことから開放されて、どんな人間らしいことに脳のリソースを集中できるようになるのでしょうか。
人間が得意とされていることは本当に得意?
創造力、直感、気配り。
これらは、一般的に人間の方がAIよりも得意とされています。
しかし、池谷先生は、必ずしもそうではないと指摘しています。AIの方が、これらの分野で力を発揮することがあるというのです。
ここで重要なのは、「大事」とされていることだからといって、「得意」とは限らないということです。
創造力を働かせよう、直感も大事、気配りを大切にしよう…、苦手だからこそ「大事」と言われ続けてきたという側面もあり得るのです。
こういった「思い込み」が「人間らしさ」の見極めを邪魔する可能性もあるということは、今後生成AIと付き合う上で、心に留めておくべきと感じました。
まとめ:生成AI時代の人間のあり方
この本を読んで、生成AIとの付き合い方について、改めて深く考えるきっかけになりました。
技術的な知識ももちろん大切ですが、それ以上に、生成AIが私たちの社会や脳にどのような影響を与えるのかを理解し、どのように共存していくかを考えることが重要だと感じました。
生成AIは、私たちの得意なこと、苦手なことを再定義し、人間らしさとは何かを問い直すきっかけを与えてくれるのかもしれません。
皆さんも、ぜひこの本を手に取って、生成AIと脳、そして人間らしさについて、一緒に考えてみませんか?
以上、「『生成AIと脳』から学ぶ、人間らしさの本質とは」についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!