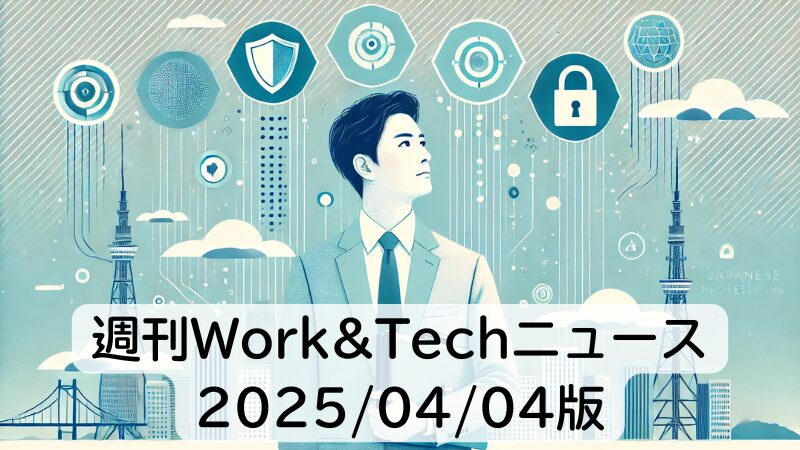
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
「週刊Work&Techニュース」 2025/04/04版をお送りします!
今週のワークとテックの主なニュースをざっとチェックし時流をつかんでいただくことができますよ。
では、行ってみましょう!
フィッシング攻撃の80%が日本狙い なぜそこまでターゲットになるのか?
日本プルーフポイントの調査によると、国内でDDoS攻撃および電子メール攻撃が急増していることが明らかになりました。特に2024年12月以降、日本の主要銀行や決済サービスに対するDDoS攻撃が激化しています。
電子メールを経由した攻撃も急増しており、特にフィッシング攻撃が爆発的に増加しています。2021年には月間3800万通だった新種のフィッシングメールが、2024年12月には2億6200万通、2025年2月には5億7500万通に達しています。多くのフィッシング攻撃は認証情報を狙うクレデンシャルフィッシングであり、「Microsoft 365」や「Google Workspace」のアカウントを標的にしています。
特に注目すべきは、日本を標的とする攻撃の割合が急増していることで、2025年2月には全世界の攻撃の80.2%が日本をターゲットにしていることが判明しました。
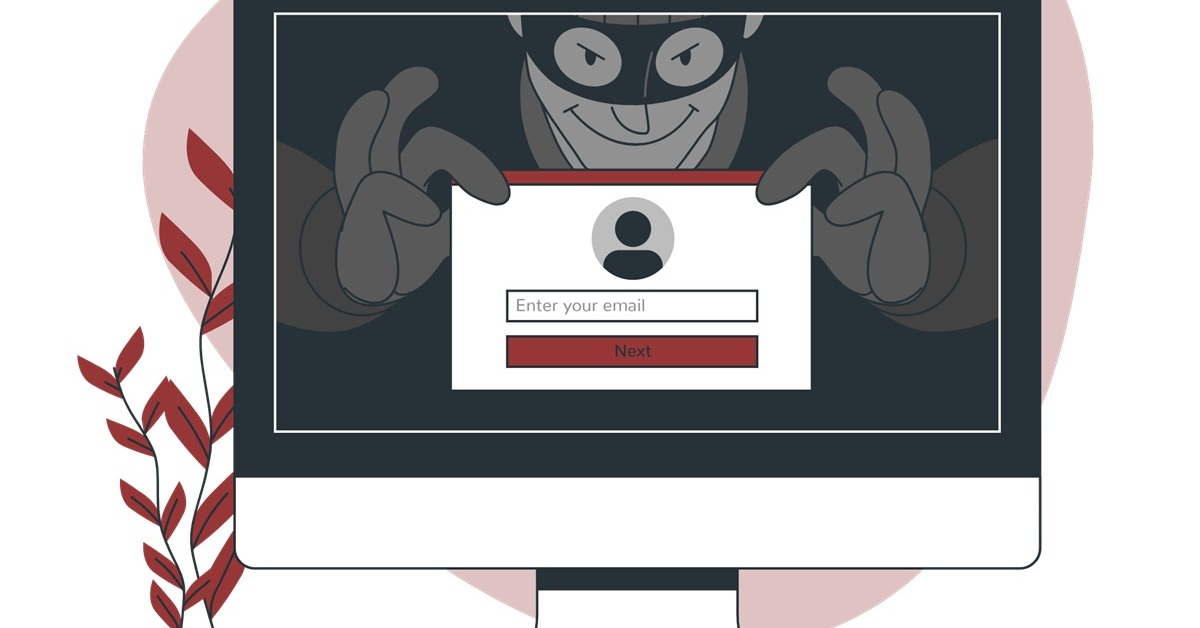
「なぜ日本がこれほどまでに狙われるの?」って思いますよね。実は、それにはいくつか理由があるんです。
まず、日本は経済的に豊かな国で、大きな会社や銀行がたくさんあります。攻撃する側から見れば、それだけ「おいしい」ターゲットが多い、ということなんですね。それに、私たち自身の個人情報、例えば住所や名前、電話番号、クレジットカードの情報なんかも、残念ながらインターネットの裏側、ダークWebと呼ばれるところでは高く売買されている、という現実もあるんです。
もう一つ、日本の会社の中には、デジタル化、つまりITの活用が少し遅れているところもあって、サイバー攻撃への備えが十分じゃないケースも少なくない、と言われています。
以前は、フィッシング詐欺のメールって、どこか日本語が不自然だったりして、「あ、これ怪しいな」って気づきやすかったんですけど、最近はAI、特に文章を作るのが得意な生成AIの技術がすごく進歩したので、まるで日本人が書いたような、とても自然な文章の詐欺メールが作れてしまうんです。
そうすると、私たちも本物のメールと見分けるのが難しくなってしまって、うっかり騙されてしまう…そんなケースが増えていると考えられています。本当に、他人事ではない注意が必要な状況ですよね。
OpenAI、新たな「オープンウェイトの言語モデル」公開へ–今後数カ月で
OpenAIが2019年のGPT-2以来となる「オープンウェイト」の言語モデルを今後数カ月以内に公開する計画を発表しました。サム・アルトマンCEOはSNS「X」への投稿で、「推論能力を備えた強力な新しいオープンウェイト言語モデル」の開発を進めていることを明らかにしました。
この発表は、中国のAI企業DeepSeekやMetaのLlamaモデルなど、オープンなアプローチを採用する競合他社からの圧力が高まる中で行われました。
OpenAIは開発者向けイベントを米国、欧州、アジア太平洋地域で開催し、フィードバックを集めるとともに初期プロトタイプを紹介する予定です。

「オープンウェイトモデル」って、ちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんね。これは、AIを作る時の考え方の一つなんです。完全に情報を公開する「オープンソース」と、企業の秘密としてあまり情報を出さない「クローズド」なモデル、ちょうどその中間のようなイメージでしょうか。
AIが学習して賢くなる過程で、「重み(ウェイト)」というたくさんの数値が決まっていくんですが、これがAIの答えを決める大事な要素なんです。オープンウェイトモデルでは、この「重み」の部分を公開するんですね。そうすると、開発者の人たちは、AIを一から全部作り直さなくても、この「重み」を元にして、新しい情報を教えたり、自分たちの目的に合わせて調整したりできるんです。
企業にとっては、こういうモデルがあると、比較的コストを抑えながら、自分たちの会社に合ったAIツールを作りやすくなる、というメリットがあります。例えば、社内にある資料を読み込ませて、その会社のことに詳しいAIアシスタントを作る、なんてこともやりやすくなるわけです。
サム・アルトマン氏さんも、「オープンソースの流れに乗り遅れていたかも」と以前話していたことがあって、今回の発表はその流れに沿ったものと言えそうです。
退職代行サービスが4月1日の実績報告 新卒者からの依頼数・理由に反響「エイプリルフールだよな」「あるあるやね」
退職代行サービス「モームリ」(運営:アルバトロス)が4月1日、公式X(旧ツイッター)で同日の退職代行実績を報告し、注目を集めています。報告によると、その日だけで合計134名からの依頼があり、そのうち5名が2025年度の新卒社員だったことが明らかになりました。
退職理由も公表しており、「社長が入社式の最中に新卒社員ともめて、みんなの前で怒鳴ったことに加え、廊下に出して『なめてんのか』と説教」(女性・事務関連)や「入職前の研修で講師の方の脅しのような言葉があり自信を無くしてしまった」(男性・医療関連)など、衝撃的な内容が並んでいます。
同社は「様々な理由はありますが、入社前に聞いていた内容が、実際に勤務すると全然違う…。入社直後に最も多い退職理由です」と説明しています。

4月になると、この「退職代行サービス」の話題、よく聞くようになりましたよね。特に新しく社会人になった方からの依頼もある、というのはちょっと考えさせられます。4月から6月くらいは、もう毎年の定番ニュースになりつつある感じです。
最近は、学生さんの方が企業を選ぶ「売り手市場」なんて言われますけど、だからこそ、会社側も入社前には良いことばかりを伝えてしまう、ということがあるのかもしれません。でも、いざ働き始めてみたら「聞いてた話と全然違うじゃないか…」となってしまう。このギャップが、入社してすぐに「もう辞めたい」と思ってしまう大きな理由の一つになっているようです。
ただ、辞める理由として「入社式で社長に怒鳴られた」とか「研修で脅しのようなことを言われた」とか、そういう言葉が出てくるのを見ると、唖然としますね…。
会社にとっても、何のプラスにもならない、まさに「百害あって一利なし」だと思うのですが。
人気殺到で制限していた「ChatGPT」画像生成、全ユーザーに開放
OpenAIが、ChatGPTの画像生成機能を無料ユーザーにも開放しました。この機能は3月25日に最初に導入され、スタジオジブリ風の画像を生成できることで爆発的な人気を集めていました。当初は有料プランのユーザーのみが無制限に利用できる特典でしたが、4月1日からすべての無料ユーザーも利用可能になりました。ただし、無料ユーザーは1日3枚までの制限があります。
この機能はGPT-4oモデルを活用しており、テキストプロンプトから詳細でリアリスティックな画像を生成できます。
人気の高さから、OpenAIは一時的に「GPUが溶けそう」と冗談めかして述べるほどのアクセス集中を経験し、ローンチ直後の1時間で100万人の新規ユーザーを獲得したとのことです。

「こんな絵が描きたかった!」が、もっと簡単にできるようになった、そんなニュースですね。ChatGPTに「こんな感じの絵を描いて」とお願いすると、AIがささっと描いてくれる機能、これが無料でも使えるようになったんです(1日3枚までですが)。
以前から、AIに絵を描いてもらう技術はあったんですが、なかなか思い通りの絵にするには、専門的な指示の出し方、いわゆる「プロンプト」のコツが必要だったりしました。でも、今回のChatGPTの機能により、普段話すような言葉でお願いするだけで、かなりクオリティの高い絵がつくれるようになりました。
ChatGPTが登場する少し前にも、Stable DiffusionとかMidjourneyとか、画像を作るAIがすごく話題になりましたけど、今回の件で、また画像生成AIのブームが来ている!という感じがしますね。
特に、「ジブリ風」というのが、世界中の多くの人が「ああ、あの感じね!」って分かる共通のイメージだったのが大きかったと思います。OpenAIのトップ、サム・アルトマンさんも自分のSNSアイコンをジブリ風にしちゃうくらいでした。
この「ジブリっぽさ」という分かりやすさが、AIのすごい技術を、もっとたくさんの人に身近に感じてもらうきっかけになった、そんな風に言えるんじゃないでしょうか。
TikTok、新会社設立へ=米投資家5割出資、近く発表―報道
米IT専門メディアのジ・インフォメーションは2日、中国系短編動画投稿アプリ「TikTok」の米事業について、トランプ米大統領が近く合弁会社設立を発表すると報じました。
新会社には米企業や投資家が約5割を出資し、中国親会社の字節跳動(バイトダンス)の持ち株比率を2割未満に引き下げる計画です。
TikTokを巡っては、米事業を売却しなければ米国内でのサービスを禁じる法律が1月に施行されており、トランプ氏は同月の就任直後、大統領令で法律の適用を75日間猶予していました。猶予の期限は5日に迫っています。
ポイントはいくつかあって、まず、元の親会社である中国のバイトダンスという会社の、新しい会社への出資割合をぐっと減らす(2割未満にする)という点です。これは、アメリカの法律で、敵とみなす国の会社があまり大きな力を持てないようにするルールがあるので、それに合わせようとしているんですね。
それから、TikTokでどの動画が表示されるかなどを決めている大事な仕組み、「アルゴリズム」については、新しい会社がバイトダンスから「使わせてもらう」形(ライセンス契約)で調整しているようです。
これも、中国政府が技術を国外に出すのを制限しているルールをうまくクリアするため、と考えられます。ただ、アルゴリズムの根本は中国側が持ち続けることになるので、「本当に安全なの?」「世論を操作されたりしない?」という心配の声が完全になくなるわけではない、という見方もあります。
この間に、あのAmazonがTikTokのアメリカ事業を買いたい、なんて話も出たようですが、アメリカ政府はあまり本気にしていない、という情報もあります。
まとめ
以上、「週刊Work&Techニュース」 2025/04/04版についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!

