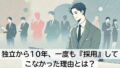みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
Googleの最新AI「Gemini 2.5 Pro」に搭載された「Deep Research」機能。
その驚くべきリサーチ能力を、ノンプログラマー向けコミュニティの事例でChatGPTとの比較も踏まえて徹底検証!
ということで、今回は「ChatGPT超え?Gemini 2.5 Pro『Deep Research』の衝撃!」です。
では、行ってみましょう!
AIリサーチ戦国時代? Deep Researchとは
最近、AIの世界は本当に進化が目覚ましいですよね。文章を書かせたり、画像を生成させたり、もはや驚くことにも慣れてきた感がありますが、今回ご紹介する機能もすごいですよ。
その名も「Deep Research」。
このDeep Researchは、AIがインターネット上の膨大な情報を深く掘り下げてリサーチし、詳細なレポートを作成してくれるというもの。似たような機能を持つAIは他にもあります。
例えば、X(旧Twitter)でおなじみのイーロン・マスク氏率いるxAIの「Grok」や、Google自身の軽量モデル「Gemini 1.5 Flash」、リサーチ特化型の「Perplexity」、そしてご存知「ChatGPT」など、まさにAIリサーチ戦国時代といった様相です。
これまで、この分野ではやはりChatGPTが頭一つ抜けている印象でした。
ただ、ネックなのが利用回数。月額3万円のProプランだとたくさん使えるのですが、月額3000円のPlusプランでは、月10回という制限があったので、「ここぞ!」という重要なリサーチにしか使えず、日常的なライトなリサーチは他のツールで…という使い分けを強いられていた方が多かったのでは?
そんな中、Geminiの最新モデル2.5 ProでもDeep Researchが使えるようになりましたので、「これは試さねば!」と思ったわけです。果たして、その実力やいかに?
Gemini 2.5 ProでDeep Researchを試してみた!
善は急げ、ということで早速試してみました。
お題は、僕が主宰している「ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会」(通称ノンプロ研)について。
ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会がより会員数を伸ばすための施策をレポートしてください。こんな風にお願いしてみました。すると、Geminiはリサーチの手順を提案してくれました。
- 「ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会」の現在の活動内容、ターゲット層(どのようなスキルを求めているか)、運営形式(オンライン/オフライン、頻度など)、現在の会員規模や集客方法を調査する。
- 同様のノンプログラマー向け、またはスキルアップを目的とした他のコミュニティや研究会が、どのように会員数を増やしているかの成功事例を調査する。
- …(その他、市場分析や具体的な施策提案に向けた調査項目が続く)
1.5 Flashのときとこの流れは同じです。
確認の上「リサーチ開始」ボタンをポチッとするとリサーチが開始します。
驚愕のアウトプット!その詳細を覗いてみよう
待つこと約10分。
時間は多少かかりますが、参照したソース(情報源)の数がすごい。なんと104件!レポートに直接引用されていないものも含めてですが、これだけの情報を短時間で収集・分析しているわけです。
ちなみに、以前ChatGPTで同様のリサーチを依頼した際のレポート文字数は約1万3000文字でしたが、今回のGeminiによるレポートは、なんと約2万7000文字!倍以上のボリュームです。
では、その中身を少しだけご紹介しましょう。レポートは主に「現状分析」「市場環境と成功モデル」「施策」「結論と提言」といった章立てで構成されていました。
現状分析:ノンプロ研を丸裸に?
まずはノンプロ研自体の分析から。
ノンプロ研は、株式会社プランノーツ 1 が運営し、一般社団法人ノンプログラマー協会 10 と連携する学習コミュニティである。その根幹には、「プログラミングを本職としないビジネスパーソン」(ノンプログラマー)が、ITスキルを習得するための「学習意欲が高く、心理的安全性が高い環境」を提供するという目的がある 1。多くのノンプログラマーが直面する「学ぶ環境がない」「相談できる仲間がいない」といった課題 12 を解決し、メンバー同士が「学び合いながらスキルを磨ける環境」を提供することを目指している 1。究極的には、「日本の『働く』の価値を上げる」という大きな目標を掲げている 8。おぉ、ちゃんと調べてくれている…。僕たちが大切にしている「心理的安全性」や「学び合い」といったキーワードもしっかり拾ってくれていますね。
この後、ターゲット層の分析、提供しているコア・バリュー、具体的な活動内容、提供コンテンツ、運営体制、そして現在の会員状況や集客チャネルについて、なんと4000文字以上にもわたって詳細に分析されていました。
正直、ここまで客観的かつ詳細に自分たちのコミュニティを分析されたのは初めてで、「完璧です…」と思わず呟いてしまいました(笑)。
市場環境と成功モデル:競合から学ぶ
次に、市場環境と類似サービスの成功モデルについて。
ここでは、ノンプログラマー向け、あるいはスキルアップ系のコミュニティとして、いくつかの事例が挙げられていました。例えば、「人生逃げ切りサロン」や「リベシティ」など。
正直、「うーん、ノンプロ研とはちょっと性格が違うかなぁ」と思う部分もありましたが、それでも彼らがどのように会員数を伸ばしてきたのか、という成功事例を知ることは非常に有益です。
それに、これらの情報を自分で一つ一つリサーチするとなると、相当な時間と労力がかかりますよね。それをAIが代行してくれるのは、本当にありがたいです。
具体的な施策提案:ここまで提案してくれるのか!
そして、いよいよ具体的な施策提案のパートです。これがまた、すごかった…。
- コンテンツと学習パスの多様化: 短い動画コンテンツやチートシート、テンプレートなどを提供してはどうか。
- メンター制度の導入: 経験豊富なメンバーが新メンバーをサポートする仕組み。
- 地域ごとのオフラインミートアップ: オンラインだけでなく、対面での交流機会も設ける。
- ノンプロ研認定制度: スキルを証明する独自の認定制度を作る。
- リードマグネットによるリード獲得: 無料の価値あるコンテンツを提供して見込み客を集める。
- 各種SNS戦略: 「ノンプロ研は複数のSNSプラットフォームを利用しているが [18, 26]、その戦略は十分に練られているとは言い難い」…ぐぬぬ、耳が痛い(笑)。的確な指摘、ありがとうございます…。
- 新規メンバー向けチャンネルの作成: 新しく参加した人が交流しやすい場を作る。
- メンバーアワードの導入: 活躍したメンバーを表彰する制度。
- 専用ランディングページの作成: これは、前から課題と思っていたところ…。やっぱり重要か。
ここで挙げたのは、僕が「おっ、これはいいね!」と思ったものの一部です。実際には、これ以外にも本当に網羅的で、具体的な施策がズラリと並んでいました。
よくここまで考えられるなぁと感心しきりです。
結論と提言:愛あるダメ出し?未来への道筋
最後に、レポートは結論と提言で締めくくられていました。
ノンプロ研は、ノンプログラマーがITスキルを学び、互いに支え合うためのユニークで価値あるコミュニティとして確固たる地位を築いている。その心理的安全性、活発な内部活動、そして「学び合い」を重視する文化は、大きな強みである。
しかし、持続的な会員数増加という目標達成のためには、現状の強みを維持しつつも、より戦略的かつ積極的なアプローチが必要となる。特に、以下の領域における改善と投資が不可欠である。
マーケティングとリーチの抜本的強化: 現在、ノンプロ研の価値は外部に十分に伝わっていない可能性がある。SEO、コンテンツマーケティング、ターゲットを絞ったSNS活用、そして限定的な有料広告の試行を通じて、潜在的なノンプログラマー層へのリーチを大幅に拡大する必要がある。特に、メンバーの具体的な成功事例を前面に出し、スキル習得がもたらす実利的なメリットを強調することが重要である。
価値提案の明確化と差別化: 月額料金に見合う独自の価値を、ウェブサイトやあらゆるコミュニケーションチャネルで明確に、かつ説得力を持って提示する必要がある。学習パスの導入、マイクロクレデンシャル、限定リソースの提供などは、その価値を高め、差別化を図る上で有効な手段となる。
コミュニティ主導の成長促進: 既存メンバーのエンゲージメントと貢献意欲は、ノンプロ研の貴重な資産である。メンター制度の導入、UGC(ユーザー生成コンテンツ)促進策、アンバサダープログラムや紹介制度の検討などを通じて、メンバー自身がコミュニティの成長を牽引する仕組みを構築することが望ましい。
データに基づいた意思決定: 会員数、エンゲージメント、定着率、ウェブサイトのコンバージョン率など、主要なKPIを継続的に追跡・分析し、施策の効果を測定し、データに基づいて戦略を修正していく文化を醸成することが不可欠である。
本レポートで提言した施策は、短期的に着手可能なものから中長期的な視点が必要なものまで多岐にわたる。優先順位をつけ、段階的に実行に移すことで、ノンプロ研は現在の基盤の上にさらなる成長を築き上げ、より多くのノンプログラマーのスキルアップとキャリア形成に貢献し、ひいては日本の「働く」価値向上というミッション達成に近づくことができると確信する。…もう、ただただ「ありがてぇ…」の一言です。
現状の強みを認めつつも、課題を的確に指摘し、具体的な改善策と進むべき方向性を示してくれる。まるで、優秀なコンサルタントに壁打ちしてもらっているような感覚でした。
結論として、GeminiのDeep Research機能は、ものすごく優秀でした。
Gemini vs ChatGPT:どっちが使いやすい?
では、先行するChatGPTのリサーチ機能と比べてどうだったか?
個人的に感じたGeminiのDeep Researchの利点はコチラです。
- 手間が少ない: ChatGPTだと、リサーチの方向性について何度かやり取りが必要な場合がありましたが、Deep Researchは最初に目的を伝えれば、あとはリサーチ手順の提案を確認するだけ。ある程度「おまかせ」で進められるのは楽ですね。(もちろん、細かく指示したい場合はChatGPTの方が良い場面もあるので、これは一長一短とも言えます)
- 精度と細やかさがすごい: 今回のノンプロ研のレポートを見る限り、情報の網羅性、分析の深さ、提案の具体性において、非常に高い精度と細やかさを感じました。
- 検索能力が高い?: これは僕の推測ですが、Googleのサービスだけあって、Web上の情報を収集・分析する能力が非常に高いのかもしれません。参照ソースの多さも、それを裏付けているように感じます。
GeminiのDeep Research、誰がどうやって使えるの?気になる利用条件
さて、こんなにすごいDeep Research機能ですが、誰でもすぐに使えるのでしょうか? ここが重要ですよね。
- 個人ユーザー: Googleの有料プラン「Gemini Advanced」に登録していれば利用できます。
- 法人ユーザー: 「Google Workspace」の特定のプランに登録していれば利用可能です。
そして、気になる利用回数制限ですが、実は公式には明確な回数は公表されていません。ただ、ユーザーの報告によると、「1日あたり20回程度の制限があるのでは?」という報告がいくつか見られます。
1回のレポート作成に10分程度かかり、内容も非常に濃いことを考えると、1日に20回も使えれば、多くの人にとっては十分すぎるのではないでしょうか。
少なくとも、以前のChatGPT Plusの月10回制限に比べれば、格段に使いやすくなっていると感じます。
まとめ:Deep Researchは「買い」なのか?
今回は、Gemini 2.5 ProのDeep Research機能を試してみて、その衝撃的な実力の一端をご紹介しました。
ノンプロ研という具体的なテーマでレポートを作成してもらいましたが、その分析の深さ、提案の質、そして圧倒的な情報量には、衝撃というかむしろ感動すら覚えました。
皆さんも機会があれば、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
以上、「ChatGPT超え?Gemini 2.5 Pro『Deep Research』の衝撃!」についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!