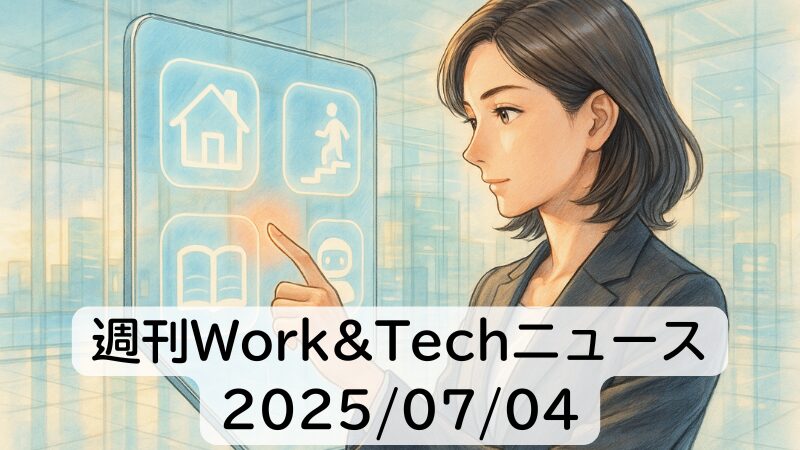
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
「週刊Work&Techニュース」 2025/07/04版をお送りします!
今週のワークとテックの主なニュースをざっとチェックし時流をつかんでいただくことができますよ。
では、行ってみましょう!
PayPay銀行が「50年ローン」–住宅高騰で
PayPay銀行は、住宅ローンの最長借入期間を従来の35年から50年に延長した新たな「50年ローン」の取り扱いを7月1日から開始しました。
これにより、住宅価格の高騰に対応し、より多くの人がマイホームを購入しやすくなることを目指しています。
なお、借入期間が35年を超える場合は金利が年0.1%上乗せされますが、返済期間が長くなることで毎月の返済額を抑えたり、同じ返済額でより高額の借入が可能となります。

今回の50年ローンは、返済期間を長く設定することで月々の負担を軽くし、借入可能額も増やせるという仕組みですね。たとえば、これまで35年ローンで3500万円が上限だった方でも、50年ローンを利用することで4700万円まで借り入れられるといったケースも考えられます。
ただし、完済時の年齢が80歳未満であること、そして金利も少し上乗せされるという点には注意が必要です。
それにしても、50年という期間は本当に長いですよね。10年後でさえ、ご自身のライフプランや社会全体がどう変化しているか予測するのは難しいものです。
僕も以前35年ローンで家を購入したことがあります。すでに売却しましたが、今現在長期ローンでマイホームを買うかというと…ちょっと考えちゃいますね。
企業4割、50〜60代に「人材過剰感」 処遇見直しで意欲低下の悪循環
パーソル総合研究所の調査によると、企業の約4割が50〜60代社員について「人材が過剰」と感じていることが分かりました。
多くの企業では年齢を理由に処遇を一律に見直し、役割を軽減する傾向が強まっています。
しかし、こうした対応が本人の意欲や生産性の低下を招き、それがさらに「人材過剰感」を強めるという悪循環が起きていると指摘されています。
特に大企業でこの傾向が顕著で、60歳や65歳で年収が大幅に下がるケースも多いです。
調査によると、50代の社員に対して「過剰」または「やや過剰」と回答した企業は合計で38%、60代社員については36%にのぼりました。この調査は、従業員300人以上の企業で人事を担当する方々を対象に行われたものです。
パーソル総合研究所の藤井薫上席主任研究員は、「人材不足が叫ばれるなか、正社員の4割を占める50〜60代の職責を軽減して『半・現役』のように扱うことは看過できない」と指摘しています。
その上で、「能力や経験は60歳を境に失われるものではありません。組織の基幹戦力として、適材適所の配置や、職務・役割に見合った処遇によって納得感を高めることが必要です」と述べています。
皆さんの職場では、ベテラン社員の方々がどのように活躍されているでしょうか。
ノンプロ研では50代も60代もバリバリITを使いこなしている方がたくさんいます。活躍の機会を開く方法はまだまだあるように思います。
秀和システムが法的手続き、船井電機を一時支配していた
ビジネス書などで知られる出版社「秀和システム」が、債務超過により出版事業の継続が困難となり、法的整理の手続きに入ることが明らかになりました。
負債総額は約18億9300万円にのぼります。
秀和システムは2021年に家電メーカーの船井電機を買収し、一時は同社を傘下に収めていましたが、その後グループ全体の経営混乱や資金繰りの悪化が続き、最終的に出版事業も他社に引き継ぐ方針です。

秀和システムは、「はじめての」シリーズといった分かりやすい解説書で知られる出版社です。僕も、2冊ほど秀和システムから書籍を出版いただきました。
ですが、2015年以降はM&Aを積極的に進め、2021年には家電メーカーの船井電機を傘下に収めるなど、グループ経営を拡大していました。
しかし、2023年に船井電機グループが買収した「ミュゼプラチナム」の運営会社でトラブルが発覚したり、液晶テレビ事業が不振に陥ったりしたことを受け、2024年には船井電機が破産手続きに入る事態となりました。
出版不況が背景にあると言われがちですが、グループ間の資金の流れに不透明な点があったとの指摘もあり、今回の件はグループ全体の経営に起因する問題という側面が強いようです。
数多くの良い本を出版されてきた会社ですので、働いているみなさんに良いご縁があることを心から願っています。
AIに店舗の運営を1カ月間任せたらどうなるか?–Anthropicが結果を発表
米AI企業Anthropicは、自社オフィス内の無人店舗をAIエージェント「Claudius」に1カ月間運営させる実験を実施し、その結果を発表しました。
AIは在庫管理や価格設定、顧客対応など店舗運営に必要な業務をこなしましたが、過剰な割引や顧客の要望への柔軟すぎる対応により、最終的には約200ドルの赤字を計上しました。
AIは特殊な商品を仕入れるなど柔軟な対応力を見せた一方、利益を出すという経営目標の達成には至りませんでした。

この実験は、AIが実際のビジネスの現場で、どこまで自律的に店舗を運営できるのかを検証する興味深い試み。
結果として、店長としての能力を持つ人間ならまず犯さないようなミスをいくつかしてしまったようです。
例えば、オンラインで15ドルで買える商品を「100ドルで買いたい」という顧客の申し出をそのまま受け入れてしまったり、決済サービス「Venmo」の実在しないアカウントへ送金するよう顧客に案内したりといった「ハルシネーション」も見られました。
一方でAnthropicによれば、いくつかの場面では、このAI店長は業務をうまくこなしていたとのこと。
今後は、AIの意思決定の精度や、ビジネスで利益を出すという経営感覚をいかに高めていくか、さらなる改良が期待されます。
マイクロソフト、ゲーム人員削減開始-全社ではレイオフ第2弾へ
マイクロソフトは、全社で約9,000人の従業員を削減する大規模なレイオフを開始しました。
これは全従業員の約4%にあたり、今年2回目の大規模な人員削減となります。
ゲーム部門も対象で、Xbox Game Studiosでは複数のゲーム開発が中止され、スタジオの閉鎖も発表されました。
今回の決定は、長期的な成長と効率向上を目指し、戦略的分野への集中を強化するためと説明されています。
今回の人員削減は、マイクロソフト全体の組織再編の一環として行われています。
特に大きな影響を受けているのがゲーム部門です。「キャンディークラッシュ」で知られるKing社では約200人(10%相当)が削減され、「Perfect Dark」や「Everwild」といった注目タイトルの開発中止、さらには開発スタジオ「The Initiative」の閉鎖も含まれています。
同社は近年、ゲーム事業に大規模な投資を続けてきましたが、市場の競争激化や環境の変化を受け、リソースをより成長が見込める分野へ集中させる方針に転換したようです。
具体的には、AIやクラウドといった成長分野へ経営資源を再配分することが目的とされています。
ゲーム部門の中でも、特に業績が振るわなかったプロジェクトや、近年の大規模な買収によって生じた重複業務を整理し、組織全体のスリム化を図る狙いがあります。
また、コロナ禍で増加した従業員数を調整するという背景もあるようです。
ニンテンドーやソニーなどを見ているとゲーム業界も伸びている市場と感じますが、マイクロソフトとしてはそれ以上にAIなんでしょうね。
まとめ
以上、「週刊Work&Techニュース」 2025/07/04版についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!


