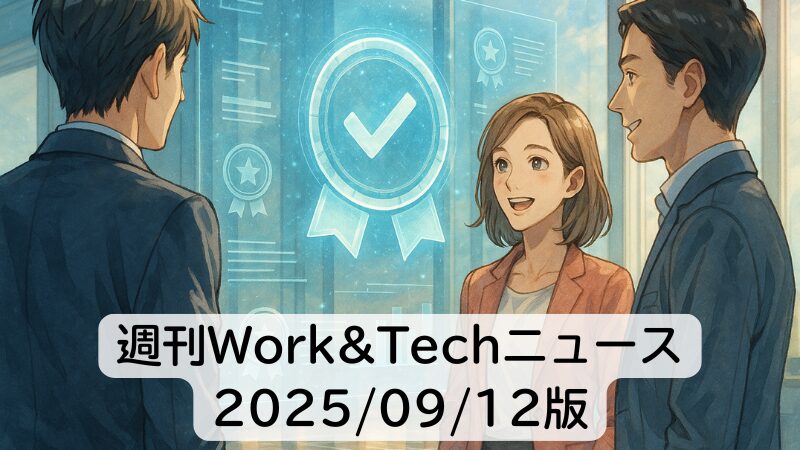
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
「週刊Work&Techニュース」 2025/09/12版をお送りします!
今週のワークとテックの主なニュースをざっとチェックし時流をつかんでいただくことができますよ。
では、行ってみましょう!
OpenAIが人材領域「Jobs Platform」公表——ChatGPT内で「学習→認定→バッジ提示→応募」までの一連のプロセスを完結
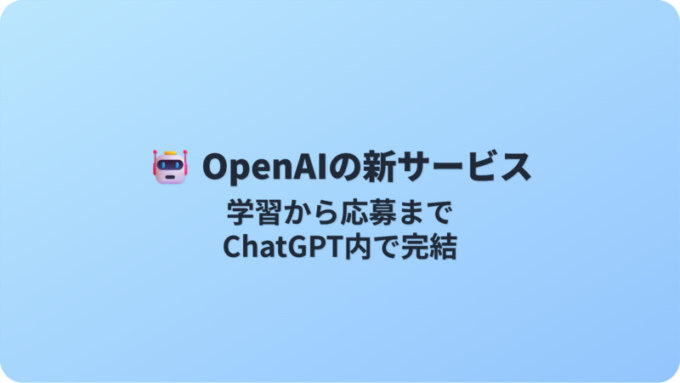
OpenAIは、新たに人材領域に参入し「Jobs Platform」を発表しました。
この仕組みでは、ChatGPT上でスキルを学び、習得度を確認するテストを受け、合格すれば認定バッジが付与されます。
そのバッジを提示することで企業への応募まで進められ、一連の流れがChatGPT内で完結するのが特徴です。
学びと就職活動をシームレスにつなぐ新しい形として注目を集めています。
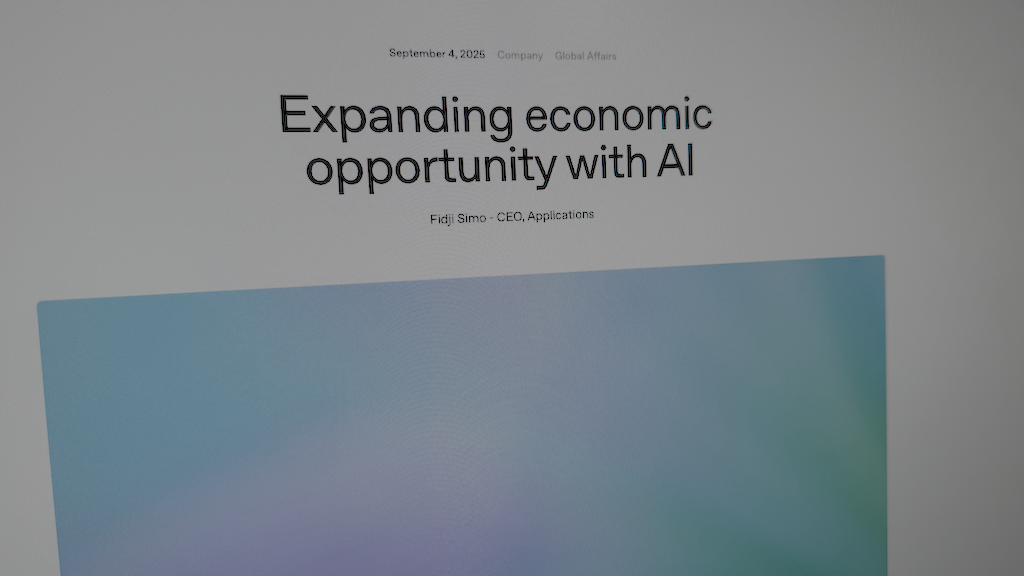
今回の「Jobs Platform」は、学習から採用応募までを一つのアプリ内で実現しようとする、非常に画期的な試みです。
従来は学習サービス、資格認定、求人サイトがそれぞれ分かれていましたが、これを統合し効率化しています。
ChatGPTのStudy modeでの学習履歴、認定試験の結果、さらにはChatGPTでの実際の作業成果まで、すべてが同一プラットフォーム内で蓄積・可視化され、それをもとに認定バッジが与えられる仕組みです。
このバッジはスキル証明の代わりとなり、企業は応募者の能力を簡単に確認できるようになります。
今後、この認定バッジを企業が採用プロセスでどれだけ参考にするかが、普及の鍵となりそうです。大人のリスキリングという観点からも、非常に注目すべきニュースと言えるでしょう。
データ全消し、嫌みメール… 職場を困らせる「リベンジ退職」の現実
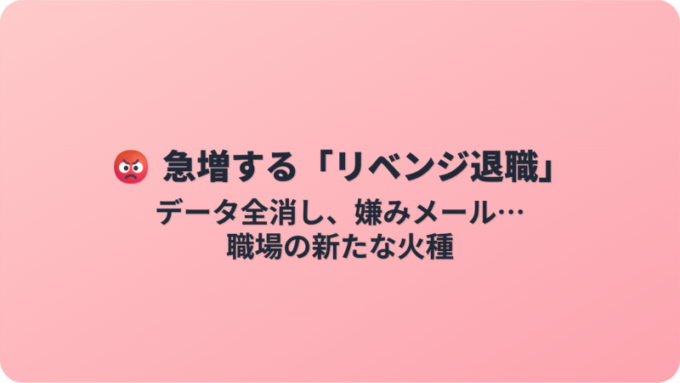
仕事を辞める際、職場に大きな迷惑をかける「リベンジ退職」が問題になっています。
職場で自分の上司や同僚らが退職した際に、そんな困った事態を経験した人が約1割いることが、経営コンサルタント会社「スコラ・コンサルト」が行った調査で分かりました。
パソコン内のデータを消去したり、社内に嫌みを書いたメールを送ったりといった行動が報告されています。

「リベンジ退職」とは、不満や怒りを抱えたまま会社を辞め、その過程で職場に意図的な迷惑を与える行為を指します。
調査によれば、「引き継ぎをしない、繁忙期に退職する、内部情報を暴露する」といった報復的な行動や、「担当業務のデータを消す」「不満や悪口を職場の一斉メールで送る」といった経験をした人が約1割いるとのことです。
背景には、長時間労働や人間関係のストレスなど、働き方に対する蓄積された不満があると考えられます。
しかし、データ消去やいやがらせ行為は、法的なトラブルにもなり得る危険な行動です。企業側も退職時のデータ管理やセキュリティ体制の強化を進めていますが、働く側も円満に退職できる環境づくりが大切です。
ただ、「引き継ぎをしない」「繁忙期に退職する」といった点は、会社側の体制に問題があるケースも考えられ、お互いに配慮が必要なポイントかもしれません。
グーグル「Gemini」、無料でどこまで使える?公式の上限値が公開

グーグルはAIサービス「Gemini」の無料プランに対する公式の利用上限値を公開しました。
無料ユーザーは、上位モデルの「2.5 Pro」を使ったプロンプトの上限は一日に最大5回、画像生成は100枚、音声まとめ(Audio Overviews)は20回までと制限されています。
また、「Deep Research」による分析レポート作成は1日5件までという上限が設けられています。

Geminiの無料プランは「試してみたい」「簡単な作業をしたい」といった個人利用に向いています。
文章生成や画像生成、音声要約などの機能を使えますが、より多く使いたい場合は有料プランの検討が必要です。
この発表がニュースになっている背景には、AI企業が具体的な利用回数やトークン制限を曖昧にする傾向があるからです。ユーザーが入力する内容によって必要となる計算能力が大きく異なるため、上限を明示しづらいという事情がありました。
今回、上限値が明らかになったことで、ユーザーは自分の使い方に合わせてプランを選択しやすくなります。こうした制限は、多くのAIサービスで公平な利用を保ち、システムへの過度な負担を避けるために設けられています。
Microsoft、Anthropic技術を一部使用へ OpenAIから多様化

Microsoftは、人工知能の活用先を広げるため、米新興企業Anthropicの技術を一部利用すると発表しました。
従来、同社は主にOpenAIの技術を基盤にしてきましたが、今回の動きでAIに関する選択肢が拡大します。
Microsoftは、生成AIの分野で競争力を高める狙いがあるとみられます。
Microsoftはこれまで、会話型AI「ChatGPT」などを提供するOpenAIと多額の出資を通じて深く連携してきました。
しかし近年、その関係性には課題も生じていました。技術や情報の共有タイミングの不透明さや、OpenAIの経営方針が変化するリスクなどが挙げられます。
実際に、OpenAIが買収した企業がMicrosoftと競合関係にあり、その技術情報を共有するかどうかで揉めたこともあったようです。
そこで、安全性を重視したAI「Claude」で注目されるAnthropicの技術を取り込むことで、リスクを分散する狙いがあります。
また、MicrosoftはExcelやPowerPointの作成においては、Anthropicのモデルのほうが優れているという見方も示しており、生成AI市場での競争が激化する中、複数の技術を取り入れることで、より柔軟で安定したサービスをユーザーに提供できると期待されています。
職場の新潮流、仕事にしがみつく「ジョブハギング」は生存戦略か、現状維持の罠か 有効な見分け方
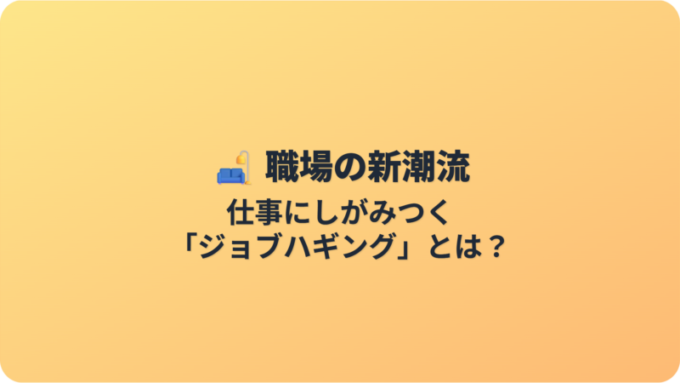
最近、「ジョブハギング」という言葉が注目されています。
これは現在の仕事や職場にしがみつき、あえて転職や挑戦を避ける行動を指します。
不安定な経済や人材流動化の中で、生存戦略として一定の合理性がある一方で、成長の機会を逃す現状維持の罠とも言われています。
自分の働き方を考える上で、重要なキーワードになりそうです。

ジョブハギングは、主にアメリカで見られる安全志向の新しい働き方の概念です。背景には、景気の不透明さやリストラへの不安、また、AIが人間の仕事に取って代わる可能性といった社会情勢があります。
ただ、日本ではもともと継続的な雇用が前提にあるため、アメリカほど景気の影響を受けづらく、そもそも「ジョブハギング状態」の人も少なくないかもしれません。
安定を求めるこの姿勢も、行き過ぎると本人の成長がストップし、やる気が上がらないといったデメリットがあります。職場にとっても、従業員が仕事にエネルギーを向けず、創造性を発揮しなくなるのは問題です。
個人的には、無理に転職を繰り返す必要はないと思いますが、今の場所で挑戦を続ける姿勢は大切ですし、職場もそれを後押しするべきだと感じます。前向きにチャレンジすることこそが、結果的に安定につながるのではないでしょうか。
まとめ
以上、「週刊Work&Techニュース」 2025/09/12版についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!

