
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
「いつか自分の本を出してみたい…」そう思ったことはありませんか?
この記事では、特別な実績がない方でも技術書の商業出版を実現するための、具体的で再現性の高いロードマップをご紹介します。
ということで、今回は「「すごい人」じゃなくても本は出せる!再現性の高い商業出版への4ステップ」です。
では、行ってみましょう!
はじめに:出版への道は一つじゃない
先日、ジャーナリストの佐々木俊尚さんのVoicyで、本の出版に関する非常に興味深い放送がありました。プロの書き手である佐々木さんのお話は、さすがの説得力でしたね。
「出版をしたいのであればnoteを書こう」というお話で、著書に『アンパンマンと日本人』など多数、編集者としてもご活躍の柳瀬博一さんも、以前同じことをおっしゃっていました。
まさにそれが王道の一つなんだろうな、と僕も思います。
でも、実は「技術書」というジャンルに限って言えば、もっと着実に、再現性高く出版の夢を叶える方法があるんです。
これは、僕が主宰するコミュニティ「ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会(通称:ノンプロ研)」の何人もの仲間たちが出版を実現してきた、実績のある道筋です。
特別な才能は必要ありません。必要なのは、正しいステップを知り、一歩を踏み出す勇気、そしてそれをコツコツと続けることです。
今日は、その具体的なロードマップを余すところなくお伝えしたいと思います。
商業出版へのロードマップ【完全版】
では早速、そのステップをご紹介します。一歩ずつ、着実に進んでいきましょう。
ステップ1:書くための「型」を身につける(ノンプロ研「技術ライティング講座」)
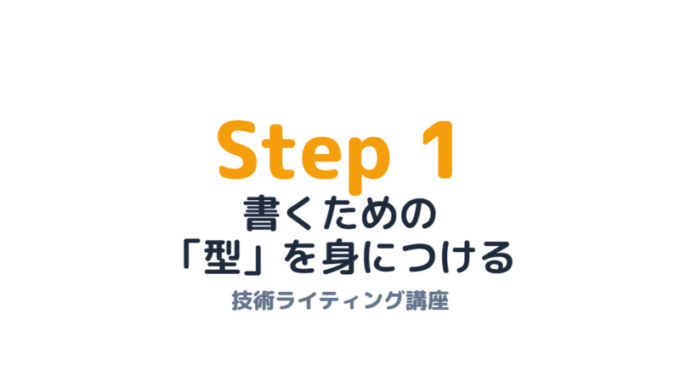
「よし、本を書くぞ!」と思っても、いきなり何万字もの文章を書くのは、流石に無理な話です。
そこで最初のステップは、書くための「土台」を作ることです。
いきなり宣伝っぽくなってしまって恐縮ですが、ノンプロ研では「技術ライティング講座」という、まさにそのための講座を用意しています。
この講座は、今まで文章を書く経験がほとんどなかったノンプログラマーの方が、ご自身の学んだことや経験を「アウトプットして価値に変える」ためのスキルを学ぶことを目的としています。
まずはX(旧Twitter)での短いツイートから始めます。
短い文章なら、気軽に始められますよね。そこから少しずつ文字数を増やして、ブログやnoteの記事へ。そして最終的には、数万字規模の「技術同人誌」の執筆を目指します。
このように、小さなアウトプットから段階的にサイズを大きくしていくことで、無理なく書く力を育てていくのです。
この講座を通して、読者に伝わりやすく、そして何より自分自身がラクに書ける文章の「型」を学ぶことができます。
そして、この講座の最終課題は「技術同人誌の企画書を提出すること」。
これが、次のステップへ進むための大事な切符になります。
ステップ2:自分のメディアで発信を始める

技術ライティング講座でインプットするのと並行して、ぜひ始めていただきたいのが、noteやブログといったご自身のメディアを開設し、発信を続けることです。
学んだ「型」は、実際に使ってみて初めて身につきます。1,000文字、2,000文字といったサイズ感の文章を書くことに、まずは慣れることが大切です。
最初は大変かもしれません。でも、これを習慣にすることができれば、例えば1ヶ月続けるだけで数万文字を書く経験が積めることになります。これって、実は技術同人誌1冊分の文字量として十分に匹敵するんですよ。
いきなり大きな山を登ろうとすると挫折してしまいますが、毎日コツコツと丘を登る練習をしていれば、いつの間にか高い山にも登れる体力がついている。そんなイメージですね。
ステップ3:最高の予行演習「技術同人誌」を出版する
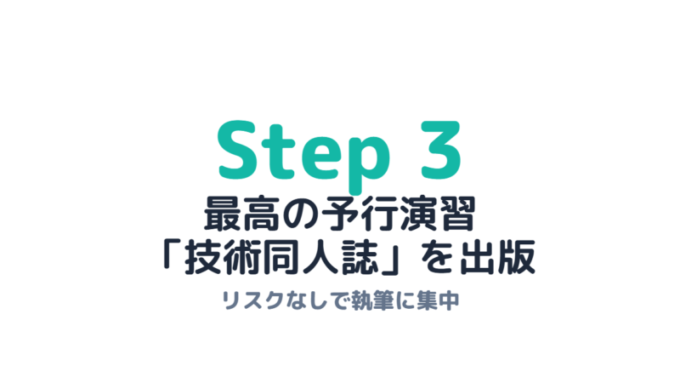
ブログやnoteでの発信に慣れてきたら、いよいよ「本」という形に挑戦します。それが「技術同人誌」。ページ数でいうと50~100ページほど、文字数でいうと数万文字ほどです。
「でも、同人誌出版ってすごくお金がかかるし、大変そう…」
そう思いますよね。本来、同人誌は個人が費用もリスクもすべて背負って制作するものです。
しかし、ノンプロ研には、この挑戦を強力にバックアップする仕組みがあります。
- 費用面のサポート:表紙デザイン費や印刷費など、制作にかかる費用は、ノンプロ研がすべて負担します。
- 企画・執筆のサポート:僕や、すでに出版経験のあるコミュニティの先輩たちが、企画の壁打ちから執筆の相談まで、手厚くサポートします。
- 販促・販売のサポート:「技術書典」のような大きなイベントでの販売も、ノンプロ研としての実績があり、たくさんの仲間たちが手伝ってくれます。
つまり、著者は金銭的なリスクを負うことなく、執筆に集中できる環境が整っているわけです。
これは、初めて本を作る人にとって、これ以上ないほど心強い仕組みだと自負しています。
ちなみに、制作費は本が売れた分から回収し、利益が出た場合は著者とノンプロ研で折半する形になっています。
ステップ4:「技術の泉」シリーズで商業デビュー!
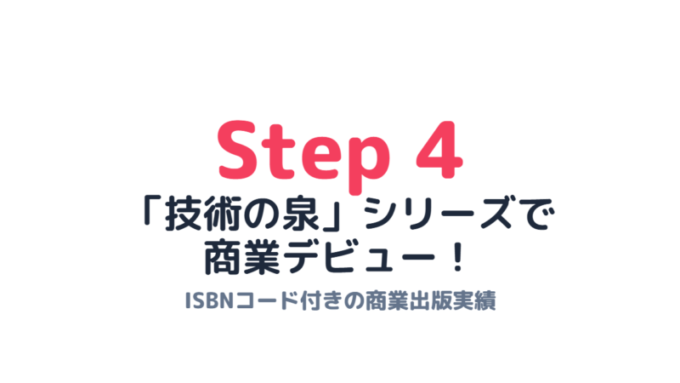
ノンプロ研のサポートのもとで完成させた技術同人誌。これを「技術書典」などのマーケットに出展すると、次の扉が開かれることがあります。
それが、インプレスグループの「技術の泉」シリーズというレーベルからの商業化のお話です。
このシリーズは、技術同人誌として発表された優れた作品を、商業書籍として出版し直すというユニークな取り組みをしています。
技術書典で発表された新刊のうち、内容がしっかりしているものには、結構な確率でお声がけをいただいています。
このお話をいただくと、作成した同人誌を「Re:VIEW」という形式で書き直し、表紙などは新たに作り直して出版することになります。
この形式は、電子書籍と、注文に応じて1冊ずつ印刷・製本されるプリント・オン・デマンド(POD)での販売がメインなので、残念ながら全国の書店に平積みされるわけではありません。
しかし、きちんと「ISBNコード」が付くので、紛れもない「商業出版」の実績になるのです。
この流れで、これまでノンプロ研から5名の方が著者としてデビューを果たしました。
かなり再現性の高いルートだと言えると思います。
まとめ:出版へのロードマップをもう一度
さて、僕やノンプロ研の仲間たちが歩んできた、商業出版へのロードマップをもう一度おさらいしましょう。
- ノンプロ研の技術ライティング講座で「書く型」を学ぶ
- noteやブログを開設し、発信を続ける
- ノンプロ研のサポートを受けながら「技術同人誌」を出版する
- 「技術の泉」シリーズで商業出版デビューを果たす
おそらく、ひとりでコツコツnoteをはじめるよりは、かなり可能性は高いはず…!
それでも、このステップの途中には、いくつかの「壁」が存在します。
例えば、「ブログの執筆が継続できない」「頑張って同人誌を作ったけれど、商業化の声がかからなかった」などです。
これに関しては以下の有料記事で、その対策と成功率を上げるコツをお伝えしています。

そして、このロードマップを達成した先には、実は「ステップ5」とも言える、さらなる展開が待っていたりもするので、それについても触れていますよ!
ご興味のある方は、ぜひこのロードマップのステップ1から踏み出してみてください。
まずは、技術ライティング講座の仮申込から…以下のリンク内のフォームからどうぞ。
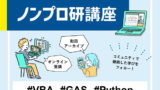
あなたの知識や経験が、誰かの役に立つ一冊の本になる日を、心から応援しています。
以上、「「すごい人」じゃなくても本は出せる!再現性の高い商業出版への4ステップ」についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!

