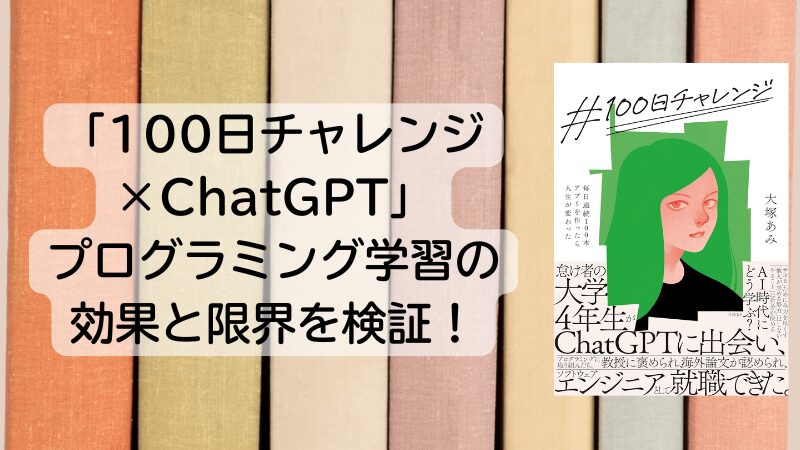
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
今日は書籍『#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』の考察編。
ChatGPTを活用したプログラミング学習の「100日チャレンジ」は、どれだけ効果があるのか…その再現性について、一緒に考えていきましょう。
ということで、今回は「「100日チャレンジ×ChatGPT」プログラミング学習の効果と限界を検証!」です。
では、行ってみましょう!
怠け者の大学生が見つけた、ChatGPTとプログラミングの可能性
簡単に本書のおさらいです。
主人公はちょっと怠け者の大学生、大塚あみさん。宿題をサボるために、ChatGPTを使いはじめたところ、プログラミングもできることを知りました。
そこで思いついたアイデアが、「100日チャレンジ」。毎日1本、ChatGPTを使いながらプログラミングし、新しいアプリを作り、X(旧ツイッター)に投稿する、それを100日続けるというもの。
その痛快なストーリー自体、魅力的なのですが、プログラミングを教えるという仕事をしている僕としては、別の観点でも超興味深いものでした。
それは、このチャレンジがどれだけ再現性があるのか?ということです。
プログラミング学習には、リソースが必要です。具体的には、時間とモチベーションです。
その観点で、考察していきます。
100日チャレンジ達成に必要な時間と、それを確保することの難しさ
まず、時間です。
大塚さん、しっかり記録をとってくださっていて、このチャレンジには124日間で1600時間、つまり毎日10時間以上もの時間が必要だったそうです。
これほどの時間をプログラミングに費やすというのは、学生ならまだしも、仕事を持つビジネスパーソンにはかなり難しい。
もう一点、大塚さんは、これとは別に、授業でプログラミングに触れていました。あまり真面目に取り組んでいなかったようですが、そこで学んだ「クラス」や「UML」などを思い出し、100日チャレンジで出てきた課題をクリアするために取り入れたりしていました。
多少は、プログラミングについて「耳慣れ」をしていた状態だったということです。
これらを踏まえると、全くの初心者であったとしても、ChatGPTをガンガン使えば、効率よく学習できて、さっさとアプリを開発できるようになるかというと、そういう話ではなさそうです。
実際、コミュニティ「ノンプロ研」にも、ChatGPTでプログラムを作っていたけれども、なんともならなくなって訪れるという方も少なくありません。
プログラミングの基礎知識の重要性:しっかりした土台を築く
もっと効率を上げるのであれば、「基礎」が重要になります。
基礎は、新しい知識を吸収するための土台となるものです。
しっかりとした土台があれば、新しい知識がスッと頭に入ってきて、「ああ、これはここにはめればいいんだな」と理解しやすくなります。
逆に、土台がガタガタだと、新しい知識が定着せず、何度も同じことを繰り返さなければならなくなります。これでは、学習のモチベーションも下がってしまいますよね。
モチベーションを維持する秘訣:宣言、他者評価、そして「好き」の力
モチベーションについても、いくつかのポイントがあります。
習慣化と「宣言効果」
まず、Xへの投稿は、習慣化の非常に有効な方法です。「宣言効果」と呼ばれるもので、人に公言することで、目標達成への意識が高まります。また、フォロワーからの応援も、モチベーションを維持する力になります。
ノンプロ研でも、「100本ノック」や「ブートキャンプ」というチャンネルがあり、毎日の行動に落とし込んで投稿し、メンバー同士で励まし合いながら、課題に取り組んでいます。
プログラミングに有利な特性
次に、大塚さんの性格です。かなり自己分析をしっかりされていて、「手を抜くことに全力を尽くすタイプ」「興味を追いかけているときには、頑張っているという意識がない」と分析されていました。
これらはいずれもプログラミング学習には、ものすごい向いている特性です。
やりたくないことを徹底的に自動化してやる、コンピューターを駆使してなくしてやる、そのような思いは強いモチベーションを生みます。
また、「100日チャレンジ」を思いつき、自分で「やる」と決めました。このチャレンジに「没頭できる」とひらめいたのでしょう。
チャレンジの価値を高める「周りのサポート」と「対外的な意義」
このチャレンジの価値をさらに高めたのは、周りの大人のサポートによって、チャレンジと対外的な意義が結びついたというポイントです。
具体的には、論文の執筆、学会発表、国内外での活動など、100日チャレンジの成果が、さまざまな形で社会に認められることにつながりました。
大塚さんは、100日チャレンジ自体に対外的な意義はそこまで感じていませんでした。
書籍の中で先生はこのように語っています。
「私がサポートできるのは、何かをやり始めた人に対してだけだ。何も考えない人には適切な手助けができない」
まとめ
以上、「「100日チャレンジ×ChatGPT」プログラミング学習の効果と限界を検証!」についてお伝えしました。
100日チャレンジは、ChatGPTとプログラミングの可能性を示す、素晴らしい事例です。しかし、その再現性には、時間、基礎知識、モチベーション、そして周りのサポートなど、さまざまな要素が関わってきます。ぜひ、ご参考ください。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!


