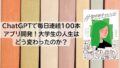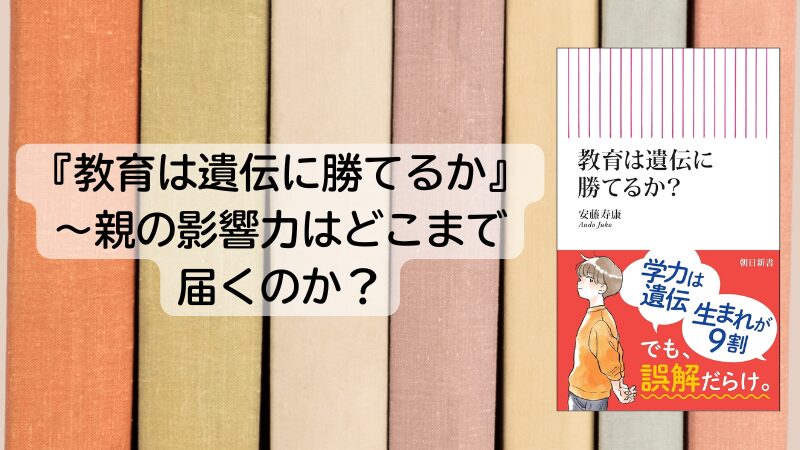
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
子どもの将来は遺伝で決まるのか、それとも親の教育で決まるのか?
この問いに対して、行動遺伝学の視点からその答えを探る書籍『教育は遺伝に勝てるか』。
今日はこちらの書籍から遺伝と教育について考えます。
ということで、今回は「『教育は遺伝に勝てるか』~親の影響力はどこまで届くのか?」です。
では、行ってみましょう!
教育と遺伝の関係性:親の影響力はどこまで?
子どもがどう育つか、遺伝によってだいぶ決まっているようにも思えるし、親の関わり方が全部決めるようにも思える。
「親の収入が子どもの学力に影響する」などという話もあります。
僕たちは、教育と遺伝の関係性について、なんとなくのイメージや思い込みで語ってしまいがちです。
本書『教育は遺伝に勝てるか』は、最新の研究成果をもとに、教育と遺伝に関する様々な誤解を解き明かし、教育の可能性について考察しています。
著者の安藤寿康先生は、慶應義塾大学の名誉教授であり、教育学博士です。行動遺伝学、教育心理学、進化教育学を専門とされており、数多くの研究成果を発表されています。
本書は2023年7月13日に朝日新書から発売されました。全256ページです。
『運は遺伝する』の構成から見る、教育と遺伝の複雑な関係
本書の構成をみていきましょう。
はじめに
はじめにでは、まず、遺伝でも親でもすべてが決まるわけではないと伝えます。子育ての見方や姿勢を、遺伝という現象を通して、これまでと違った見方で捉えることが本書の目的です。
第1章:遺伝は遺伝せず――基本はメンデルにあり
第1章では、「遺伝は遺伝せず――基本はメンデルにあり」と題して、遺伝のメカニズムについて解説されています。
「メンデルの法則」覚えていますか?
「えんどう豆」のつるあり、つるなしとか、学校ではたいして面白みを感じていませんでしたが、こうしてヒトの遺伝に当てはめると、また見え方もかわってきます。
第2章:あらゆる能力は遺伝的である
第2章は、「あらゆる能力は遺伝的である」という、少しドキッとするようなタイトル。
ここでは、行動遺伝学の研究について詳しく紹介されています。
その中心は、一卵性双生児と二卵性双生児を比較することで、遺伝、共有環境(主に家庭環境)、非共有環境(双子がそれぞれ異なる環境)の影響を、知能、学力、性格、行動特性など、あらゆる項目に対して調べるというもの。
第3章:親にできることは何か――家庭環境の効き方
第3章では、「親にできることは何か――家庭環境の効き方」というテーマで、共有環境の影響について考察されています。安藤先生は、教育の科学的定義として「独力で学ぶこともできない知識やスキルを他者が学ぶのを、わざわざ手助けしてあげること」と述べています。教えるという行為は、人間だけが行う特別なもの。しかし、親の影響力は、遺伝の力にどこまで立ち向かえるのでしょうか。
第4章:教育環境を選ぶ――学校の内と外
第4章は、「教育環境を選ぶ――学校の内と外」と題して、二卵性双生児の4つの事例をもとに、学校生活や非共有環境がどのように影響するかを考察しています。
それぞれの双子がどのように成長し、どのような人生を歩むのかを追跡した内容。非常に興味深いものでした。
第5章:「自由な社会」は本当に自由か?
第5章では、「「自由な社会」は本当に自由か?」。
なぜ急に「自由」というワードが出てきたかというと、「自由度」は遺伝の影響度に関連しているようなのです。
たとえば、都会と田舎でいうと、田舎の方がアクセスや慣習などさまざまな要因で制約が多く、自由度が抑えられます。遺伝でいうと、遺伝由来の能力が発揮されにくいということがわかっているそうです。
それでは、自由は僕らにとって果たして望ましいものなのでしょうか?
第6章:そもそも、子どもにとって親とは?
第6章は、「そもそも、子どもにとって親とは?」という根源的な問いから、親の視点でこれまでの内容をまとめたパートです。
親として、子どもにどのように向き合えばよいのか、改めて考える機会となりました。
親に、教育者にできることは何か
この本を読んで、特に印象に残ったことをお伝えします。
「遺伝だから」と考えると親は無力に感じ、「親次第だから」と考えると親は過剰な責任を感じてしまいます。どちらの考え方も、親を苦しめる可能性があります。
しかし、本書が語るのは遺伝の影響は確実にあり、でもそれだけでもないということです。また、「親にできることはあるが、それは思っているよりもわずかである」ということです。
子どもが生来さずかったもの、それがどう美しく花開くのか、そこにおいて、自分にできるわずかなことは何なのか謙虚に向き合うことなのだと思いました。
また、非共有環境の影響も見逃せません。
子どもでいうと学校、大人でいうと職場が中心ですが、人の個性は千差万別。ひとつの枠組みで全員が能力を覚醒させ、発揮できるわけではありません。
向いているのかを見極めて、そうでないなら、別の環境を用意し、そこへ促すことが重要。行動遺伝学の視点からも、それがいえるということだと思います。
この本は、子育てに悩む親御さんだけでなく、教育に関わるすべての人にとって、大きな示唆を与えてくれる一冊だと思います。
神秘ではありますが、その理の一部を知るだけでも、少し肩の荷を下ろせることもあるのではないでしょうか。
まとめ
以上、「『教育は遺伝に勝てるか』~親の影響力はどこまで届くのか?」についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!