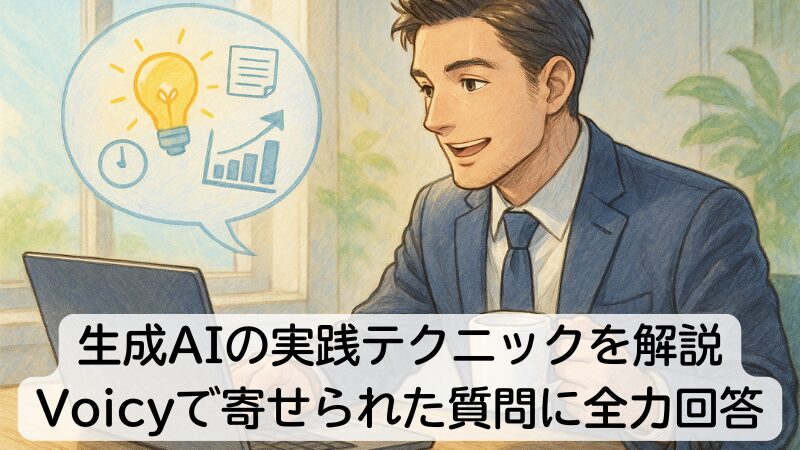
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
昨日に続き、生成AI関連コメント返しスペシャル第2弾です。
ノンプロ研の「生成AI講座」第2期の事前課題が、Voicy「スキルアップラジオ」のAIに関する放送を聞いてコメントをするというもの。
今回はそのコメント返しの2回目となります。
時間の棚卸し術から、メタプロンプティング、バイブコーディングまで、皆さんのAI活用術をさらに広げるヒントが満載です。
皆さんのリアルな活用法や疑問に触れることで、僕自身もたくさんの気づきをもらっています。それでは、早速見ていきましょう!
ということで、今回は「生成AIの実践テクニックを解説|Voicyで寄せられた質問に全力回答」です。
では、行ってみましょう!
#1051 生成AIによる新・時間の棚卸し実践法
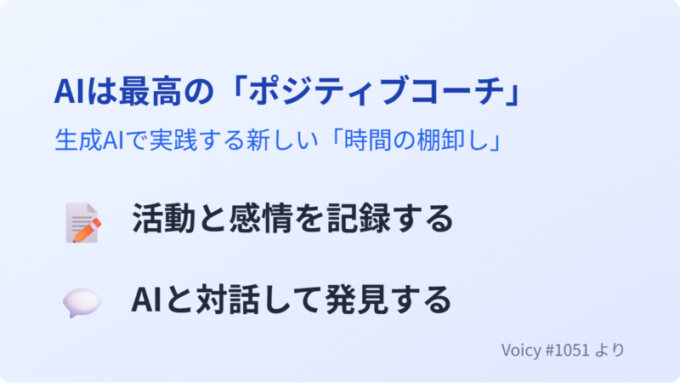
おおさきさん
生成AIをポジティブなコーチとして活用する、そのためには活動の記録を詳細に記録しておくことが重要です。一言感情とメモを合わせて残すと客観的に見てくれる。共感しながら聴きました。
おおさきさん、ありがとうございます!
そうなんです。僕がおすすめしている「時間の棚卸し」という習慣は、今日一日、自分が何時から何時まで何をして、その時間は自分にとって価値があったのかを客観的に判断する、というものです。
これまでは自分一人で振り返ることが主でしたが、ここにAIというパートナーが加わることで、自分だけでは得られない新しい気づきや、より客観的な視点を得られるようになります。まるでポジティブなコーチが隣にいてくれるような感覚ですよね。
ぜひ、この新しい時間の棚卸しを、皆さんの「働く」を見直すきっかけにしていただけたら嬉しいです。
YamaMasaさん
生成AIの利用はほぼ調べ物か質問でした。この時間の棚卸しは、自身の記録を生成AIでも活用する事も学べると思いましたので、やってみようとおもいます。
YamaMasaさん、ありがとうございます!
生成AIを調べ物や質問に使う、というのは素晴らしい第一歩だと思います。でも、実はAIにできることはそれだけじゃないんですよね。
特に「壁打ち」や「相談」といった対話ができるようになると、AI活用の幅は一気に広がります。今回の時間の棚卸しのように、自分の記録をインプットして対話することで、AIは最高の相談相手になってくれます。ぜひ試してみてください!
#1056 生成AIへのプロンプトは覚えなくていい。メタプロンプティングの勧め
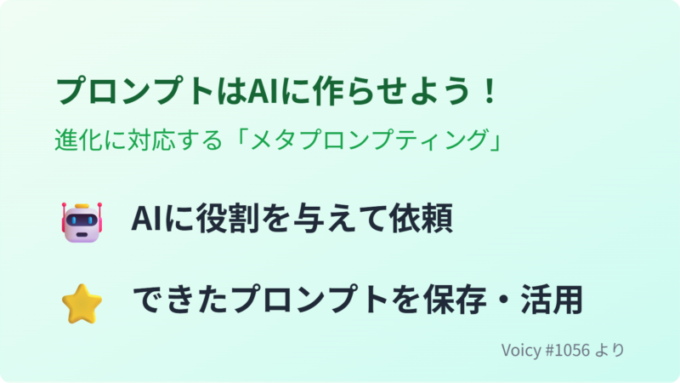
おおさきさん
プロンプトをAIに作ってもらうテクニック。AIの進化にも対応できるので非常に効果的とのこと。作ってもらったプロンプトはスニペットなどにまとめると良い。「あなたはプロンプト生成職人です」
おおさきさん、いつもありがとうございます!
そうなんです、メタプロンプティングは本当に強力なテクニックですよね。AIにプロンプトそのものを作ってもらうことで、AIの進化にも柔軟に対応できます。
さらに一歩進んだ使い方として、メタプロンプティングを重ねて作り込んだ最高のプロンプトを、ChatGPTの「GPTs」やGeminiの「Gems」のようなカスタムAI機能にセットしておくことをお勧めします。こうすることで、自分だけの優秀なAIアシスタントをいつでも呼び出せるようになり、とても便利ですよ。ぜひ、試してみてくださいね。
ichihukuさん
AI関連Voicy視聴中。メタ・プロンプティングの話し。以前聞いたはずなのにすぐ使ってないから忘れてる。入力が苦じゃないのですぐ打っちゃうけど、便利機能はどんどん使って行かないと
ichihukuさん、ありがとうございます!
わかります、便利な機能って、いざという時に忘れてしまいがちですよね(笑)。ついつい、いつものやり方で入力しちゃいますよね。
メタプロンプティングを習慣にするコツとしては、毎日行うような定型作業で、かつ、ある程度の精度が求められる指示が必要なものから試してみることです。
そういった作業で一度、少し凝ったプロンプトをメタプロンプティングで作っておくと、「こんなに楽になるんだ!」と実感できて、他の作業でも使ってみようという気持ちになるはずです。
#1058 ChatGPTの新画像生成AIの落とし穴。挫折と再挑戦のリアル体験記
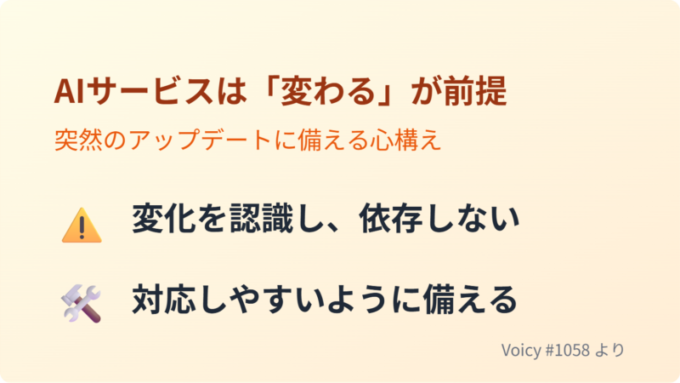
おおさきさん
改変は突然やってくる…。試行錯誤の過程が生々しくて参考になります。「どのように指示出ししたら良い?」とプロンプト作成方法をGPTに聞いて壁打ち。GPTsよりプロジェクト機能の方が安定した。
おおさきさん、生々しいレポートがお役に立てたようでよかったです!
おっしゃる通り、ChatGPTのPlusプラン以上で使える「プロジェクト」機能は、とても便利ですよね。関連するチャット履歴を一つの場所にまとめておけるだけでなく、プロジェクトごとにあらかじめ指示(カスタムインストラクション)をセットしておくことができます。
これにより、簡易的なGPTsのような使い方が可能です。もしGPTsの挙動が不安定な時などには、このプロジェクト機能でデフォルトの指示を与えておくと、安定した結果が得られることがありますので、使い分けてみてください。
ichihukuさん
4月30日の放送だけどすでに懐かしい感じがします。ただ、自分としてはあまりに最新情報ばかりだと身に沁みないので、これぐらいのタイミングで聞き直すと、あーそうだった、と腑に落ちます。
ichihukuさん、ありがとうございます!
本当にそうですよね、AIの世界は情報の更新が速すぎて、少し前の放送でも懐かしく感じますよね。最近はChatGPTも少し落ち着いてきた感はありますが、それでも進化のスピードは凄まじいです。
最新情報を追いかけるのは大変ですが、あまり焦らず、ご自身のペースで「あ、そうだった」と腑に落ちるタイミングで情報をキャッチしていくのが一番だと思います。僕も頑張って情報をキャッチアップし、皆さんに分かりやすくお伝えできるよう努めます!
かにみそさん
あくまでサービスを利用しているのでサービスのクオリティやアップデートに翻弄されるということを改めて認識させられた回でした。進化も早く、仕事でのAI依存度も高く、変わったときの影響は大きいなぁと思いました。大きな局面で見れば享受している恩恵の方が何万倍もあるはずなので、変わることは前提で変わることに対応しやすいよう常に考えて利用していることが大事だなと思いました(/・ω・)/
かにみそさん、これは本当に、本当に重要なポイントをありがとうございます!
テクノロジーを利用する上で、この「サービスの継続性や安定性はどうなのか?」という視点は避けて通れない問題です。そして、かにみそさんがおっしゃるように、「変わることは前提」として捉え、その変化にどう対応していくかを常に念頭に置いておくことが、賢いテクノロジーとの付き合い方だと思います。
僕たちがいま享受している恩恵は計り知れません。だからこそ、変化を恐れるのではなく、変化に対応できる準備をしておくことが大切ですね。心に刻んでおきたいコメント、ありがとうございます。
#1068 話題のバイブコーディングとは?非エンジニア向けにやさしく解説
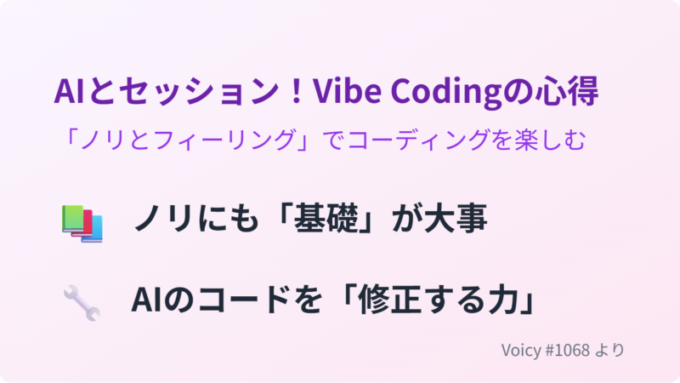
おおさきさん
OpenAI共同創業者の一人アンドレイ・カーパシー氏が提唱したコーディングスタイル。ノリとフィーリング。セキュリティを意識しないツールやWebページ制作などに活用していきたい手法です。
おおさきさん、ありがとうございます!
バイブコーディング、面白いコンセプトですよね。ただ、ノンプログラマーの方が「ノリとフィーリングでガンガン作れる!」と思ってしまうと、少し注意が必要です。プログラミングの知識がないことで生じるリスクは、思った以上に大きい場合があります。
ですので、ぜひプログラミングの基礎はしっかりと身につけていただくことをお勧めします。基礎知識という土台があってこそ、バイブコーディングのような手法が活きてきて、まさに「無双状態」になれるはずです。
ichihukuさん
今までコードのわからないところだけAIに聞いてましたが、バイブコーディングでまるっと聞いちゃっても書けるってことですね。やってみましたが、よりコードの修正力が必要になりそうな気がします。プログラミング勉強しといてよかった。
ichihukuさん、その通りだと思います!
AIにまるっと作ってもらったコードが、よく分からないけど動いたからOK、というのはちょっと怖いですよね(笑)。ichihukuさんのようにプログラミングの素養があるからこそ、「コードの修正力が必要」だと感じられるのだと思います。
AIが生成したコードを叩き台にして、そこから自分の手で修正や改善を加えていく、といった使い方が現実的かもしれませんね。勉強しておいてよかった、という言葉が全てを物語っていますね!
かにみそさん
この放送で「バイブコーディング」という言葉を始めて知りました。AIを使ったコーディング、めっちゃ楽しいですね(/・ω・)/ GASとPythonだと、圧倒的にGASの方がうまくいくので、基礎の学びや経験値はしっかり大事なんだなと実感しています。
かにみそさん、ありがとうございます!
「めっちゃ楽しい」と感じられるのが一番ですよね!そして、GASの方がうまくいく、というご経験、非常に興味深いです。やはり、ご自身が得意で、基礎知識や経験値がある分野の方が、AIとの連携もうまくいくということですよね。
お話を聞いていて、僕は昔やっていたジャズのジャムセッションを思い出しました。僕はサックスが得意なので、AIとサックスでセッションするのは楽しいでしょうけど、いきなりピアノでやれと言われても上手くいかないはずです(笑)。
Vibe(ノリ)で楽しむためにも、やっぱり基礎は大事なんだなと、改めて感じさせられました。
まとめ
ということで、今回もたくさんのコメント、本当にありがとうございました!
まだまだご紹介しきれていないコメントがたくさんありますので、また近いうちに第3弾をお届けできればと思っています。
以上、「生成AIの実践テクニックを解説|Voicyで寄せられた質問に全力回答」についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!

