
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
Voicyに寄せられた皆さまからのコメントに、タカハシノリアキが誠心誠意お答えします!
今回は第3弾!
生成AI時代の発信の価値や、最新AIニュースについて一緒に考えていきましょう。
ということで、今回は「生成AI時代に“伝わる発信”をするには?|Voicyコメント返し」です。
では、行ってみましょう!
#1073 データ活用で人生も仕事も激変。AI時代突入で発信の価値が爆上がり
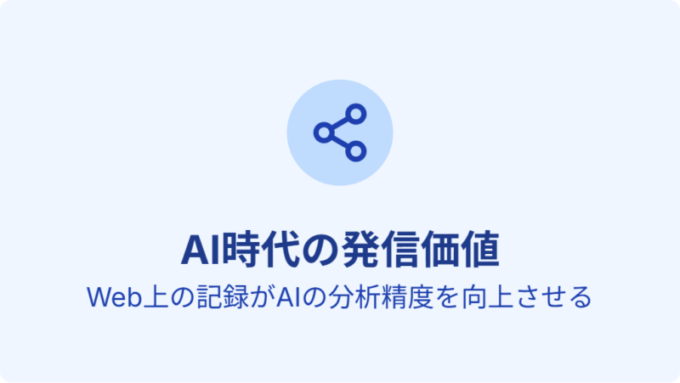
おおさきさん
生成AIによって発信の価値が向上している、という内容が印象深いです。発信は「記録」の意味があるが、Web上に自分の記録があることで生成AIが情報を集めやすく、現状分析や次の発信活動に役立つ。
おおさきさん、ありがとうございます。
おっしゃる通り、発信は「記録」としての意味合いが強いですが、その記録がWeb上にあることで、生成AIが情報を収集しやすくなります。特に、「Deep Research」のような機能を使うと、その効果がよくわかりますよね。
この機能は、インターネット上の情報を広範囲に集めてレポートを作成してくれるのですが、自分や自社に関する情報をたくさん発信している場合とそうでない場合とでは、出来上がるレポートの精度に大きな差が生まれます。
AI時代において、発信しておくことの価値がますます高まっていることをお伝えした放送でした。
ichihukuさん
「AI時代突入で発信の価値が爆上がり」私の書き散らしたブログはどうなっているんだろう。なかなか見返すこともしていないなあ
ichihukuさん、コメントありがとうございます。
ご自身のブログが今どうなっているのか、気になりますよね。もしよろしければ、ぜひ一度ご自身のブログについて「Deep Research」を試してみてはいかがでしょうか。
新たな発見があるかもしれません。今度、ぜひ一緒にやってみましょう!
かにみそさん
何年もコツコツとブログを積み上げてきているタカハシさん最強ですね(/・ω・)/この放送を聞いて、かにも発信再開しようかな…と思ったのを事前課題のおかげで思い出しましたw
かにみそさん、ありがとうございます!
僕の場合は個人で事業をしているので、必要に迫られて発信を続けてきた、という側面もあります。
会社員の方だと、会社の情報を発信することにためらいを感じることもあるかもしれませんね。そういった意味では、企業自身がオウンドメディアなどを活用して、しっかりと情報発信していくことが重要になってくるのかなと思います。
かにみそさんの発信再開、応援しています!
YamaMasaさん
AIの利用は、他人のアウトプットを活用するというイメージがありましたが、自身のアウトプットも活用できるんだなと気づけました
YamaMasaさん、素晴らしい気づきですね!
AIは、世の中全体の情報を活用することはもちろん得意ですが、特定の範囲、例えば「自分自身のこれまでのアウトプット」だけを対象に情報を活用することも可能です。
ぜひ、ご自身のアウトプットを活用する方法も試してみてください。
#1080 非エンジニアでも分かるGoogle I/O 2025の注目AIニュース総まとめ

ichihukuさん
情報量が多くて、聞けば聞くほど混乱してきました(笑) Geminiも使い始めましたので、身近なところから試していきたいと思います。
ichihukuさん、コメントありがとうございます。
そうですよね、本当に情報量が多いですよね。僕の伝え方にも改善の余地があったかもしれませんが、Google I/Oは毎回新しい情報が満載で…。次回は2回に分けるなど、もう少し工夫してみますね。
今回の発表における大きな潮流は、以下の3つです。
- AIエージェント: 自律的にタスクを手伝ってくれるAI
- ユニバーサルAIアシスタント: カメラで映したものについて対話できるAI
- パーソナルコンテキスト: 個人の情報(メールやカレンダーなど)を踏まえて対話できるAI
まずは「世の中のAIはこんな方向に進んでいるんだな」という大きな流れを掴んでいただければ大丈夫です。
身近なところからGeminiを試していくという姿勢、素晴らしいと思います!
かにみそさん
毎年 Google I/O 楽しみで、リアルタイムで視聴したいから早起き(3:00)してます。個人でメモしてXで呟いて会社で共有して….と、かに個人が楽しむだけで満足している中、こうやってちゃんとまとめて世間に発信しているタカハシさんの姿を見て反省するなどしました(V)o¥o(V)
かにみそさん、朝3時起きはすごいですね!
かにみそさんのXでの投稿、いつも拝見していますよ。個人で楽しむだけでなく、会社でも共有されていて、周りの方々もきっと助かっていることでしょう。
せっかくXでつぶやいているのですから、その投稿をAIにまとめてもらって、一つの記事にする、なんてことも可能かもしれませんね。
#1085 AIとのおしゃべり14回目「主催なのに人気がないのだけど」
おおさきさん
ChatGPTのボイスモードMapleとのおしゃべりの様子が面白いですw AIのスタンスとして、相談するとまず受け止めてくれるものの、その後に長文のアドバイスが返ってくる印象。これが個人的には苦手だったりします。
おおさきさん、コメントありがとうございます!
なるほど、その感覚よく分かります。AIはまず受け止めてくれる優しさがありますが、その後のアドバイスが長文になりがちですよね。実はこれ、テキストベースのやり取りでも、AIのモデルが新しくなるにつれて回答が長くなる傾向があるんです。
「前のモデルの方が簡潔で良かったな」と感じることもありますよね。もしかしたら、最初に「短めに答えてね」とお願いしておくのが良いのかもしれません。
#1086 まずやることは目標設定。ブートキャンプ式の生成AI講座の成果はいかに
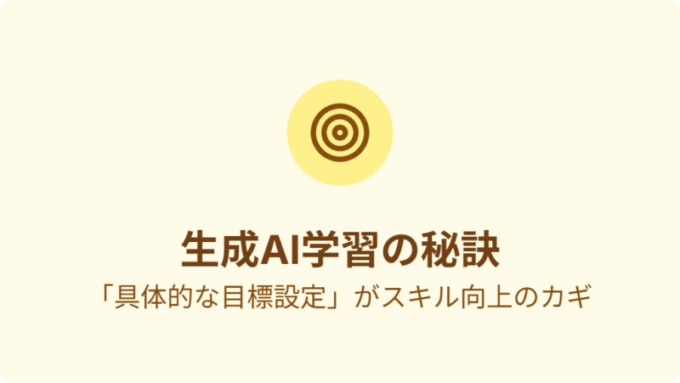
おおさきさん
生成AIを学ぶ際には、なんとなくではなく確固たる「やりたいこと」「目標」がないと使えるようにならない。まず何をやりたいか?
おおさきさん、的確なコメントありがとうございます。
まさにその通りで、僕自身、生成AIの活用スキルが飛躍的に向上したのは、「この一連の発信活動にAIを徹底的に活用しよう」と決意してからでした。
当時は毎日2時間半もかかっていた発信作業の時間を短縮しつつ、クオリティは絶対に落とさない、むしろ向上させる。そんな具体的な目標があったからこそ、AIの回答の細かいクオリティの差にもこだわるようになりました。
何か具体的な目標を題材にして、AIと共に試行錯誤していくのが、上達への近道なのかもしれませんね。
#1120 私のおすすめプレミアム放送その1|ガチAI活用事例編
ichihukuさん
Google NotebookLMは話に聞くたびに「おっ!」となるけどなかなか使い始められない。AI講座を使うきっかけにしたい
ichihukuさん、ありがとうございます。
ぜひ、この機会にNotebookLMを活用してみてください!
例えば、少し難解で長いPDF資料(国が発表しているレポートや、複雑な手続きの書類など)を読むときに非常に便利です。
資料をアップロードすれば、AIが要約してくれたり、音声で概要を説明するポッドキャストを生成してくれたり、チャット形式で内容について質問したりできます。
ぜひ一度試してみてください。
#1126 新たに見つかった生成AIの弱点「ポチョムキン理解」とは
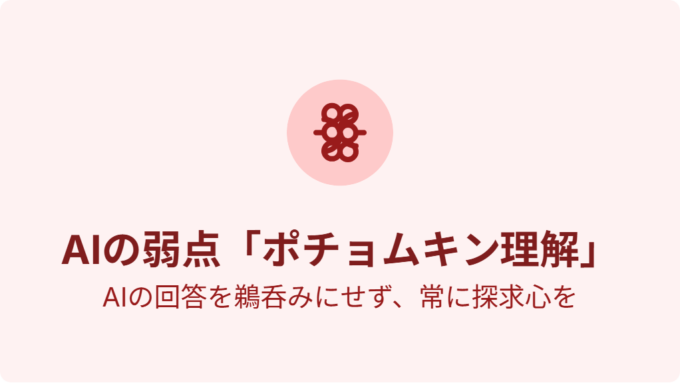
ichihukuさん
「ポチョムキン理解」って初めて聞いたけど、AIはちょっとわかったふりしちゃうってことかな。AIの使い方より向き合い方がより重要になってきますね。AIの回答を疑える知識は必要かも
ichihukuさん、いつもありがとうございます!
「ポチョムキン理解」、面白いネーミングですよね。この現象自体はおそらく以前からあったものですが、研究成果として発表され、名前が付けられたということなのだと思います。
ichihukuさんがおっしゃる通り、AIは時々「わかったふり」をしてしまうことがあります。だからこそ、私たちはAIの回答を鵜呑みにせず、「本当にそうかな?」と一度立ち止まって考える姿勢が非常に大切です。
AIと上手に付き合っていくためには、私たち人間側も学び続ける姿勢が求められますね。
まとめ
全3回にわたってお送りしたコメント返しスペシャル、いかがでしたでしょうか。
合計で29件もの温かいコメントをいただき、本当にありがとうございました。
これからも、生成AIに関する役立つ情報をお届けしていきますので、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいです。
以上、「生成AI時代に“伝わる発信”をするには?|Voicyコメント返し」についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!

