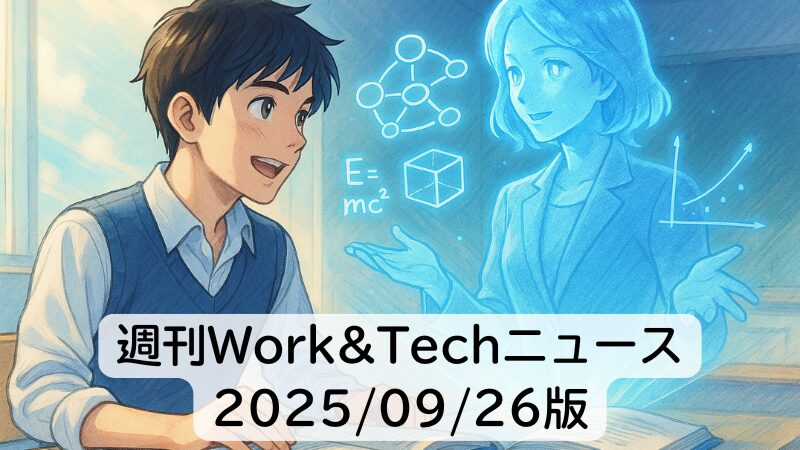
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
「週刊Work&Techニュース」 2025/09/26版をお送りします!
今週のワークとテックの主なニュースをざっとチェックし時流をつかんでいただくことができますよ。
では、行ってみましょう!
生成AIを活用した学習支援ツール「Learn Your Way」を試験提供 Googleが教科書との新たな関わり方を提案

Googleは、生成AIを活用した学習支援ツール「Learn Your Way」の試験提供を開始しました。
このツールは、同社の教育向けAIモデル「LearnLM」を基盤に、教科書や授業内容に基づいた個別最適化された学習サポートを実現します。
生徒は自身の理解度や進度に応じて学習内容を調整でき、学習目標の達成をアシストする仕組みとなっています。
Googleは今後、教育現場での運用効果を検証しながら、さらなる機能拡充を目指す方針です。

Googleが発表したAI学習支援ツール「Learn Your Way」、その基盤となっているのが、教育支援に特化したAIモデル「LearnLM」です。
このAIは学習科学の原則にもとづいて設計されており、学習者一人ひとりに最適な学びを提供することを目指しています。
例えば、教科書の内容からマインドマップや対話型のクイズ、音声レッスンといった多様な学習形式を自動で生成してくれます。
さらに、生徒の理解度や関心に合わせて学習のペースや内容を調整し、進捗の振り返りや適切なフィードバックまで行ってくれるという、「個別最適化」をとことん追求した仕組みです。
具体例を挙げると、学習テーマが「ニュートンの運動法則」で、学ぶ人がバスケットボールに興味のある高校2年生だった場合、バスケットボールを比喩に使いながら法則を説明するような教材をAIが自動で作り出してくれます。
実際に、このLearn Your Wayを使った学生は、従来のデジタル教科書で学んだ学生よりも、テストの成績が平均で11ポイントも高かったという報告もあり、その学習効果の高さがうかがえます。
このようなツールが登場することで、学校教育のあり方そのものが、これから大きく変わっていくのかもしれませんね。
米NVIDIA、OpenAIに最大1000億ドル投資へ

米半導体大手NVIDIAが、対話型AI技術で知られるOpenAIに対し、最大で1000億ドル(約15兆円)規模の投資を行う計画が明らかになりました。
この巨額投資は、AI開発の加速や次世代半導体市場の拡大を目指す動きの一環です。
NVIDIAはすでにAI分野で世界をリードする企業のひとつですが、OpenAIへの追加支援によって、その技術力と資金力を活かして一層の成長を目指します。
OpenAI側も、資金調達の規模・スピードにより、AI技術の深化と応用領域の拡大が期待されています。
NVIDIAがOpenAIに1000億ドルを投資するというニュースです。
最近は大きな金額のニュースに慣れてしまいがちですが、1000億ドル、つまり約15兆円という投資額は、日本の年間国家予算にも匹敵するほどの、まさに異例の大型案件です。
NVIDIAは、画像処理用の半導体「GPU」で世界トップクラスのシェアを持つ企業です。
このGPUは、生成AIモデルの開発や運用に不可欠なため、世界中のAI企業がこぞってNVIDIAのチップを買い求めています。この需要を背景に、NVIDIAは今年7月、ついに時価総額で世界首位に躍り出ました。
今回の巨額投資には、興味深い側面があります。NVIDIAがOpenAIに出資することで、その資金はOpenAIがNVIDIAのチップを購入するために使われる可能性が高いのです。それがまたNVIDIAの売上と株価を押し上げるという、一種の循環が生まれています。
しかし、こうした動きが続くと、AI市場が一部の巨大企業に支配される「寡占状態」がますます進むのではないか、という懸念も生まれています。アメリカの独占禁止法(反トラスト法)が、この状況に対応するのか、今後の動向が注目されます。
管理職の95%「なって良かった」 なぜ? 531人を調査
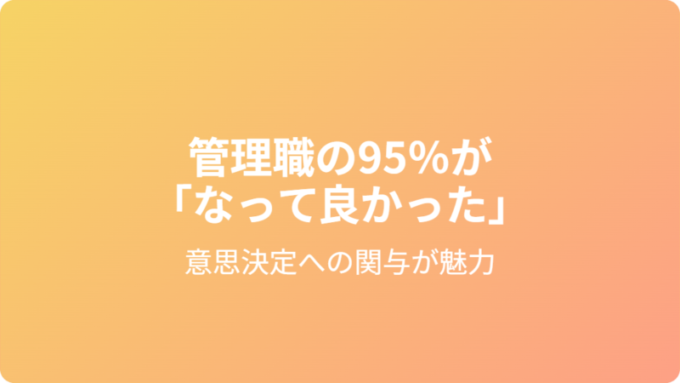
人材育成事業を手掛けるALL DIFFERENTが全国の管理職531人に実施した調査によると、実に95%が「管理職になって良かった」と回答しました。
理由で最も多かったのは「意思決定に関与できるようになった」(51.5%)で、「仕事の裁量が増えた」(48.2%)や「収入が増えた」(46.8%)が続きました。
また「部下の成長や成功を喜べるようになった」(42.0%)や「経営視点が養われた」(41.2%)といった声も目立ち、多くの管理職がやりがいを感じていることが分かります。

ここ最近、「罰ゲーム化する管理職」といった言葉をよく耳にするようになりました。メディアなどでは、管理職にはなり手がいない、という論調が目立っていたように思います。
しかし、今回の調査は、それとは少し異なる視点を提供してくれています。調査結果を見ると、「意思決定への関与」や「仕事の裁量」、「収入の増加」といった点が、管理職の満足度に大きく貢献していることがわかります。これらは確かに、やりがいや満足感につながりやすい要素ですよね。
もちろん、職場環境によっては管理職になりたくないと考える人もいるでしょう。
ですが、この調査では大多数の管理職が「なって良かった」と感じているという結果が出ており、メディアで語られるほど管理職は「罰ゲーム」ではないのかもしれません。
皆さんの職場では、実際のところいかがでしょうか。
アリババがAIを中核事業に、NVIDIAと提携も 株価急伸

中国の大手電子商取引企業アリババは、AIを電子商取引と並ぶ中核事業として位置付け、NVIDIAとの提携や世界的なデータセンターの拡充を発表しました。
アリババは新たなAI言語モデル「Qwen3-Max」も公開し、AI分野での競争力強化をアピールしています。
また、ブラジルやフランス、オランダなど世界各地で新しいデータセンターを開設し、今後さらに拡大する方針です。この発表を受けて、アリババの香港株は一時10%近く上昇し、約4年ぶりの高値を記録しました。
ECサイトの「アリババドットコム」や決済サービスの「Alipay」などで知られるアリババが、AIを事業の中核に据えると発表しました。世界的なAI需要の高まりを受けた動きです。
今回あわせて発表された新しいAIモデル「Qwen3-Max」は、1兆個を超えるパラメータを持つとてつもなく大規模なもので、特にプログラムコードの生成や、自律的にタスクをこなすエージェントの分野で高い性能を持つと説明されています。
AI開発というとアメリカの企業が目立ちがちですが、この発表からは、中国企業も世界のAI競争で主導的な立場を目指していることが伝わってきます。
以前、低コストながら優秀ということで話題になった中国製AI「Deep Seek」もありましたし、中国のAIの動向にも、引き続き注目していきたいですね。
EU、子どものSNS制限検討へ 欧州委員長が意向表明
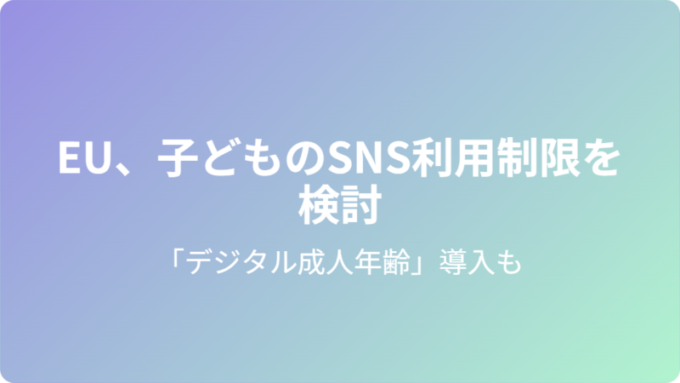
欧州連合(EU)のフォンデアライエン欧州委員長は、EU全体で子どもへのSNS利用制限を検討する方針を明らかにしました。
これは、16歳未満の利用を禁止したオーストラリアの法律を参考にする意向によるものです。
委員長は「デジタル成人年齢」を設ける必要性についても述べており、現在多くの加盟国がこの問題に注目しています。
EUでは、今後新たなSNS規制案を議論し、2026年後半には具体的な法案を提出する計画です。

EUが子どもたちのSNS利用を制限する方向で検討を始めました。これは、SNSが若年層の心身に与える影響への懸念が高まっていることが背景にあります。
懸念されている点は、大きく3つあります。
1つ目は、ネットいじめや誹謗中傷による深刻なメンタルヘルスの悪化。
2つ目は、プッシュ通知や動画の自動再生といった「中毒性」の高い設計によってSNSに長時間触れてしまい、依存症状に陥ること。これは学業への支障だけでなく、うつ病などを引き起こす可能性も指摘されています。
そして3つ目は、SNSを通じた性的搾取や犯罪に巻き込まれるリスクです。
こうした問題を受け、オーストラリアでは2025年12月から16歳未満のSNS利用が法律で禁止されることになっており、EUもこれを参考にしようと考えているわけです。
一方で、こうした規制の効果や必要性については、まだ十分な科学的根拠が揃っているとは言えず、議論が続いています。今後、EUがどのような判断を下すのか、その動きに注目していきたいですね。
まとめ
以上、「週刊Work&Techニュース」2025/09/26版についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!

