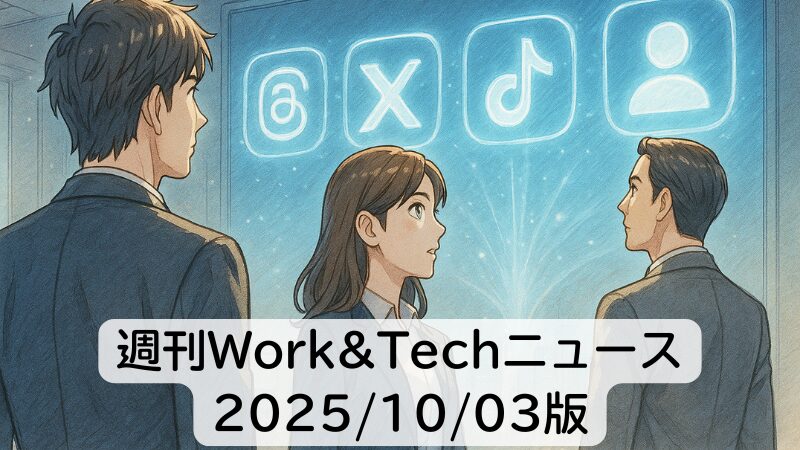
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
「週刊Work&Techニュース」 2025/10/03版をお送りします!
今週のワークとテックの主なニュースをざっとチェックし時流をつかんでいただくことができますよ。
では、行ってみましょう!
Threadsのユーザー数がついにXを上回る、公開から2年で初めて

メタが提供するテキストSNS「Threads」が、モバイル端末における世界の日間アクティブユーザー数で「X」を初めて上回りました。
Similarwebの調査によると、9月15日から21日の週平均でThreadsが1億3020万人、Xが1億3010万人でした。9月20日時点でもThreadsが1億2870万人、Xが1億2710万人となっています。
iOSユーザー限定でもThreadsが、Xを上回るなど勢いを見せていますが、アメリカでは依然
としてXが強く、ウェブサイトの訪問数や滞在時間ではXが上回っています。
メタはThreadsの成長を背景に、今後広告収入の拡大も見込んでいます。

ThreadsのDAU(デイリーアクティブユーザー数)が、ついにXのそれを超えたというニュースですね。ここでいう「アクティブ」がどの程度の活動を指すのかという点はありますが、メタ社としては当面の目標を見事に達成したというところでしょうか。
最近のXは少し落ち着いた印象もありますが、イーロン・マスク氏がTwitterを買収して以来、重要な機能の変更や、マスク氏自身の政治への関わり方などによって、ユーザーや広告主から不評を買うことが時々ありました。
また、以前からある炎上やユーザー間の対立といったイメージも、根強く残っているように感じます。
一方でThreadsは、今も成長を続けるInstagramからの強固な流入経路を持っています。
多くのユーザーはInstagramからとてもスムーズにThreadsを訪れることができます。さらに、現状では広告なしの空間が提供されており、Threadsを使っているユーザーは比較的、安全で安心な場所だと感じているようにも思います。
ですので、今のところどちらが有利かと問われれば、個人的にはThreadsに分があるかなと感じています。
もちろん今後、Threadsのアクティブユーザー数や利用の熱量が高まり続けると、Xと同じように炎上や対立、フェイク情報などが問題になる可能性も考えられます。
また、本格的に広告が導入されれば、快適ではない体験が出てくるかもしれませんので、まだまだ勝負の行方はわからないなとも思いますね。
トランプ大統領、TikTok米国事業の売却計画を承認

アメリカのドナルド・トランプ大統領は、短編動画アプリ「TikTok」の米国事業について、米オラクルやシルバーレイクといった米企業連合に売却する計画を承認しました。
この決定は、国家安全保障上の懸念を背景に、米国内のユーザーデータ保護と情報操作への対策を求める法律に基づくものです。
売却後は合弁会社がTikTok米国事業を運営し、米国側が過半数の株式を保有する形となります。
事業評価額は約140億ドル(約2兆円)で、今後120日以内に買収手続きが完了する予定です。
中国政府もこの取引に合意しており、習近平主席が電話会談で売却を承認したことが明らかになっています。

しばらく懸案事項となっていたTikTokの米国事業売却の件ですが、これで一つの決着ということになろうかと思います。
なぜTikTokの米国事業売却がこれほど求められていたかというと、その背景には「データ管理」と「情報操作」という2つの大きな懸念がありました。
一つは、TikTokの運営会社は中国企業のByteDanceですが、アメリカ国内の多くのユーザーデータがByteDanceを通じて中国政府に渡ってしまうのではないかという懸念です。
そしてもう一つは、TikTokのアルゴリズムによって世論が操作されてしまうのではないか、というリスクが指摘されていました。
今回の決定により、売却後はアメリカ企業が主体となる合弁会社がユーザーデータの管理やアルゴリズムの運営を担うことになります。これによって、アメリカ国民のプライバシー保護や安全保障面での懸念を軽減することを目指しているわけです。
この合意でTikTokは米国内でのサービスを続けられるようになり、中国企業の影響力は大幅に低減される見通しです。米中間の外交的な計算や、双方の利害を調整した結果として実現した動きと言えそうですね。
売上ゼロで時価総額3.1兆円、AIバブルの次は「原子力」か? Oklo熱狂の行方
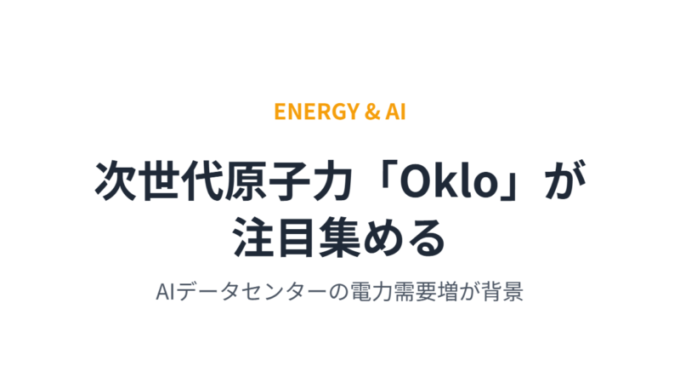
米国ではAIデータセンターの電力消費が問題となり、次世代原子力発電が解決策として注目されています。
そんな中、売上ゼロにもかかわらず時価総額3.1兆円を記録した原子力企業「Oklo」が脚光を浴びています。
Oklo株は、AIブームによるエネルギー需要の増加に加え、米英両政府による5兆円規模の投資協定を受けて、過去1週間で47%、半年間で400%以上も急上昇しました。
同社は初の原子力発電所建設を発表し、創業者夫妻は新たなビリオネアとなっていますが、直近の決算では大きな赤字を計上したままです。

Okloはアメリカを拠点とするスタートアップで、小型モジュール原子炉(SMR)を開発し、クリーンで安定したエネルギー供給を目指している企業です。
燃料リサイクル技術にも力を入れており、使用済み核燃料から新しい燃料を作り出すことで、長期間燃料交換をしなくても運転可能な原子炉の実現を目指しているそうです。
このOkloへの期待が高まっている背景には、AIの発展があります。
AIデータセンターを動かすには、膨大な電力が必要になります。そのため、たくさんの電力を作らなければいけないわけですが、一方で気候変動問題が大きな課題となっており、化石燃料で電力を作るのはちょっと…という風潮があります。
そこで、次世代の原子力分野がこれまで以上に注目されているというわけです。
しかし驚くべきことに、Oklo自身は創業から12年経っていますが、まだ一切の売上を生み出していません。現時点では商業運転の実績はなく、事業化に向けた技術的・経済的な検証が続いている段階です。
にもかかわらず、ここまで躍進している背景には、AIブームに加えて、OpenAIのサム・アルトマンCEOがOkloに投資している点、そしてトランプ大統領の第1期政権時代に築かれ、現在も続く政府との緊密な関係が推進力となっていると言われています。
主要企業が内定式、26年春卒 初任給引き上げ相次ぐ

2026年春に卒業予定の大学生を対象に、主要企業が一斉に内定式を開きました。
長引く人手不足を背景に、企業の採用熱は高く、初任給を引き上げる動きが相次いでいます。
大手各社の調査では、総合職の初任給を引き上げる企業が、前年より4.4ポイント増の88.8%にのぼり、売り手市場が続いています。
内定者や担当者からは「初任給の高さが決め手になった」「正当な評価を期待したい」といった声も多く聞かれました。
政府は採用活動の前倒し防止のため、内定は10月以降の日程遵守を企業に求めています。

近年、人材の獲得競争、特に新卒をはじめとする若手の獲得競争は激化しています。
ニュースでお伝えした通り、今は完全に学生側が有利となる「売り手市場」が続いているということです。若者の人口が減ってきていることを考えると、この流れは必然という感じでしょうか。
企業としては、どんどん学生から「選ばれる立場」になってきています。その中で、どのように自社を選んでもらうかが、非常に重要なポイントになります。
かといって、むやみに給料を上げたり、学生の顔色をうかがいすぎたり、誰でもいいから入社してもらえば良い、という話でもありません。
なぜなら、入社してもらった後には、できる限り活躍してほしいですし、できる限り離職も避けたいからです。
つまり、入社後のミスマッチを減らし、自社に合っていて、スキルもある学生をきちんと獲得したいわけです。
そのための一つの方法として、情報発信があります。
例えば、このVoicyでも採用目的で音声配信をしましょう、と企業向けにアピールされていますし、SNSやnoteなどで、企業の実態をリアルに伝えていくことが有効な手段の一つだと言われています。
OpenAI、生成AI動画だけのSNS「Sora」発表–文章から自身の映像、短編アニメなど生成
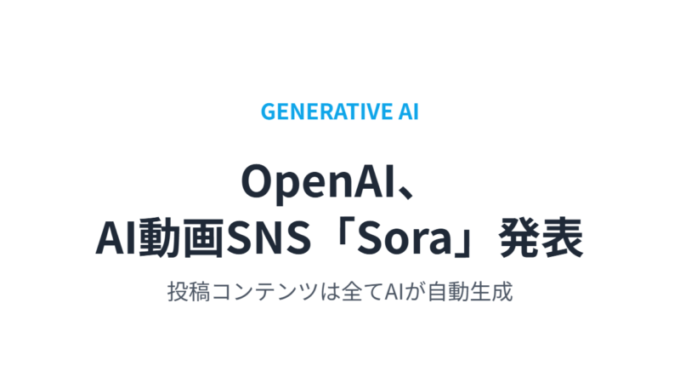
OpenAIは、文章からAI生成動画を作成し投稿できる新しいSNS「Sora」を発表しました。
現在は招待制となっており、最新モデル「Sora 2」を利用して自分や友人の顔を動画に登場させる「Cameo」機能や、音声付き動画生成にも対応しています。
ユーザーは一般のSNS同様に友人をフォローして動画を共有でき、投稿されるコンテンツは全てAIによる自動生成です。
従来のSNSとの違いは、人間が投稿するものの、動画の内容自体はAIが生成する点です。

OpenAIが「Sora」という名前のSNSを発表しました。これは動画生成AIサービスではなく、「SNS」であるという点がポイントです。
OpenAIのThomas Dimson氏は配信で、「ボットが投稿するわけではなく、人間が投稿する。
ただし中身はすべてAI生成だ」と説明しています。これはまさに逆転の発想ですよね。
既存のSNSでは生成AIによるフェイクコンテンツが課題になっていますが、このSNS「Sora」では、むしろ作り物しかない、ということになります。
「Cameo」と呼ばれる機能を使えば、自分や他人の顔をAI動画に登場させることができます。他人の顔を使う場合は、本人の承認があれば利用可能とのことです。
また、音声付きの動画生成も可能になったことで、短編アニメや映画のワンシーンのような、幅広い表現が簡単に作れるようになっています。
コンテンツの監視については、当初は厳しめに行うということだそうです。そうなると、動画生成のコストもさることながら、このSNSの運営には膨大なコストがかかりそうだなと感じます。
それに加えて、AIが生成するコンテンツの品質や著作権の問題など、今後さまざまな議論が必要な課題が出てきそうですが、とにかくこの先どうなっていくのか、とても気になりますね。
まとめ
以上、「週刊Work&Techニュース」 2025/10/03版についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!

