
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
「週刊Work&Techニュース」 2025/02/21版をお送りします!
今週のワークとテックの主なニュースをざっとチェックし時流をつかんでいただくことができますよ。
では、行ってみましょう!
グーグルAI「Gemini」、過去の会話を覚えていられるように!より的確な応答が可能になる
グーグルが開発中のAI「Gemini」が、ユーザーとの過去の会話内容を記憶し、それに基づいてより的確な応答を行う機能を搭載する予定です。この機能により、ユーザーとの対話がさらに自然で効率的になることが期待されています。
たとえば、以前話した内容を踏まえて質問したり、その人の趣味や好みに合わせた提案を行ったりすることも可能になります。
保存される情報はユーザー自身で管理可能。具体的にはチャット履歴の確認、削除、保存期間の設定ができます。

Geminiが過去の会話を記憶するようになるのは、大きな進歩ですね。
これまで、多くのAIチャットボットは、会話の流れが途切れたり、別のチャットでのやり取りを反映できなかったりすることがありました。しかし、Geminiが過去の会話を記憶することで、より人間らしい自然な対話が可能になります。
例えば、顧客対応においては、過去の問い合わせ履歴を参照することで、迅速かつ的確な問題解決が期待できます。教育分野では、生徒一人ひとりの学習履歴や理解度に合わせて、個別最適化された学習支援が実現するでしょう。
この機能は、現在はGoogle One AIプレミアムプランの英語版のみで利用可能ですが、今後の日本語対応、そして機能のさらなる進化に期待したいですね。
Google、「年齢詐称」をAIで判別へ
Googleは、AIを活用してユーザーの年齢を推定する新技術を2025年に米国で試験導入すると発表しました。
この技術は、アカウントの利用履歴や検索行動などのデータを基に、未成年か成人かを推定し、適切なセキュリティ設定を自動で適用します。例えば、18歳未満と推定された場合、YouTubeでは不適切なコンテンツが非表示になり、Google検索では「セーフサーチ」機能が自動的に有効になります。
ユーザーが誤判定だと感じた場合には、セルフィーや身分証明書で年齢を確認する選択肢も提供されます。この取り組みは、未成年者のオンライン安全性向上を目的としており、将来的には他国にも展開される予定です。

GoogleがAIによる年齢推定技術を導入する背景には、世界的に高まるオンラインセーフティへの意識があります。
特に、未成年者を不適切なコンテンツから守ることは、喫緊の課題といえます。
Meta(旧Facebook)やTikTokなど、他のプラットフォームも同様の技術開発を進めていますが、AIによる年齢推定には、まだ精度向上の余地があると言われています。
Googleは、検索履歴や動画の視聴傾向、アカウントの利用期間など、様々なデータを総合的に分析することで、より正確な年齢推定を目指すとしています。
「Yahoo!ニュースコメント」に導入のAI「コメント添削モデル」で「不快なコメント」が24%減少
LINEヤフーは、ニュース配信サービス「Yahoo!ニュース」のコメント欄に導入したAI「コメント添削モデル」の効果を発表しました。
このモデルは、投稿前にユーザーに表現の見直しを提案する仕組みで、不快なコメントの投稿が約24%減少したことが確認されました。また、修正されたコメントの約50%が不快度の低い表現に改善されたことも明らかになっています。
導入後も全体のコメント投稿数には大きな変化がなく、健全な議論の場を提供する効果が期待されています。

Yahoo!ニュースのコメント欄におけるAI「コメント添削モデル」の導入は、健全な言論空間を形成するための有効な取り組みと言えますね。不快なコメントは、時に議論を妨げ、ユーザーの参加意欲を削ぐ原因にもなりかねません。
「コメント添削モデル」は、投稿前にAIが表現の見直しを提案することで、投稿者自身に気づきを促す仕組み。感情的になっているところを踏みとどまらせるのは、とても効果的と感じます。
この技術は、GoogleマップのレビューやAmazonのレビューなど、他のプラットフォームにも応用できる可能性があります。
AIがユーザー間のコミュニケーションをサポートすることで、より多くの人が安心して意見交換できる場が広がることを期待したいですね。
xAI、新たなAIモデル「Grok 3」を発表
イーロン・マスク氏が率いるxAIは、新たなAIモデル「Grok 3」を発表しました。
このモデルは前世代よりも10倍以上の演算能力で事前学習をしており、高度な推論能力とデータ解析機能を備えています。また、新機能「DeepSearch」を搭載し、インターネットやSNSから情報を収集し要約する能力も追加されました。
「Grok 3」は科学分野やプログラミングなどで優れた性能を示しており、18日からXのプレミアムプラス会員向けに提供を開始します。

xAIの「Grok 3」は、OpenAI、Gemini、Claude、DeepSeekなどに続く、新たなAIモデルとして注目されます。特に、新機能「DeepSearch」による情報収集・要約能力は、ビジネスや研究など、様々な分野での活用が期待されます。
一方で、Xの最上位プラン「プレミアムプラス」の大幅な値上げも報道されており、ユーザーにとって悩ましい問題かもしれません。DeepSearchの性能が、この価格に見合うものであるかどうかが、今後のユーザーの動向を左右する可能性があります。
ChatGPTの「deep research」機能も注目されていますが、proプランの月々30,000円という高額な料金設定がネックとなっています。
Perplexityなど、他のサービスも同様の機能を投入しており、「Grok 3」が価格と性能のバランスで優位に立てるかどうかが、今後の競争を左右するでしょう。
退職代行モームリ、最も“使われた企業”とは? トップ40社の業種・回数を公表
退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスが、2022年3月15日から2025年1月31日までの利用データを基に、最も多く利用された企業の業種と回数を発表しました。1位は人材派遣会社で104回、2位はコンビニチェーンで65回、3位も別の人材派遣会社で57回。上位10社は、全て従業員数が1500人を超える大企業。
また、上位40社のうち、人材派遣会社が16社を占め、全体の4割に達しました。主な退職理由は「労働環境や人間関係」「退職時の強引な引き止め」などであり、特に派遣先企業での勤務環境が問題視されています。
同社はこれらの背景について「本社方針が現場に届かない管理体制の不備」が一因と指摘しています。
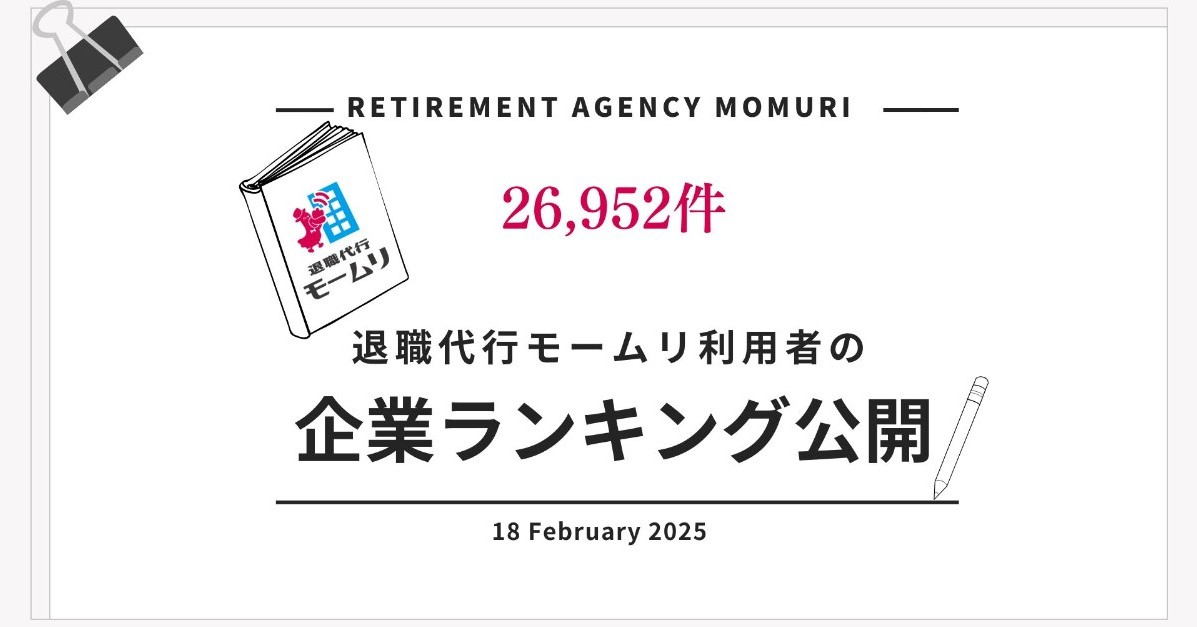
ランキング自体は、従業員数に依存するので、あまり参考になりませんが、人材派遣会社の利用が多い点は注目ポイントです。
人材派遣業界では、雇用元と就業先が異なるため、労働環境の実態把握が難しく、問題が潜在化しやすい傾向があります。また、派遣契約の仕組み上、退職時の引き止めが強引に行われるケースもあるようです。
労働環境や待遇に関する不満が、退職代行サービスの利用につながっている可能性も考慮する必要があるでしょう。
IT業界においても、実質的な派遣形態で働くケースは少なくありません。過去、SESの案件で、「聞いた仕事と違う」というときは、その確認と調整がとても面倒だった記憶があります。
以上、「週刊Work&Techニュース」 2025/02/21版についてお伝えしました。次回もお楽しみに!
まとめ
以上、「週刊Work&Techニュース」 2025/02/21版についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!

