
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
「週刊Work&Techニュース」 2025/10/10版版をお送りします!
今週のワークとテックの主なニュースをざっとチェックし時流をつかんでいただくことができますよ。
では、行ってみましょう!
OpenAIの動画SNS「Sora」、米App Storeで1位に–「ChatGPT」超え

OpenAIが開発したAI動画SNSアプリ「Sora」が、米国App Storeの無料アプリランキングで1位を獲得しました。
Soraは、かつて1位だった同社の「ChatGPT」やGoogleの「Gemini」といった競合アプリを上回る人気となっています。
TikTokのような縦型動画フィードが特徴ですが、投稿される全ての動画がAIによって生成されている点が大きな違いです。
特に、ユーザーが自身の顔や声をAIに登録し、AI生成動画の登場キャラクターとして使える「Cameo」機能が話題となっています。
現在は招待コードを持つiOSユーザーのみ利用可能で、Androidユーザーはウェブ版でアクセスできます。
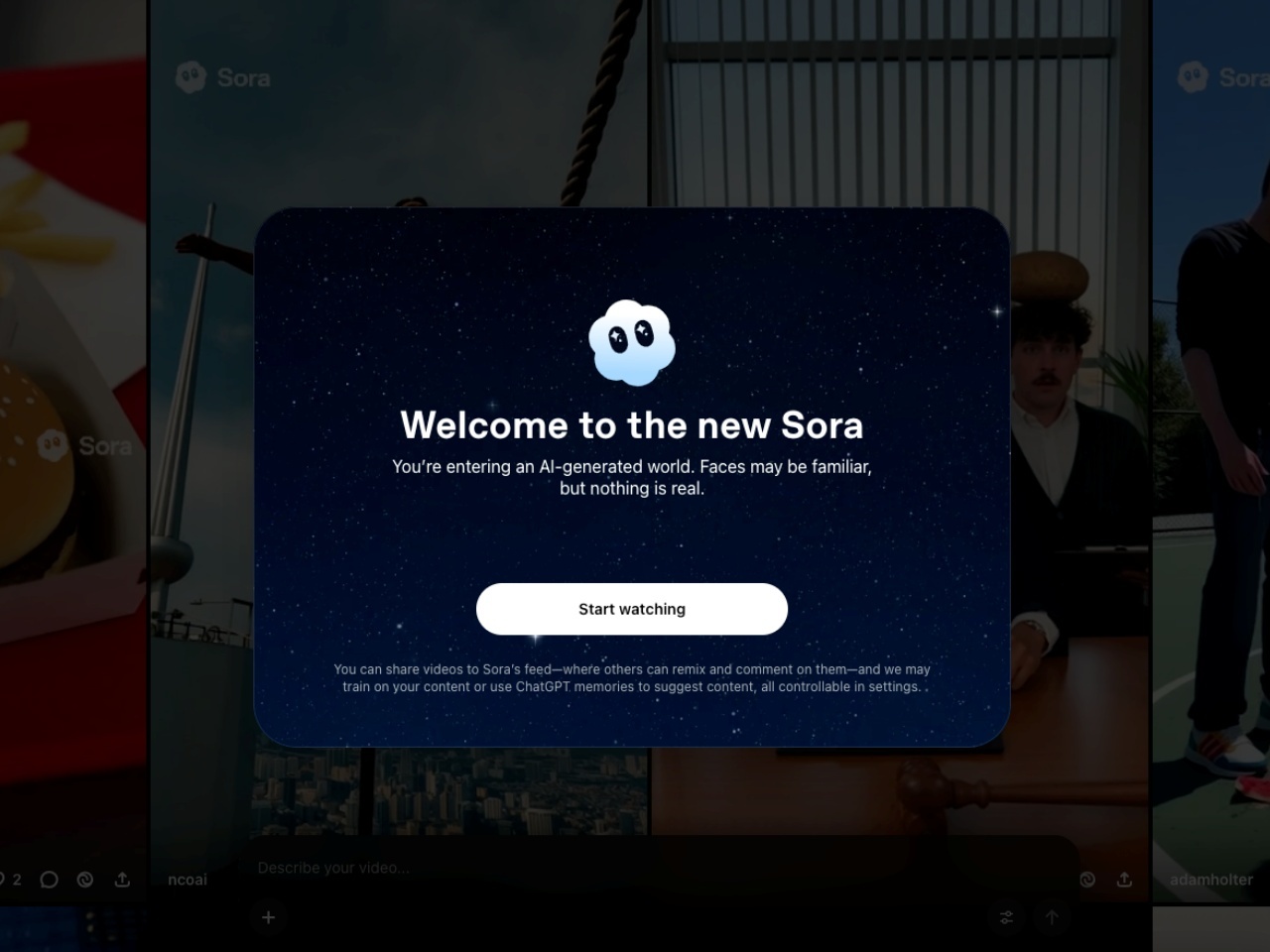
Soraは、OpenAIの最新AIモデル「Sora 2」によって動画が生成される、新しいタイプのソーシャルメディアです。
従来のSNSと違い、アップされている動画はすべてテキストなどからAIが作ったもので、実際の撮影映像はありません。
ユーザーは自分の顔や声を使い、AIが生成した動画のなかにキャラクターとして“共演”することも可能です。
この人気については、2つの見方ができそうです。
1つは、最先端のAIが持つ創造力を一目見ようと多くの人が殺到している、一時的な流行という見方です。
もう1つは、OpenAIが信じているように、コンテンツの作られ方に本質的な変化が起きていて、Soraが他のアプリでは不可能だったレベルの創造性を可能にしているため、人々がこのアプリに留まり続けるという考え方です。
今後どちらの方向に進んでいくのか、注目したいですね。
高市自民新総裁、党立て直しへ「ワークライフバランスという言葉捨てる」
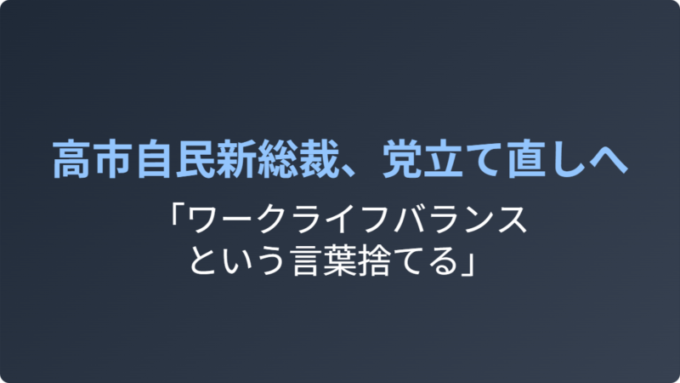
自民党の新総裁に選出された高市早苗氏は、就任直後のあいさつで「ワークライフバランスという言葉を捨て、馬車馬のように働いて党を立て直す」と強い決意を示しました。
この発言は、党員や国会議員に対し、全力で取り組む姿勢を求めたものですが、長時間労働の助長につながるとの懸念も広がっています。
一方で、「強い覚悟を持ったリーダーの誕生」と評価する声もあり、賛否が分かれる形となっています。
ワークライフバランスとは、仕事と生活の調和を図るという考え方で、ここ数年、健康的な働き方を目指す社会の流れのなかで広がってきました。
この背景には、かつての雇用者と労働者の力関係があります。
過去には、上司や社風に逆らえなかった若い社員が過労によって命を落とす痛ましい事件もあり、弱い立場になりがちな労働者を守るために、仕事(ワーク)と生活(ライフ)を分けてバランスを取るという考え方が重要視されてきました。
私自身は経営者という立場なので、働くのが好きですし、自分の判断で仕事と生活のバランスをシームレスに調整できます。
体調が優れない時や、家族のために時間が必要な時は、自分で裁量をもって働き方を決めることができます。
高市氏の発言は、おそらく党内の政治家の方々に向けられたものだと思いますが、その言葉によって、本当に過労死するほど追い詰められるような関係性のなかで仕事をしているのかどうかが、この発言を考える上での一つのポイントになるのかもしれませんね。
動画AIのSora、著作物勝手に使う「オプトアウト方式」に不満の声
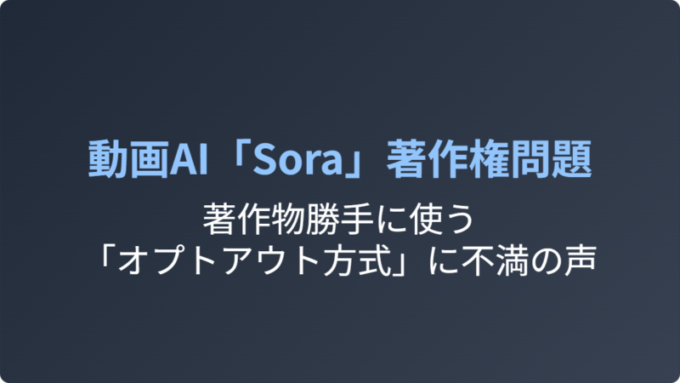
OpenAIが開発した動画生成AI「Sora」が、著作権者が明示的に拒否しない限りコンテンツを利用できる「オプトアウト方式」を採用していることに対し、日本のアニメ業界などから不満の声が高まっています。
この方式では著名な日本発キャラクターの動画が、権利者の許諾なく生成される事例が相次ぎ、関係者から「権利が守られない」との懸念が噴出しています。
一方、ディズニーなど一部海外企業のコンテンツについては事前に利用が制限されるケースもあり、対応の差も問題視されています。
「オプトアウト方式」とは、AI開発企業が著作物を学習や生成に利用することを基本的に許可した上で、著作権者が利用を拒否する場合にのみ、その手続きを求める仕組みです。
このため、権利者が知らない間に自社のキャラクターや作品がAIのデータとして使われてしまう可能性があります。
実際に9月30日にSoraの最新版が公開された当初は、日本の著名なキャラクターが生成できてしまい、著作権侵害の可能性が指摘されました。
批判を受け、OpenAIは方針を一部修正し、今後は権利者が自身のキャラクターなどの利用を細かく指定でき、「一切使わせない」という選択も可能にすると発表しました。
しかし、ディズニーのキャラクターは当初から生成できない状態になっており、OpenAIが一部の権利者には事前に対処していたと見られ、その対応の差も問題視されています。
ディズニーは、AIがコンテンツを「生成する」段階だけでなく、データを「学習する」段階から許諾が必要だと主張しており、議論はまだ続きそうです。
Google、Webブラウザーを操作するAI「Gemini 2.5 Computer Use」を発表/ワークフローの自動化や、UIテストの効率化などに向け
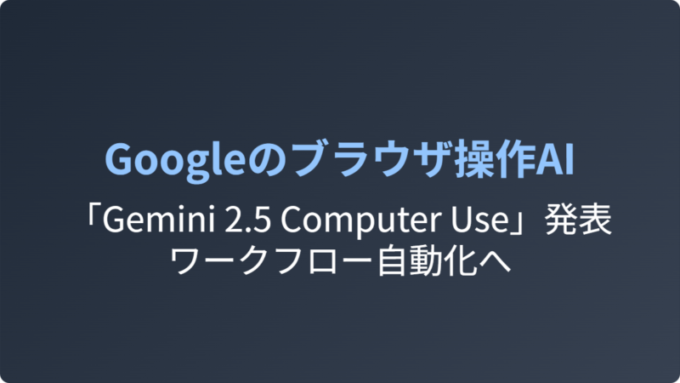
Googleは、AIによってWebブラウザーの操作を自動化できる新モデル「Gemini 2.5 Computer Use」を発表しました。
このモデルは、画面のスクリーンショットと直前の操作履歴をもとに、クリックや入力、スクロールなどのUIアクションを自動生成し、タスクを完了するまで繰り返し操作を行います。
Gemini 2.5 Proをベースとし、Google AI StudioやVertex AIで利用できるプレビュー版として登場しました。人間が手動で行っていたフォーム入力やメニュー選択、情報収集などの作業が、AIによってより効率的にこなせることが期待されています。
Googleがリリースした「Gemini 2.5 Computer Use」は、Webブラウザーの画面を直接解析し、まるで人間のように操作できるのが特徴です。
画面上のボタンをクリックしたり、入力欄に文字を入れたりといった細かな操作を自律的に行い、「一番安いフライトを検索して予約する」といった複雑な指示にも対応できます。
これは既存のRPAという技術と似ていますが、RPAは決められたルール通りにしか動けず、少しでも前提条件が変わると停止してしまう課題がありました。
一方、AIであれば、多少の変化があっても状況を自ら判断し、揺れを吸収しながらユーザーの望みをかなえてくれることが期待できます。
性能比較のテストでは、他の主要なAIモデルよりも優秀な結果だったとのことですし、この分野での競争を通じて、今後さらに精度は上がっていくことでしょう。
1万人削減のパナソニック、黒字リストラの企業の本音。氷河期世代に突きつけられる現実
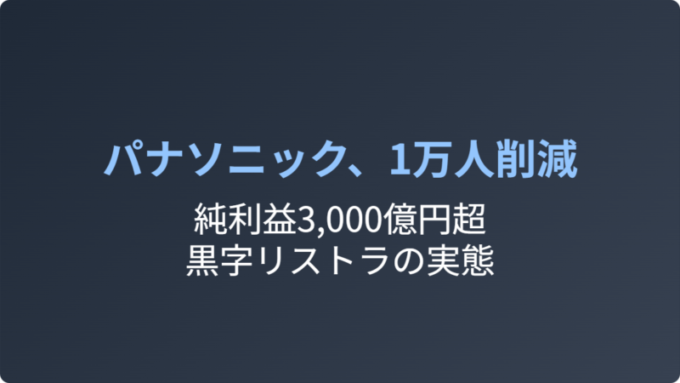
パナソニックホールディングスが国内外で1万人規模の人員削減を実施します。
今回は純利益3,000億円超という黒字にもかかわらず、「人員の適正化」として主に49歳から59歳の中高年社員、いわゆる氷河期世代やバブル世代が対象です。
国内では5,000人の削減を予定し、家電事業などの部門に影響が及びます。
他にも三菱電機など電機業界を中心に、黒字企業による大型リストラが相次いで発表されています。
これらの動きは、今後の企業構造改革の波を象徴しています。

黒字でありながらリストラを行う背景には、単なる人件費の削減だけでなく、人員の若返りを図り、組織の高齢化を是正するといった複数の理由があるようです。
記事からは、50歳以上の社員は年功序列の賃金で給与が高く、人数も多い一方で、彼らが新しい価値を創造することは難しい、という企業の割り切りも感じられます。
本来であれば、キャリアカウンセリングやリスキリングの機会を提供することで、社員が新たな価値を生み出せるように導くことも可能かもしれません。
しかし、リストラに比べて時間もコストもかかり、成果も見えづらいのが現実なのでしょう。
人生100年時代において、50歳はまだ人生の折り返し地点です。
このような状況を考えると、会社に頼るだけでなく、私たち一人ひとりが自ら中長期的なキャリアを設計し、主体的に進んでいくことが、ますます大切になってきていると感じます。
まとめ
以上、「週刊Work&Techニュース」 2025/10/10版についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!

