
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
VoicyからPodcastへの移行を考え始めたら、もっと大事な「発信の軸」を見直すことに。
Geminiとの壁打ちで見えた課題と、大きな気づきをシェアします。
ということで、今回は「VoicyからPodcastへの移行検討が、発信活動全体の「棚卸し」になった話」です。
では、行ってみましょう!
移行検討が「発信の軸」を見直すキッカケに

お伝えしたとおり、VoicyからPodcastへの移行を本格的に検討しはじめたところ、この僕の発信活動の「見通し」がしっかり定まっていないことに、なんだか気持ち的にザワザワするものがありました。
日々の活動の軸を作る大事な習慣でもあるので、早く方針を決めたいなと思っていたんです。
そこで、早速Geminiと壁打ちしながら考え始めました。
具体的には、僕の「スキルアップラジオ」のどの部分を、どう移行するのか(全部は移行できなそうなので)、それから過去分の音声データをどう活用するのか、といった移行の方法やロードマップについて提案してもらいました。
ロードマップ自体は、1.5ヶ月ほどのプランで「この通りやれば、ちゃんと移行できそうだな」という具体的なものが出てきました。
「いよいよかー」なんて感じにもなりますね。
見えてきた「枝葉」の課題たち
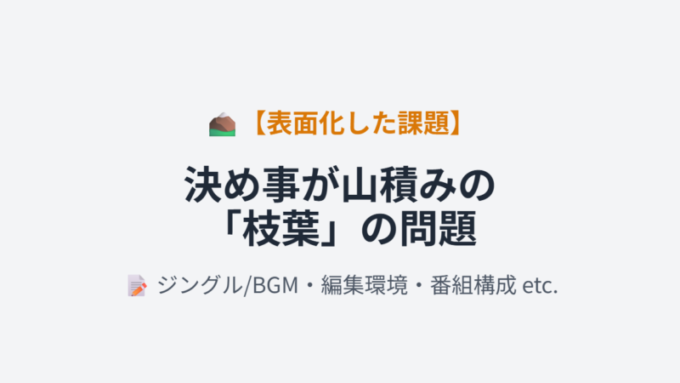
ただ、いざ具体的に考えると、決めなければいけないことが山積みであることにも気づきました。
例えば、Podcastにするならジングル(番組の冒頭や終わりの短い音楽)やBGMも必要になります。編集作業も発生するので、その環境も整えなければいけません。
さらに、せっかく移行するなら番組構成も変えていきたいなと思ったり、配信の方針も考え直す必要があります。
今、Voicyでは土日に生放送のアーカイブを流しているのですが、Podcastでは生放送機能が使えなくなります。「じゃあ土日はどうするんだ?」とか、そういったことを全部決めていく必要があるんですね。
このように、枝葉の部分で、とてもたくさん考えることが出てきました。
課題の根本は「上流」にあった
そうなると、「もしかしたら、もっと上流から整理した方がいいのかもしれない」という気がしてきたんです。
というのも、音声配信は、あくまで僕の発信活動全体の一部です。ブログや各種SNSも含めて、今は「マルチアウトプット」という方針でやっています。
ですから、発信活動全体の方針をしっかり固めた方が、今出てきたジングルやBGM、配信方針といった枝葉の部分も決めやすくなるだろう、と考えたわけです。
そこで、一旦Podcastへの移行の話はストップして、「発信活動全体を一度棚卸しして、全体最適を目指したい」と、再びGeminiと壁打ちを始めました。
Geminiの提案「ハブ&スポーク戦略」
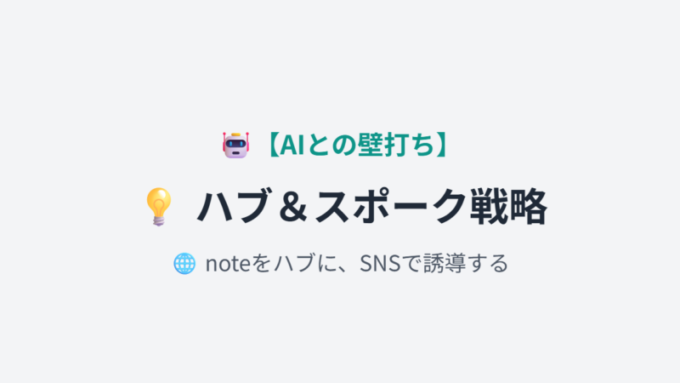
するとGeminiが、「ハブ&スポーク戦略に再構築するのはどうでしょう?」と提案してきました。
これは、自転車の車輪をイメージしてもらうと分かりやすいです。ハブが車輪の真ん中、スポークがそこから放射状に伸びている棒(骨組み)ですね。
具体的には、「noteをハブ(中心)にして、各種SNSをスポーク(誘導経路)として使いましょう」という提案でした。
noteにテキスト記事をしっかり書き、Podcastや、もし作るならDiscordなどのコミュニティへの入り口としてもnoteを活用する。そして、各種SNSは、そのnoteの記事に誘導する役割(つまりnoteのリンクを貼る)を持たせる、という戦略です。
なるほどな、と思いました。
というのも、今は各SNSでコンテンツを丸出し(その場で完結できる形で投稿)していますし、さらにブログへのリンクやVoicyへのリンクも貼っている状態です。
全部に全力で投稿すればよいという話でもないのかも知れません。
独自サイト vs note のジレンマ
ただ、Geminiはnoteを提案してきましたが、僕には「いつも隣にITのお仕事」という独自サイトがあり、そこには既に二千数百の記事が溜まっています。
「これらの棲み分けはどうするの?」という新たな疑問が出てきます。
SEO(検索エンジン最適化)でいうと、現状ではnoteの方が強そうです。
しかし、noteには「コンテンツをnote(プラットフォーム)に握られてしまう」というリスクがあります。
もちろん、今のところnoteはクリエイターをとても大事にしているように見えるので、変なことにはならないだろうなとは思いつつも、長期的に見たとき、データは自分でも持っておきたい、という気持ちもあります。
そんなやり取りをGeminiとしていました。
さらに上流へ:「企画書」の必要性
またしても、そんな枝葉の話をしていたところ、ふと思い出したことがあります。
以前、flier book laboの樋口さんのCampに参加したとき、「一度、きちんと企画書を作り直すのも手だよ」というアドバイスをもらったことがあったんです。
確かに、その時も「スキルアップラジオ」の企画を練り直そうと思っていたのに、すっかりやらないまま今日に至ってしまっていました。
発信活動の方針を決める前に、もっと上流、つまり僕の発信活動全体、僕の「発信空間」全体についてのコンセプト、ターゲット、そしてベネフィット(リスナーや読者が得られる価値)を整理する方が、枝葉の話もずっと決めやすくなるはずです。
そこで、三度(みたび)、Geminiと改めてその点について壁打ちを始めました。
壁打ちで見えた「大きな気づき」
これが、すごく良い時間になりました。
話したいことは山ほどあるのですが、今日はその中で得た「一つの大きな気づき」についてお伝えしたいと思います。
その前提として、そもそも僕がVoicyというプラットフォームを使って何を実現したかったか、というお話をさせてください。
僕は、Voicyという場所を使って、そこにコミュニティを作りたかったんです。
具体的には、「ノンプロ研(僕が運営するコミュニティ)」より一回り大きいコミュニティです。規模感でいうと数百人以上、うまくいけば数千人くらいになるといいな、と。
そこにいさえすれば、「日々働くことについての前向きな情報や知識」を摂取することができ、「ポジティブなリスナーさん同士のつながり」を感じられる。そんな場所を作れたらいいな、と思っていました。
Voicy運営で直面した「2つの課題」
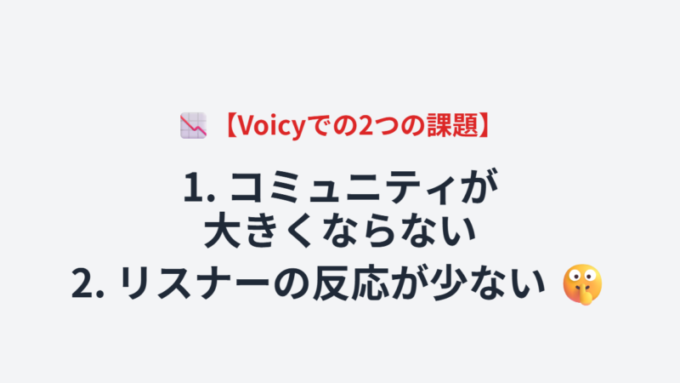
しかし、実際にやってみると、その理想に至る前に2つの大きな課題が立ちはだかりました。
課題1:コミュニティが大きくならない
まず一つ目。「Voicyを中心としたコミュニティがあまり大きくならなかった」という問題です。
実際、ノンプロ研と同じくらいのサイズ感か、もしかしたらそれよりも小さいかな、ぐらいのコミュニティにしかなっていない印象です。
その理由としては、「新規リスナーさんの獲得が結構難しい」という問題がありました。
Voicy内からの流入が弱くなってしまったという感覚がありますし、何より、Voicyの外から新しいリスナーさんを連れてくるハードルが、すごく高いなと感じるんです。
Voicyアプリをダウンロードしてもらい、登録してもらって、ようやくリスナーになってもらい、それを習慣に組み込んでもらう。これは、なかなか高いハードルですよね。
課題2:リスナーさんの反応が少ない
そして、もう一つの課題が、「リスナーさんの反応(アクション)が少ない」ということです。
たとえコミュニティのメンバーが多くなくても、そこで活発なアクションやリアクションがあれば、盛り上がっている感じは出ます。
ずっと暖かいリアクションをし続けてくださるリスナーさんもいらっしゃるのですが、ちょっと少なくて盛り上がりに欠けるかな、という感覚がありました。
これは、ひとえに僕の話術や腕の問題も大いにあるんですけれども(苦笑)、もう一つ、根本的な原因があるな、と気づいたんです。
マルチアウトプット戦略が招いた「反応の分散」
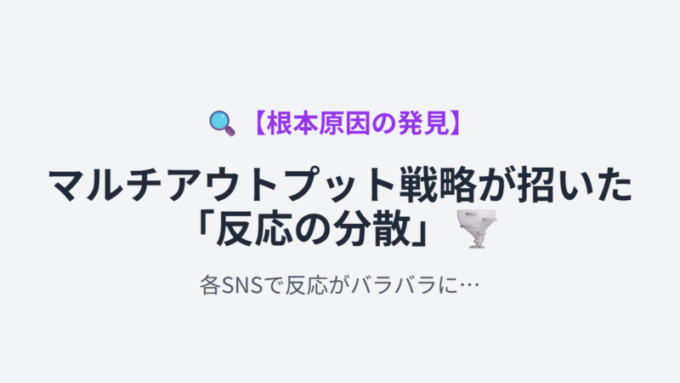
それは何かというと、「マルチアウトプット戦略」が、逆に反応の少なさを引き起こしてしまっている可能性があるな、と思ったんです。
今や、インターネット空間上で人々がどこにいるのかは、かなり多様化しています。
X(旧Twitter)にいる人もいれば、Instagram、Facebookにいる人もいます。Google検索を使う人もいれば、最近はAIに尋ねる人もいる。
YouTubeにはたくさんの人がいそうですし、学びであればUdemy(オンライン学習プラットフォーム)にもいます。
その中で、Voicyにいる人は、決して多くはないわけです。
多くの人に届けたい、という思いがあるので、僕はそれぞれのプラットフォームに対して、そこでコンテンツを摂取できるように「マルチアウトプット」をしよう、という戦略で今年やってきました。
そうなると、僕のコンテンツを届けたいターゲットの皆さんは、いつも自分がいる場所(XやInstagramなど)で僕のコンテンツに接することができ、そこで満足することができるわけです。
そして、そこで満足していただけたなら、当然、そこで「いいね」やコメントなどの「反応」をしますよね。
つまり、バラバラのあちこちにコンテンツを提供しているので、その反応もバラバラの場所で起きてしまっているということです。
例えば、トータルで20人の方が反応してくれていたとしても、それが5つのプラットフォームに分散していたら、1つの場所では平均4つの反応にしかなりません。
これでは、なんとなく「あまり盛り上がっていないように見えてしまう」という現象が起こります。
こうして考えてみると、先ほどGeminiが提案した「ハブ&スポーク戦略」(どこか中心となる場所=ハブに誘導する)は、確かに有効なのかもしれないな、と改めて思いました。
発信の「Why, Who, What」を再定義する
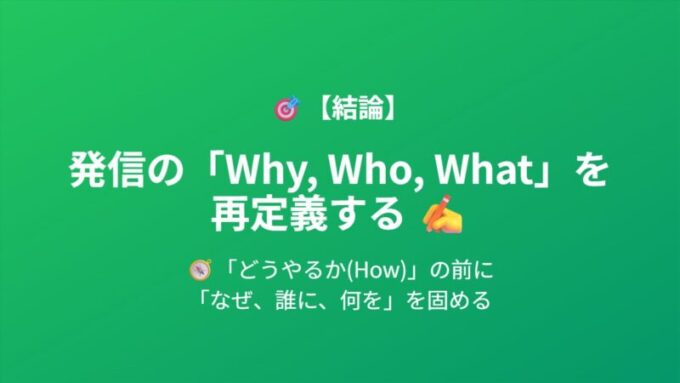
と、このように、VoicyからPodcastへの移行という、どちらかといえば「How(どうやるか)」の検討から始まったわけですが、それが結果として、僕の発信活動の最も上流である、
- Why(なぜ発信し続けるのか?)
- Who(誰に届けるのか?)
- What(何を提供するのか?)
この部分を、もう一度しっかり整理する、とても意義深い機会になっています。
今のところ、この「Why, Who, What」がいよいよ整理できてきた感じです。
特に「What(何を提供するのか)」の部分では、僕がノンプロ研というコミュニティを運営してきたノウハウが、とても活かせる気がしています。
引き続きこの整理を進めていきますので、今後の展開をぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。
まとめ
以上、「VoicyからPodcastへの移行検討が、発信活動全体の「棚卸し」になった話」についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!

