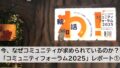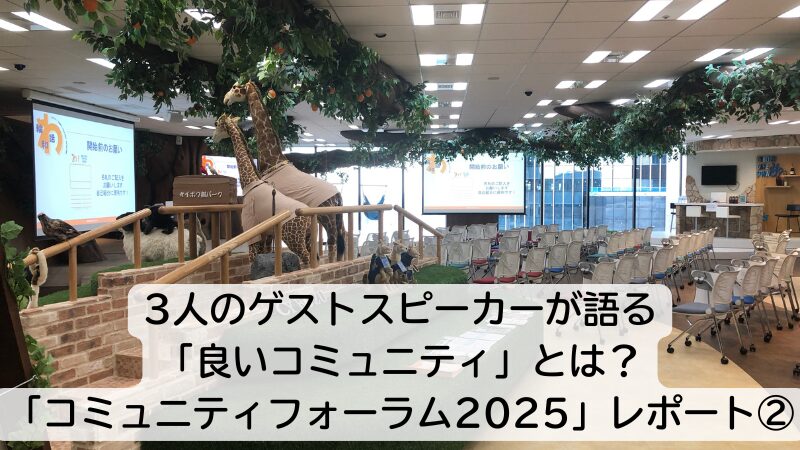
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
コミュニティの祭典「コミュニティフォーラム2025」レポート第2弾!
3名のゲストスピーカーが語る「良いコミュニティ」とは??
ということで、今回は「3人のゲストスピーカーが語る「良いコミュニティ」とは?~「コミュニティフォーラム2025」レポート②」です。
では、行ってみましょう!
年に一度のコミュニティの祭典「コミュニティフォーラム2025」
先日開催された「コミュニティフォーラム2025」、本当に素晴らしいイベントでしたね。
昨日はイベントの概要と、主催であるCRファクトリー代表の呉哲煥さんの基調講演についてお伝えしましたが、今日はゲストトークの模様をお届けします。
今回のゲストトークは、ちょっとした仕掛けがありました。
4名のゲストスピーカーが、10分ずつお話するのですが、お二人の発表が終わったら、会場参加者全員で30分間(長い!)のグループディスカッションを行う、それを2セットするというもの。
「ようこそ『わ』の世界へ!」というキャッチフレーズの通り、参加者みんなが「輪」になって、「和」気あいあいと「語」り合う、まさにそんな温かい空間が生まれていました。
こまちぷらす 森祐美子さん:「コミュニティと参加」
「わたし」と「コミュニティ」の間にあるもの
まず最初に登壇されたのは、NPO法人こまちぷらすの森祐美子さん。「コミュニティと参加」というタイトルでお話いただきました。
実は、我々ゲストスピーカーは、今回実行委員のみなさんから、「良いコミュニティとは何かというテーマで話してほしい」というお題をいただいてました。
森さんはその問いに対して、「自分にとっての良いコミュニティ」だから、「わたし」と「コミュニティ」の間にあるものが大事だと語りかけてくれました。
原体験から生まれた「こまちぷらす」
もともと、我々には学校、会社、サークルなど、常に用意されたコミュニティがありました。
しかし、森さんは出産を機に、そういったコミュニティからリリースされてしまったこと、そのたいへんな時期に自ら勇気を出して外の世界に飛び出し、新しい関係性を築くことの難しさを痛感されたそうです。
そんな経験から生まれたのが、「こまちぷらす」です。「子育てをまちの力で豊かにする」というビジョンを掲げ、横浜市戸塚区の常設カフェの運営を中心に、多岐にわたる活動を展開されています。
こまちぷらすの活動を支えているのは、50名のスタッフと、350名を超える登録ボランティアの皆さん。
つながりのデザイン:ゆるやかなスロープ
森さんのお話で特に印象的だったのは、「つながりのデザイン」が非常に秀逸である、ということ。
こまちぷらすでは、最初から明確な目的意識を持って参加する人ばかりではなく、ふらっとカフェに立ち寄った人が、徐々にコミュニティに関わるようになっていく、そんな自然な流れが生まれるように設計されていました。
僕が運営しているノンプログラミング研究会(ノンプロ研)は、月額制のコミュニティなので、最初から明確な目的意識を持った方が参加されます。こまちぷらすのような、ゆるやかなスロープのようなものを、うまくつくれないかな…などと考えておりました。
母親アップデートコミュニティ なつみっくすさん:「内向型こそ、コミュニティ運営を。」~多様な価値観に触れる場づくり~
「母親を、もっとおもしろく」がきっかけでコミュニティが生まれた
続いて登壇されたのは、「母親アップデートコミュニティ」を主宰する、なつみっくすさんこと鈴木奈津美さん。「内向型こそ、コミュニティ運営を。」というタイトルでお話いただきました。
なつみっくすさんは、会社員として働きながら、母親アップデートコミュニティの運営も行うという、パラレルキャリアを実践されています。
母親アップデートコミュニティは、NewsPicksでのイベント「母親を、もっとおもしろく」がきっかけで生まれたコミュニティ。
このイベントで、なつみっくすさん自身が、「母親はこうあるべき」という固定観念に縛られて苦しんでいたことに気づき、同じような思いを持つ参加者の方々と共にコミュニティを立ち上げることになったのだとか。
「自分を知る」「触発」「挑戦」の3ステップ
母親アップデートコミュニティでは、「自分を知る」「触発、多様な価値観に触れ合う」「挑戦する」という3つのステップを大切にしています。
会員数は220名を超え、これまで開催されたイベントは1100以上、読書会も250回以上開催されているという、非常に活発なコミュニティ。ノンプロ研も負けてられませんね。
また、Voicyで「母親アップデートラジオ」という番組を配信しており、交代制でパーソナリティを務めているそうです。Voicyのこんな活用の仕方があるのか…と思いました。

内向型の強みを生かすコミュニティ運営
そんな活発なコミュニティを、副業として続けられている秘訣は何なのでしょうか?
内向型というと、今の時代でいうとちょっと不利だみたいな、そんなイメージありますよね?
しかし、なつみっくすさんは、内向型ならではの強み、例えば、本質を見抜く力、深く考える力、観察力、共感力などが、コミュニティ運営に非常に向いている、と語ってくださいました。
僕も内向型だと自認していたので、なるほどなぁと思います。内向型のみなさん、コミュニティを!
サイボウズ ソーシャルデザインラボ 渡辺清美さん:「コミュニティ」と「コミュニケーション」の可能性
サイボウズの社会課題へのアプローチ
最後に紹介するのは、サイボウズソーシャルデザインラボの渡辺清美さん(きよみんさん)です。
きよみんさんは、「『コミュニティ』と『コミュニケーション』の可能性」というテーマで、サイボウズが取り組む社会課題解決に向けた活動についてお話してくださいました。
サイボウズといえば、kintoneなどのITツールを提供している有名IT企業で、そのパーパスは「チームワークあふれる社会を創る」です。
ソーシャルデザインラボは、そのサイボウズ流のチームワークを生かして、「多様な価値観の人が安心して暮らしている社会づくり」に取り組んでいる部署です。
社会課題にアプローチする実証実験を「育苗実験」と名付けて、さまざまな活動が行われています。例えば、「ワクワクする学び場を創る」「災害時のICT活用」「児童虐待を防ぐ」といったテーマでのプロジェクトです。
「しんどい」を共有する:当事者研究とkintone
デイサービス(生活介護)に通所している「えっちゃん」ときよみんさんが取り組んでいる当事者研究のお話は、とても印象的でした。
当事者研究とは、障害や病気などの当事者が、仲間と協力して自分自身の困りごとを研究する活動のこと。
「『しんどい』っていえない」をテーマにしたイベントをきっかけとして、きよみんさんご自身も、がん治療の経験があったことから、この当事者研究に取り組まれました。
えっちゃんからの「しんどさを共有するアプリ」を作りたいという話から、kintoneを使って、日々の出来事や気持ちを共有する仕組みなどを作っていきました。
ITというと効率化のためでしょとか冷たいイメージをもたれやすいですが、このような温かいつながりを生むこともできるという事例は、多くの方にぜひ知っていただきたいと思いました。
非営利団体向けITツール支援の重要性
サイボウズをはじめ、多くのIT企業が、非営利団体向けに特別なライセンスやプランを提供しています。
その情報自体、まだまだ知れ渡っていないような気もしますし、それを用いたこのような取り組みは、もっと広く知られても良いのではないか、と強く感じました。
僕も、微力ながら、こういった情報を発信していきたいと思います。
まとめ: こんな素敵なコミュニティに溢れた社会を
今回のゲストトークを通じて、「良いコミュニティ」とは、単に人が集まる場所ではなく、それぞれの参加者が安心して自分を表現でき、互いに支え合い、共に成長できる場なのだと、改めて感じました。
そして、みなさんがお話されたような素敵なコミュニティに溢れた社会にしていきたい、そんな思いを新たにした一日でした。
以上、「3人のゲストスピーカーが語る「良いコミュニティ」とは?~「コミュニティフォーラム2025」レポート②」についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!