
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
学びのコミュニティについて、Voicy「スキルアップラジオ」のリスナーの皆さんからたくさんのコメントをいただきました。
今回はそのコメントをご紹介しつつ、コミュニティ運営を成功させるための秘訣を深掘りしていきます。
ということで、今回は「なぜこの学びのコミュニティは続くのか?OODAループとソース原理の力」です。
では、行ってみましょう!
- 学習コミュニティをつくろう #7: 企業にとってもめちゃくちゃ意義がある
- 学習コミュニティを作ろう #9: コミュニティ継続には時間と モチベーションが必須である
- 学習コミュニティをつくろう #10: 学習コミュニティは何を目指して活動すればいいのか
- 学習コミュニティをつくろう #11: OODAループが超有効な理由と観察の仕方
- 学習コミュニティをつくろう #12 コミュニティ内外の流れをつかみ、方向づけをしよう
- 学習コミュニティをつくろう #13: OODAループで迅速な意思決定と行動を
- 良い学びのコミュニティとは何か
- 『すべては1人から始まる』~その取り組みの「ソース」は誰ですか?
- おしごと相談室 #16: 「働くの価値を上げる」の作り方
- まとめ
学習コミュニティをつくろう #7: 企業にとってもめちゃくちゃ意義がある
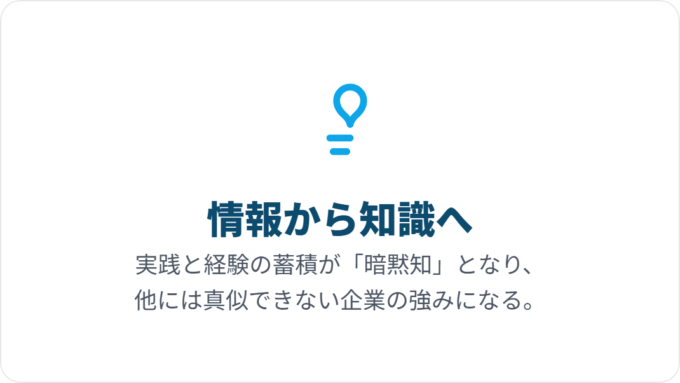
まずはじめに、学びのコミュニティの根幹に関わる「情報」と「知識」の違いについて、皆さんからいただいたコメントを見ていきましょう。
ゆうきさん
情報:WEBや書籍等で得られただけで終わったもの
知識:実践や活用の経験の蓄積
実践共同体は暗黙知・形式知が共有される。企業の中に社内コミュニティがあれば、暗黙知も含めてコミュニティに知識が保管される。暗黙知は真似するのは難しく、企業としての強みになる。
kenさん
情報と知識の違い
この部分は働き方を考える上でも非常に参考になる考え方
当たりの言葉しかないけど、確かにしっかり意味を考えたことない
ゆうきさん、kenさん、ありがとうございます。
お二人がおっしゃる通り、「情報」と「知識」は似ているようで全く異なります。今やAIに聞けば、世界中のありとあらゆる「情報」は一瞬で手に入ります。
でも、それをどう解釈し、どう活用するかという実践的な「知識」は、やはり人間が経験を通して蓄積していくしかありません。
特にゆうきさんが指摘してくださった「暗黙知」は、コミュニティの価値を考える上で非常に重要なキーワードになります。
暗黙知とは、言葉や文章で表現するのが難しい知識のこと。感覚とか勘とかがありますよね。これはマニュアル化するのが難しく、他の人や会社が真似するのも困難です。
企業研修などで「従業員にスキルを身につけさせると、転職してしまうのでは?」と心配される経営者の方に時々お会いしますが、実はその逆なんですよね。
社内に学びのコミュニティのような「実践共同体」があれば、個人の持つ暗黙知が組織全体に共有され、蓄積されていきます。
それは結果的に、他社には真似できない強力な「企業の強み」になるんです。コミュニティは、個人のスキルアップと組織の成長を両立させる素晴らしい仕組みなんですね。
学習コミュニティを作ろう #9: コミュニティ継続には時間と モチベーションが必須である

活気のあるコミュニティも、継続させていくのは簡単なことではありません。そこには「燃料」が必要だと、皆さんも感じていらっしゃるようです。
ゆうきさん
活動には燃料が必要。我々のリソースはそこまで大きくなく、ギリギリ。なので、そのための戦略・戦術が必要である。
kenさん
時間とモチベを持続的に投下循環させる必要があり、それが戦略
その視点がないとむしろコミュニティの継続は難しい
まさにおっしゃる通りです。コミュニティ活動における燃料とは、メンバーの「時間」と「モチベーション」。そして、この燃料は無限ではありません。特に本業の傍らで活動していると、とくに時間のリソースは本当にギリギリですよね。
だからこそ、「戦略」が必要になります。ただ「頑張ろう!」と気合を入れるだけでは、いつかガス欠になってしまいます。
限られた時間とモチベーションを、どうすれば最も効果的に使い、さらに再生産できるような循環を生み出せるか。それを考えることこそがコミュニティ運営における戦略であり、継続の鍵を握っていると言えるでしょう。
学習コミュニティをつくろう #10: 学習コミュニティは何を目指して活動すればいいのか
では、コミュニティは一体何を目指して活動すれば良いのでしょうか。目標設定についても、示唆に富むコメントをいただきました。
ゆうきさん
領域:学ぶテーマ
アウトカム:メンバーによるコミュニティ内外での価値提供の総和の最大化
アウトプット:コミュニティの参加人数・コミュニティ外でのアウトプットの回数・メンバー間の繋がりの数等
kenさん
目指す指標が数値で表されるものだけではない。感じることでわかる部分も大事
な~さん
領域:目的・学ぶテーマ
課題がしっかりみんなの課題を言語化しておく。言語化できていると違った価値観を持った人が入り込みにくくなる
みんなの目標が一致すると効果が倍増する
KPI数値化できることに着目しすぎてしまうとわくわくがなくなってしまったりする
皆さん、深い洞察をありがとうございます。
コミュニティという掴みどころのないものを運営していく上で、ゆうきさんが挙げてくださったような「アウトカム」や「アウトプット」といった指標を立てることは、進むべき方向を見失わないために非常に重要です。
一方で、kenさんやな~さんがおっしゃるように、数値化できるKPI(重要業績評価指標)ばかりを追いかけることには危険も伴います。参加人数や投稿数といった数字だけを追い求めてしまうと、本来最も大切にすべき「楽しさ」や「ワクワク感」、「メンバー同士の心地よい繋がり」といった、数値化できない価値を取りこぼしてしまう可能性があるからです。
な~さんの「みんなの課題をしっかり言語化しておく」というご意見も、本当にその通りだと思います。
このコミュニティは何を目的としていて、どんなテーマを学ぶ場所なのか。その「領域」が明確であればあるほど、メンバーの目線がそろい、活動の効果は倍増します。
社内勉強会などで、つい「IT勉強会」のような曖昧な名前をつけてしまいがちですが、目的をしっかりと言語化することが、コミュニティの羅針盤になるんですね。
学習コミュニティをつくろう #11: OODAループが超有効な理由と観察の仕方

コミュニティ運営は、計画通りに進むことばかりではありません。むしろ、予期せぬ変化の連続です。そんな変化に俊敏に対応するためのフレームワークとして、僕は「OODA(ウーダ)ループ」が非常に有効だと考えています。
kenさん
OODAループって初めて聞きました。その中でもやはりオブザーブ、観察がとにかく大事
周りと自分を観察する
な~さん
OODAループ
観察
情勢判断
意思決定
行動
==
もともとは戦闘の意思決定の際に用いたフレームワーク
観察
メンバーの状況、やりたいことを観察する。
自分の状況もあわせて観察する。
OODAループは、もともと軍事での意思決定プロセスを分析したもので、「観察(Observe)」「情勢判断(Orient)」「意思決定(Decide)」「行動(Act)」の頭文字をとったものです。
kenさんやな~さんが強調してくださっているように、コミュニティ運営において重要なのが「観察」です。
コミュニティで今、何が起きているのか。メンバーはどんな様子で、何に興味を持っているのか。それを注意深く、見る、聞く、そして「感じる」。あらゆるヒントは、この観察の中に隠されています。
そして面白いのは、観察の対象が「周り」だけでなく「自分」も含まれるという点です。運営している自分自身の気持ちや体調、置かれている状況などを客観的に観察することも、健全なコミュニティ運営には欠かせません。
学習コミュニティをつくろう #12 コミュニティ内外の流れをつかみ、方向づけをしよう
な~さん
情勢判断
コミュニティ内外の流れを感じつつ、これから進む道を判断する
コミュニティ内だけではなく、コミュニティの外の流れも感じて、方針を決める。
観察の次に来るのが「情勢判断」です。な~さんのコメントのように、コミュニティの中だけでなく、世の中の技術トレンドや社会の動きといった「外の流れ」も感じ取り、僕たちの進むべき方向を判断することが重要です。
会社組織の中にいると、どうしても内向きになりがちですが、外に目を向けることで新たな発見がたくさんあります。
学習コミュニティをつくろう #13: OODAループで迅速な意思決定と行動を
な~さん
意思決定
流れに乗った勉強会をしてみる
一部の人しか発言していないから、全員が発表するような会を企画してみる
など
そして、OODAループは迅速な「意思決定」と「行動」につながります。
なにも大げさな意思決定ばかりではありません。「一部の人しか発言していないから、次は全員が発表する形式にしてみよう」といった小さな意思決定と行動をスピーディに繰り返していくこと。
この小さなサイクルの積み重ねが、コミュニティを常に生き生きとした状態に保つ秘訣なのだと僕は思います。
良い学びのコミュニティとは何か
ichihukuさん
学びのコミュニティづくり講座のために聞きなおしました。ペイフォワードってほんと良いシステムだと思います。ペイフォワードがどんどんつながっていくためにはコミュニティをうまく機能させないといけないですよね。そのための仕組みづくり大切だなと思います。
ichihukuさん、ありがとうございます!
ichihukuさんがおっしゃる「ペイフォワード(受けた恩を別の人に送ること)」の循環は、良いコミュニティの証ですよね。
自分が誰かから受けた親切や学びを、また別の人につないでいく。この循環が生まれ始めると、コミュニティは一気に豊かになります。
Payback(恩返し)の関係だけだと、できることが限られてしまいますが、ペイフォワードの考え方を取り入れることで、本当に良い循環が生まれやすくなります。
『すべては1人から始まる』~その取り組みの「ソース」は誰ですか?

最後に、コミュニティの根源的なエネルギーである「ソース原理」という考え方についてです。
古谷さん
放送を聞いてさっそく本を買いました!「イニシアチブ」「クリエイティブフィールド」など初めて聞く言葉なので、今は慣れるのに精一杯ですが、その先になにが書いてあるかワクワクしながら読んでいます!
ichihukuさん
「ソース原理」って初めて聞きました。カタカナ言葉がなかなか頭に入ってこないですが、なんとなく身近な話の言語かな気がします。読んでみようと思います。ちょっと本のタイトルいいですね、勇気出ます。
古谷さん、ichihukuさん、本を手に取ってくださりありがとうございます!
「ソース原理」とは、すべての取り組みは、たった一人(=ソース)の「こうしたい!」というアイデアや直感から始まる、という考え方です。
ichihukuさんがおっしゃるように、本のタイトルもかっこいいんですが、この「勇気」という言葉がポイントだと思っています。
ソースになる人には、周りからどう見られるかを気にせず、リスクを取って一歩踏み出す「勇気」が必要です。しかし、その勇気ある一歩が、やがて周りを巻き込み、大きなクリエイティブな場を生み出していくのです。
おしごと相談室 #16: 「働くの価値を上げる」の作り方
kenさん
ソース=愛だとすると、自分がその愛を育んできた過程を観察、理解することが重要だと思う。その理解なしでは、ソースの熱が伝わりづらいのでは?
kenさん、素晴らしい洞察ですね。
「ソース=愛」、本当にそうかもしれません。自分が何を大切にし、どんな未来を創りたいのか。そのビジョンや価値観を深く自己理解しているからこそ、ソースから湧き出るエネルギーには熱が乗り、人の心を動かすのだと思います。
自分自身を深く知ることが、周りに良い影響を与える第一歩になるんですね。
まとめ
今回は、学びのコミュニティに関する皆さんからのコメントをご紹介しながら、運営のヒントを掘り下げてきました。たくさんの貴重なご意見、本当にありがとうございます。
皆さんのコメント一つひとつが、僕にとっても新たな気づきとなり、コミュニティをより良くしていくための大きなエネルギーになっています。これからも、放送へのご感想やご意見など、気軽にコメントいただけると嬉しいです。
また一緒に、学びを深めていきましょう!
以上、「なぜこの学びのコミュニティは続くのか?OODAループとソース原理の力」についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!


