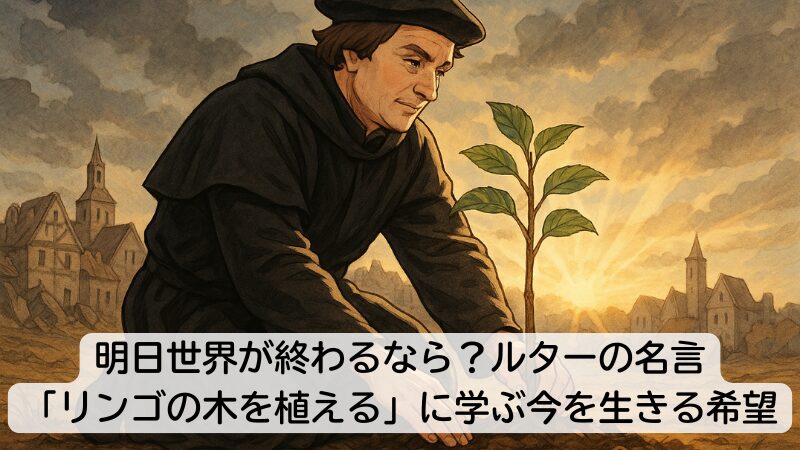
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
もし明日で世界が終わるとしたら、あなたは何をしますか?
宗教改革者マルティン・ルターの力強い言葉から、先の見えない現代を生き抜くためのヒントを探ります。
ということで、今回は「明日世界が終わるなら?ルターの名言「リンゴの木を植える」に学ぶ、今を生きる希望」です。
では、行ってみましょう!
Voicyで名言のリクエストをいただきました!
僕がVoicyで配信している「深掘ってみた名言」シリーズで、嬉しいことに初めてリスナーの方からリクエストをいただきました。大山さん、本当にありがとうございます!
今回はそのリクエストにお応えして、こちらの名言を深掘りしていきたいと思います。
たとえ世界の終末が明日であっても、自分は今日リンゴの木を植える。/マルティン・ルター
この言葉、どこかで耳にしたことがある方も多いかもしれませんね。
一体どのような背景から生まれ、私たちに何を語りかけてくれるのでしょうか。一緒に見ていきましょう。
名言の主、マルティン・ルターとは?
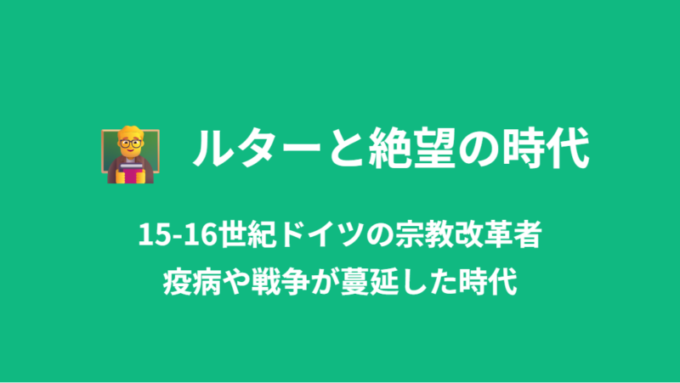
まず、この言葉を遺したマルティン・ルターという人物について簡単にご紹介しますね。
彼は15世紀から16世紀にかけて、神聖ローマ帝国(現在のドイツ)で活躍した人物です。
神学者であり、牧師であり、そして何よりも「宗教改革者」として歴史にその名を刻んでいます。
彼の行動が、キリスト教の歴史を大きく二分するほどの大きなうねりを生み出したんですね。
名言が生まれた、絶望の時代背景
ルターが生きた15世紀から16世紀のヨーロッパは、決して穏やかな時代ではありませんでした。
ペストなどの疫病が猛威をふるい、戦争が絶えず、飢饉も頻繁に起こる。人々は常に死と隣り合わせの、非常に不安定な社会を生きていたんです。
そうした状況から、多くの人々が「世界の終わり」を本気で意識していました。
「明日、世界が終わってしまうかもしれない」。そんな終末思想が、社会全体を暗く覆っていたわけです。
人々の不安につけ込んだカトリック教会
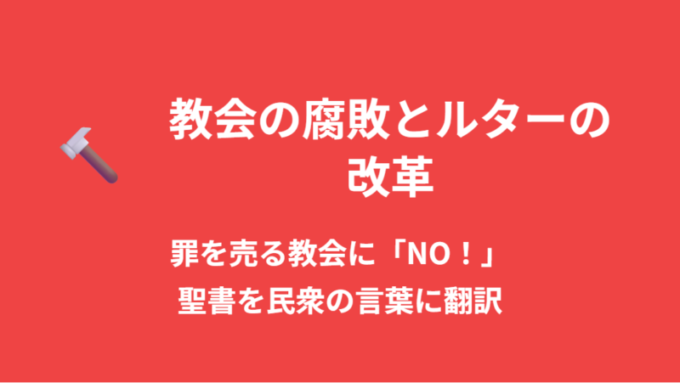
当時、人々の精神に絶大な影響力を持っていたのがカトリック教会でした。しかし、その教会もまた、人々の「世界の終わりへの恐怖」を巧みに利用し、権力を維持しようとしていた側面があったんですね。
その象徴的な例が「免罪符(めんざいふ)」です。
これは、教会が発行する証明書のようなもので、「これを買えば、あなたの犯した罪が許され、天国へ行くことができますよ」という触れ込みで、人々にお金で販売されていました。
明日世界が終わるかもしれないと本気で怯えている人々は、藁にもすがる思いでこの免罪符を買い求めます。
教会は、人々の純粋な信仰心を悪用して、資金集めを行っていたというわけです。
さらに、当時の聖書は非常に難しいラテン語の原典しかなく、読むことができるのは一部の聖職者だけでした。
一般の民衆は、教会が「聖書にはこう書いてあります」と語る言葉を、そのまま信じるしかなかったのです。
この情報の非対称性が、教会の腐敗に拍車をかけていました。
「それは違う!」と立ち上がったルター
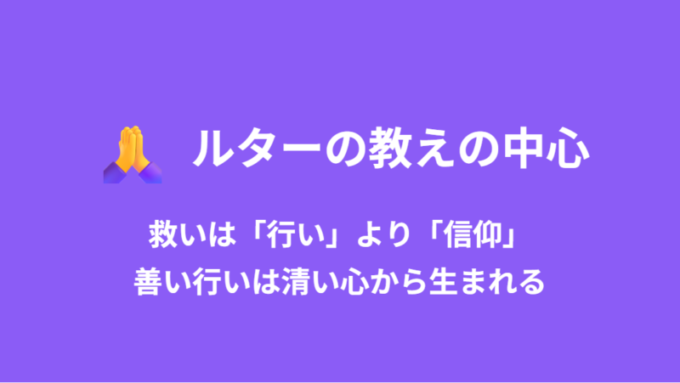
そんな状況に「待った」をかけたのが、今回の主役であるマルティン・ルターでした。
彼自身も神学者であり牧師でしたが、聖書を深く読み込む中で、「今、カトリック教会がやっていることは、聖書の教えとは全く違うじゃないか!」と強い疑問を抱くようになります。
そして1517年、彼はその怒りと疑問を「95箇条の論題」として発表します。
これは、先ほどお話しした免罪符の販売をはじめとする、教会の腐敗を真正面から厳しく批判する内容でした。そのすべての批判の根拠は、彼が深く読み込んだ「聖書」そのものにありました。
さらにルターは、これまで聖職者しか読めなかったラテン語の聖書を、一般民衆が使うドイツ語に翻訳するという事業を成し遂げます。
これにより、誰もが自分の言葉で聖書を読み、神の教えに直接触れることができるようになりました。もう、教会の言うことを鵜呑みにする必要はなくなったのです。
この一連のルターの行動が、宗教改革の大きな引き金となり、ローマ・カトリック教会から「プロテスタント」が分離・誕生するという、キリスト教世界の歴史的な大分岐へとつながっていきました。
ルターの教えの中心「信仰義認説」
ルターの思想の中心には「信仰義認説(しんこうぎにんせつ)」という考え方があります。少し難しい言葉ですが、これが今回の名言を理解する上でとても重要になります。
当時のカトリック教会は、「良い行いをすることで、人は救われる」と教えていました。この考え方が行き過ぎてしまった結果が、「お金で罪の許しを買う」という免罪符のような腐敗につながったわけです。
それに対してルターは、「人は、行いによってではなく、ただ信仰によってのみ義とされ、救われるのだ」と唱えました。
これが「信仰義認説」です。
つまり、何かをしたか・しないか、結果を出したか・出していないか、ということではなく、神を信じる「心」そのものが、人を救いへと導くのだ、という考え方なんですね。
「じゃあ、心で信じてさえいれば、実際の行動はどうでもいいの?」と思ってしまいますよね。
しかし、ルターはこうも言っています。
「本当に神を信じ、救われているのであれば、その人からは自然と良い行動が生まれてくるはずだ」と。
つまり、清らかな心があれば、その人の行動もまた、清らかなものになるでしょう、ということです。
「リンゴの木を植える」ことの本当の意味
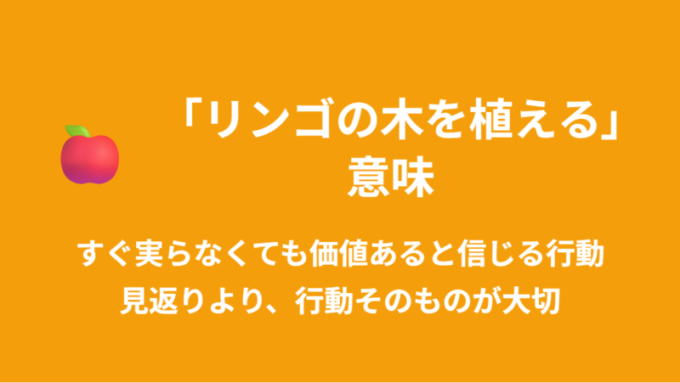
さて、ここまでの話を踏まえて、もう一度、今回の名言を見てみましょう。
たとえ世界の終末が明日であっても、自分は今日リンゴの木を植える。
この「リンゴの木を植える」という行為は、一つのメタファー(比喩)です。
リンゴの木は、植えてすぐに実がなるわけではありませんよね。何年もかけて水をやり、育てて、ようやく果実を実らせます。つまり、「すぐには結果が出ないけれど、価値があると信じる行動」の象徴なのです。
ルターが伝えたかったのは、こういうことではないでしょうか。
「たとえ明日、世界が終わってしまい、植えたリンゴが実るのを見ることができなくても、関係ない。僕たちにとって大切なのは、結果や見返りではない。神を信じる心、そしてその心から自然に生まれる、愛と希望に満ちた行動(=リンゴの木を植えること)そのものに価値があるのだから」と。
信じる心があれば、たとえ世界の終わりが明日だったとしても、今日やるべきことは変わらない。ただ淡々と、自分にとって価値のある行動をとるだけだ。そんな力強いメッセージが込められているわけですね。
現代を生きる私たちへのメッセージ
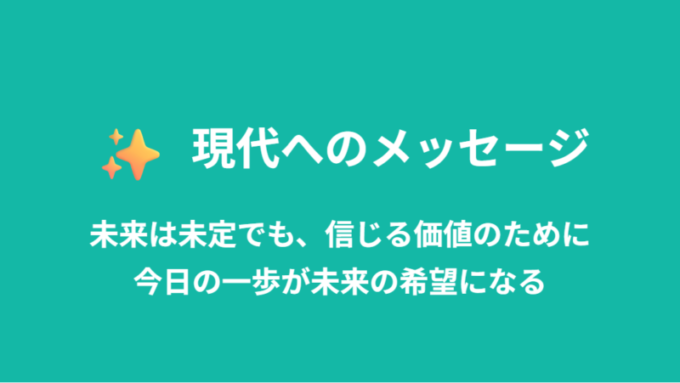
僕らの多くは、ルターのように神や聖書を熱心に信じているわけではないかもしれません。しかし、この名言から学べることは、現代を生きる私たちにとっても非常に大きいと感じます。
この言葉が持つ本質的な意味は、「たとえ未来がどれだけ絶望的に見えても、自分にとって『これは大事だ』『これには価値がある』と心から思えるものを見つけ、それを信じよう」ということではないでしょうか。
皆さんにとって、心から信じていることは何でしょうか。
その「信じるもの」が、日々の行動に一本の芯を通してくれるようになるのだと思います。
実はこれ、僕が以前このシリーズで紹介した、マーガレット・サッチャーの有名な名言とも深くつながっているんです。
思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。
言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。
行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。
習慣に気をつけなさい、それはいつか人格になるから。
人格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。
この最初の「思考」という言葉には、ルターの言う「信じる心」に近い意味合いが込められています。
心から信じるものが、あなたの言葉や行動、そして最終的には運命さえも形作っていく。二人の偉人が、時代を超えて同じ本質を語っているようで、調べていてとても面白く感じました。
まとめ
今回は、マルティン・ルターの名言「たとえ世界の終末が明日であっても、自分は今日リンゴの木を植える」を深掘りしてみました。
先の見えない不安な時代だからこそ、私たちはつい目先の結果や見返りを求めてしまいがちです。しかし、そんな時代だからこそ、ルターの言葉は一層深く胸に響きます。
未来がどうなるか分からなくても、自分自身の内なる声に耳を澄まし、信じる価値のために今日できる一歩を踏み出す。その一つ一つの行動こそが、未来を形作る「リンゴの木」になるのかもしれませんね。
以上、「明日世界が終わるなら?ルターの名言「リンゴの木を植える」に学ぶ、今を生きる希望」についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!

