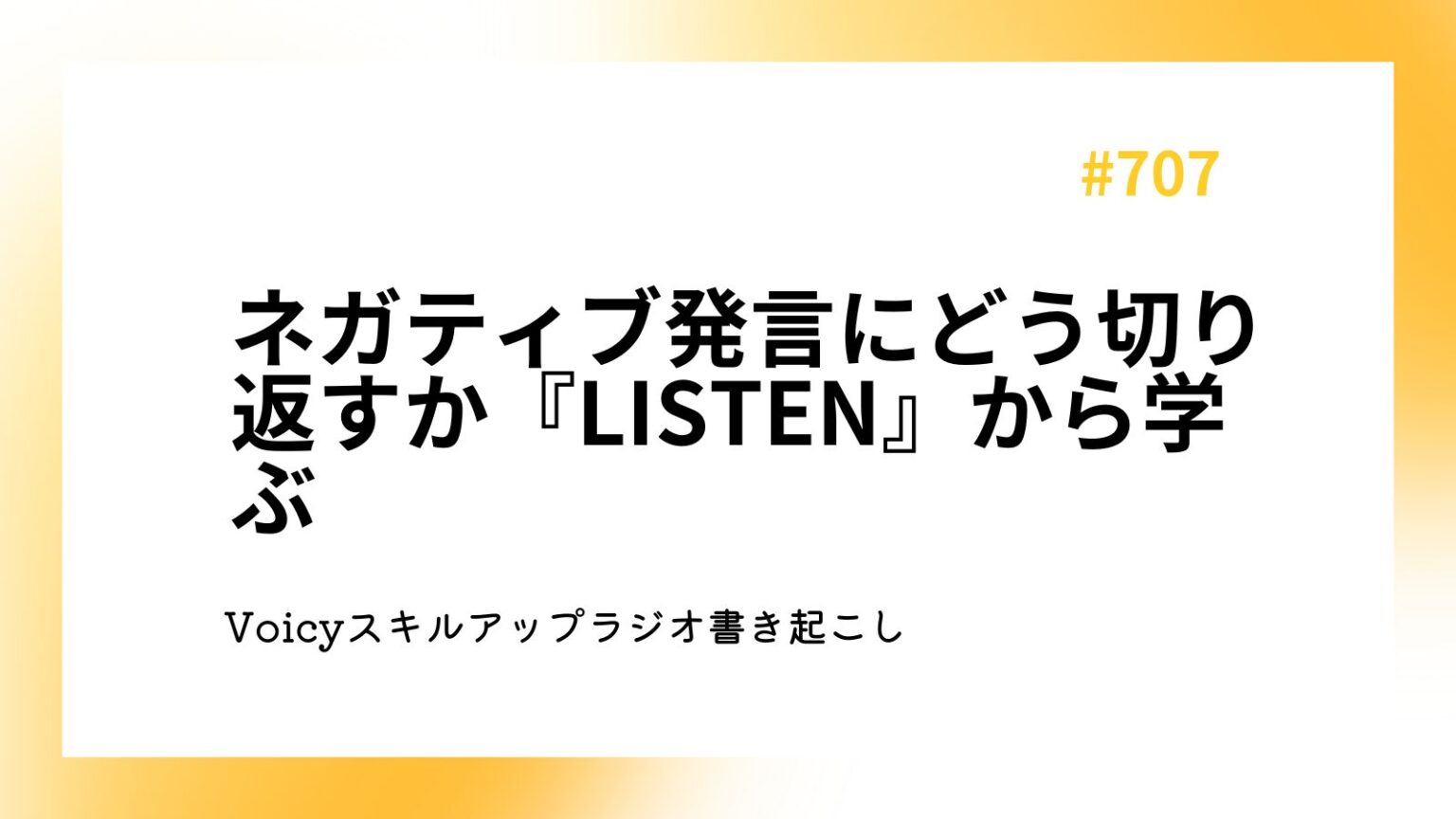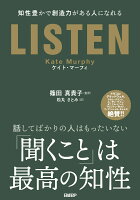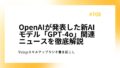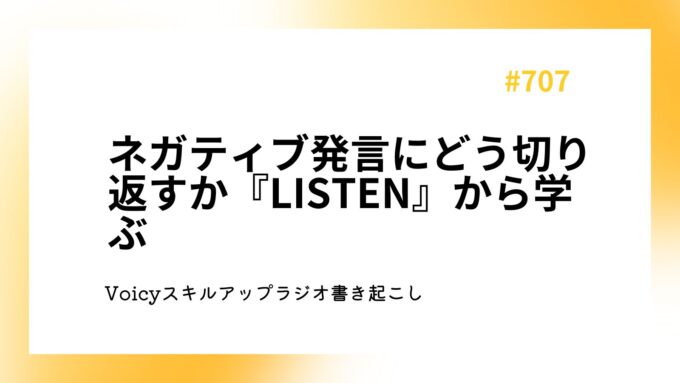
みなさん、おはようございます!タカハシ(@ntakahashi0505)です。
こちらの記事は、タカハシが音声メディアVoicyの「スキルアップラジオ」にて放送した内容から、ピックアップしてお届けします!
今回のテーマは、ネガティブ発言にどう切り返すか『LISTEN』から学ぶです。
なお、以下で実際にお聴きいただくこともできます!
では、よろしくお願いいたします!
職場やプライベートでネガティブな発言を聞くとき
よくあるネガティブ発言の例
職場やプライベートでネガティブな発言を聞いてしまう。
そんな状況はよくあるものです。
仕事が面白くないとか、理不尽な目に遭った、給料はなんでこんなに安いんだとか。そんな不平や不満があります。
もしくは、自分なんかどうせ無理だとかこんな仕事うまくいくわけがないと、そういった自信や自己肯定感の欠如もネガティブな発言に繋がります。
他人への不満や批判
さらに、あの人本当に気に食わないとか、あいつは本当に仕事ができないやつだとか、そういったネガティブ発言もよく耳にしてしまうかもしれません。
そういった言葉は聞くだけでもモチベーションを下げられたりとか、イライラさせられたりとか、あまり気持ちのいいものではありません。さらに、それに切り返そうとしたら、相手をもっと落ち込ませたり、怒らせたりしてしまう。
自分の切り返しによって、より状況が悪化してしまう。そういったこともあるので、とても難しいなと感じます。
このテーマで考える時に、以前読んだ書籍『LISTEN』がいくつかのヒントを与えてくれていたなということを思い出したので、今日はその話をしていきたいなと思っています。
ネガティブな発言への対処法
ネガティブなやり取りに関する2つの調査
まず、書籍の中で紹介されていたネガティブなやり取りに関する2つの調査を紹介していきたいと思います。
まずは、ミネソタ大学とイリノイ大学の調査です。
どんなことかというと、職場でのネガティブなやり取りで腹を立てた気分は、ポジティブなやり取りをした時の幸せな気分の5倍の強さに感じられたということでした。
もう1つ、ワシントン大学の研究によると、ポジティブなやりとりの回数がネガティブなやり取りの5倍以上なくてはいけない。このような報告をしています。
つまり、ネガティブなやり取りや発言、その強さは増幅しやすくて、そしてその回数は増殖しやすいということなんです。
誰もがネガティブな発言に触れていたくない、このように思うはずなんですが、なぜかたくさん聞いてしまう、なぜか心に残ってしまう、そういった理由がここにあるなと思います。
したがって、ネガティブな発言、これはよくよく意識して増幅しないようにし、他の人に伝播しないようにする。強い意志を持って立ち向かわなければいけない、このように思うわけです。
6つの衝動を抑える
では、どうするかという話なんですが、書籍の中では、今からあげるような衝動、これを抑えなさい。このように伝えているんです。
6つありますので、そのような行動を取っていないのか確認しながら聞いてください。
- どんな気持ちか自分にも理解できるという問題の原因を突き止める。
- その問題についてどうすべきか言う。
- 相手の心配事を矮小化する。
- 無理やりポジティブ視点や陳腐な言葉を使って違う見方をさせようとする。
- 相手の強さを称賛する。
さて、いかがだったでしょうか。
この6つを読んだ時、僕は全部やっているなと思いました。
しかし、本書ではこれらのような問題を解決してあげようとか、安心させよう、そして話を終わらせよう。このようなタイプのずらす対応、これは避けないといけないと伝えています。
相手の問題解決能力を信用するか
ここで、ある研究が紹介されていました。
ヴァンダービルト大学の研究なんですが、子供がパターン認識の問題の解き方を説明している間、母親がただ耳を傾けていると、問題解決能力は著しく向上する。このように伝えています。
よく、子供が何かに取り組んでいると、手を出してしまったりとか、口を出してしまったりとか、そういった衝動にかられます。そして、実際に口や手が出てしまいます。
しかし、本書ではそのことをしないようにと伝えています。
なぜなら、その口や手を出すということは、あなただけでこの問題を解決するのは無理。そういったメッセージを送るということになってしまうからということなんです。
この研究は、子供に対して親が手を出す、口を出すということに関するものなんですが、これは大人同士でも同じことが言えるわけです。
その問題の解決を試みる、そのために何かを言う、何かをしてあげる、そういうふうに思うということは、相手の問題解決能力を信用していないという行為だからです。
自分の感情をひとまず置いてただ耳を傾ける
では、どうすればいいのか。本書はこのように伝えています。
最善策は、自分の感情をひとまず置いて、ただ耳を傾けること。
何に直面しているか理解し、その感覚を感じ取ること。解決策はその人の中にあるということなんです。
じっと耳を傾けて、その人が自分自身で解決することを信じる。そして、待つということなんです。
近接コミュニケーションバイアス
しかし、これは言うは易しですが、かなり難しいと感じるかもしれません。しかも、これは間柄が親しいほど難しくなるということも言われています。
これは、心理学者ジュディス・コシェが近接コミュニケーションバイアスという言葉で説明しています。
つまり、近接相手に近いほど、相手を知っている。わかっていると思い込んでしまうということがあるです。
いつも共に働いているチームメンバー上司は部下のこと、部下は上司のことよくわかっている。そのように感じているかもしれません。
さらに、配偶者や親子であるのであれば、より一層そのように感じていることが多いんじゃないかなと思います。したがって、より近しい人ほど、きちんと相手の話を聞こう。そのような姿勢を持たないといけないということなんです。
ネガティブな発言をずっと聞かされるとき
さて、自分の感情を置いておいて、ただ耳を傾ける、この方法が良いということなんですが、ただネガティブな発言をずっと聞かされてしまう、そういったこともあるわけです。
ネガティブな発言をいくら聞いても自分は平気でいられるわけではありません。
誰しも感情がありますから、どうしても嫌な気持ちやストレスがたまってしまう、そういったこともあります。
本書では、その課題についてこのように伝えています。
すべての人の話を聞き続けなければいけないわけではない
誰からでも何かしらか学べるが、だからといって全ての人の話を聞き続けなければいけないわけではない。
コミュニケーションとは、お互いの協力で成り立つもの。
1日の時間は限られています。
時間をかける相手を選ぶことができるということなんです。ネガティブな発言を聞くということには、どうしても労力を使います。
今は聞けないという判断も大切
その労力を使う知的・精神的な元気がないなら、今は聞けないという判断もダメではないということです。
ということで、『LISTEN』からのヒント、いかがだったでしょうか。ネガティブな発言に関しては、自分の感情をひとまず置いて、ただ耳を傾ける。
しかし、元気が十分にないのであれば、今は聞けない。
そういった判断もOKということです。
ぜひご参考いただければと思います。
まとめ
ということで、今日はVoicy「スキルアップラジオ」の放送から「ネガティブ発言にどう切り返すか『LISTEN』から学ぶ」をお届けしました。
タカハシのVoicyの放送はこちらからお聴きいただけます。
チャンネルのフォロー、コメント、SNSでのシェアなどなど、楽しみにお待ちしております。
では、また。