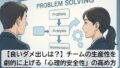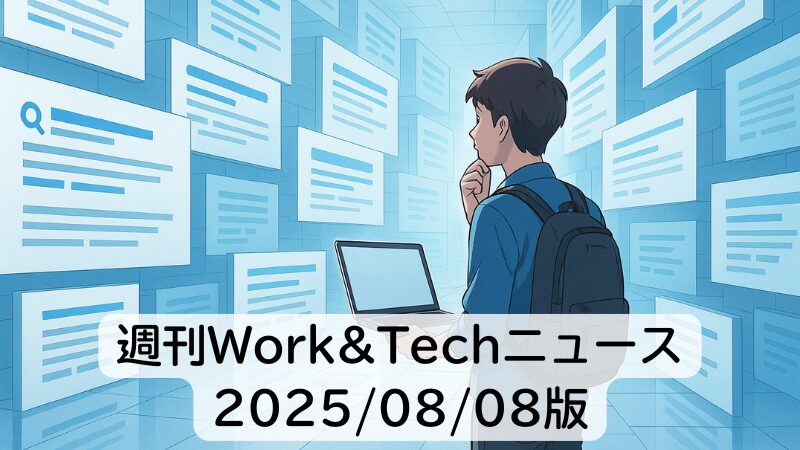
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
「週刊Work&Techニュース」 2025/08/08版をお送りします!
今週のワークとテックの主なニュースをざっとチェックし時流をつかんでいただくことができますよ。
では、行ってみましょう!
ChatGPTの「嘘」を信じてレポートを書く学生たち–生成AIのハルシネーションが教育現場を直撃
大学などの教育現場で、生成AI・ChatGPTが作り出す「もっともらしい嘘」をそのまま信じてレポートとして提出する学生が増えています。
AIが提示した実在しない記事や著作名を根拠に挙げたり、リンク切れの出典をそのまま記載するケースが見られます。
実際、学生の約4分の1はAIをレポート作成に利用しているという調査結果もあり、教育現場ではAIによる誤情報「ハルシネーション」への警鐘が鳴らされています。

「ハルシネーション」とは、AIが事実とは異なる情報を、あたかも本当の情報であるかのように生成してしまう現象のことです。AIは、膨大なデータから次に来る言葉を予測して文章を作っているため、その内容が本当に正しいかどうかを判断する機能は持っていません。
そのため、AIが生成した文章には、存在しない文献や誤った情報がレポートに含まれてしまう危険性があるのですね。
私たち利用者は、AIの回答をそのまま信じるのではなく、それが本当に正しい情報なのかを必ず自分で確認する、いわゆる「ファクトチェック」の必要性がますます高まっています。
実際に、ある大学では生成AIの特性を理解させるために、このようなレポート課題が出されています。
「情報リテラシーの講義で学んだ範囲から、まだ解決できていないテーマを選び、まずChatGPTに回答を作成させます。その上で、ChatGPTの回答に対する自分の考えをレポートにまとめてください。その際、ChatGPTが出力しなかった考えや、反対意見を必ず一つ以上含めること。また、その根拠となる出典(URLや記事名など)も明確に示してください」
このように、AIを賢く使いこなすための教育も始まっているというわけです。
キリン、経営会議に「AI役員」同席–過去10年の議事録学習 「想像より凄い」とネットで話題
キリンホールディングスは、AI役員「CoreMate」を経営戦略会議に本格導入したと発表しました。
過去10年分の取締役会や経営戦略会議の議事録データ、社内資料、外部の最新情報を学習した12のAI人格が、会議で議論すべき論点や意見を提示します。
これにより会議の質やスピード向上が期待され、年間30回以上の会議で活用される予定です。ネットでは「人間より多様性がある」「想像より本格的」など話題となっています。

今回導入されたAI役員「CoreMate」は、キリングループが掲げるデジタル活用戦略「KIRIN Digital Vision2035」の一環として開発されました。
AI役員を導入する大きな目的は、経営の質とスピードを向上させることです。
具体的には、会議の担当者が事前にAI役員と議題について議論することで、多様な経営視点を取り入れた資料を効率的に作成できるようになります。これにより、会議の準備時間が短縮され、経営層や担当者がより本質的な価値創造活動に時間を使えるようになることが期待されています。
さらに、AI役員は過去の経営情報だけでなく、外部の最新専門知識も継続的に学習します。AIは感情や先入観に左右されず、データに基づいた客観的な提案ができるため、人間だけでは気づきにくい視点から意見を出すことができます。これにより、変化の激しい事業環境にも迅速に対応できる、質の高い意思決定を促進していくとのことです。
今後は、取締役会や他の事業会社にも順次この仕組みを広げていく予定で、経営判断の新しいサポート役として大きな期待が寄せられています。
OpenAI、ChatGPT利用者7億人に 前年比4倍に増加
アメリカのAI企業OpenAIは4日、対話型生成AI「ChatGPT」の週間利用者数が7億人を超える見通しだと発表しました。
これは、今年3月末の5億人からわずか4か月で2億人増加したことになり、前年と比べると4倍の成長です。
ChatGPTは仕事や学習など多様な目的で世界中の人々に活用されており、今後もさらなる利用拡大が予想されています。
ChatGPTの利用者は驚異的なスピードで増え続けていますね。2022年11月の公開から、わずか5日で100万ユーザーを突破し、世界的なAIブームの火付け役となりました。
週間利用者7億人のうち、有料で利用しているユーザーは全体の約2〜3%と見られており、個人向けの「Plus」や法人向けの「Enterprise」「Team」といったプランを合わせると、1,000万人から2,000万人が有料で活用している計算になります。特に企業での導入が急速に進んでおり、ビジネス利用の有料契約者数は500万人を突破したとのことです。
この利用者増加の背景には、ChatGPT自体の機能が向上し、利用シーンが広がっていることがあります。
例えば、テキストだけでなく画像や音声にも対応した新しいモデルの導入や、教育現場、企業での本格的な活用が進んでいることが大きな要因と考えられます。
ちなみに、競合であるGoogleの「Gemini」も、2025年の中頃には月間アクティブユーザー数が4億人を超えたと見られており、生成AI市場全体の成長が続いていることがうかがえます。
Google DeepMind、リアルタイムで世界を生成するAI「Genie 3」発表 “AGIへの足がかり”
Google傘下のDeepMindが、テキスト入力からリアルタイムで操作可能な多様な3D世界を生成できるAI「Genie 3」を発表しました。
Genie 3は、言葉ひとつでゲームのような仮想空間を自動的に作り、ユーザーの動きや指示に応じて即座に反応します。
生成された世界は高解像度で、一貫性やリアリズムも向上。今後、AIの基礎研究だけでなく、ゲームや教育、ロボット訓練など幅広い分野で応用が期待されています。
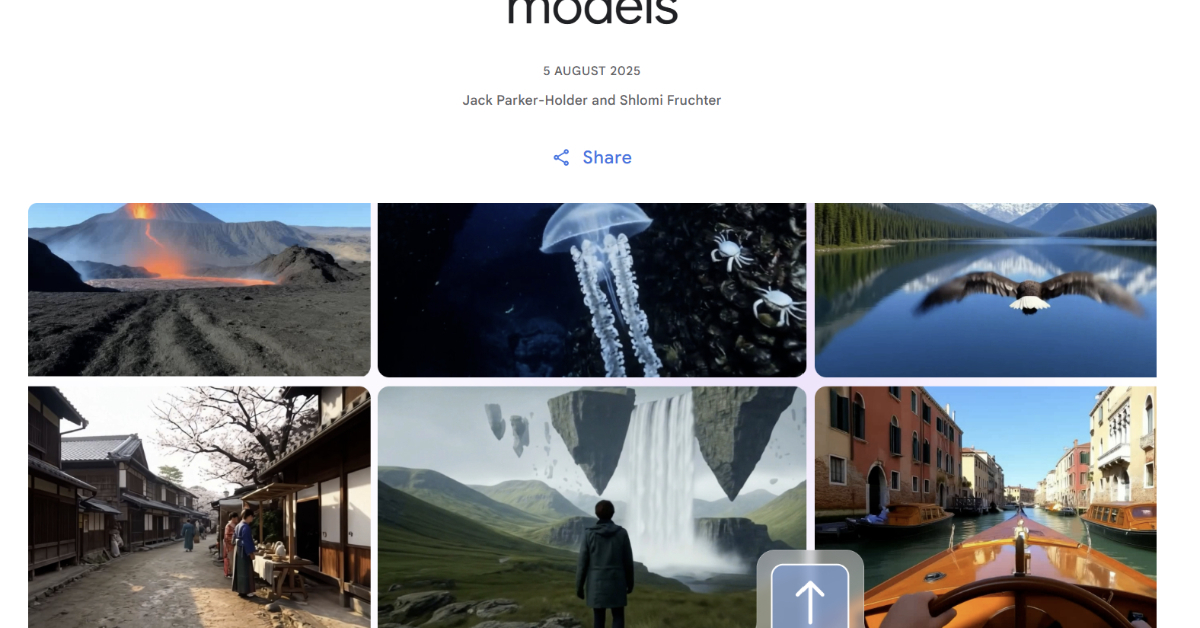
今回発表された「Genie 3」は、これまでのAIが得意としてきた画像や動画の生成からさらに一歩進んで、ユーザーが自由に歩き回ったり、物事を変化させたりできる「動的な世界」そのものを創り出すのが大きな特徴です。
具体的には、生成された世界は720pの解像度で、1秒間に24フレームという滑らかさで動作します。
さらに「ワールドメモリ」という機能を備えており、物体の状態や場所を記憶し、何分間も一貫したリアルな動きを保つことができるそうです。ユーザーが世界を探索するのに合わせて、AIがその動きや指示にリアルタイムで反応し、環境を生成し続けてくれるというわけですね。
こうした技術は、AIが現実世界の物理法則などを自ら学び、仮想空間で試行錯誤するための基盤となります。
様々な環境に柔軟に対応できる、人間のように汎用的な知能を持つ「AGI(汎用人工知能)」の実現に向けた、非常に大きな一歩と言えるでしょう。
OpenAI、オープンなAIモデル「gpt-oss」発表 性能は“o4-mini”に匹敵 軽量版含む2種類を公開
OpenAIは8月5日、最新のオープンウェイトAIモデル「gpt-oss」を発表しました。
公開されたのは、大型の「gpt-oss-120b」と軽量の「gpt-oss-20b」の2種類で、どちらも誰でも無料で利用できるApache 2.0ライセンスです。
gpt-oss-120bは、従来のクローズドモデル「o4-mini」とほぼ同等の性能を持ちながら、1台の80GB GPUで動作します。
軽量版の20bは、16GBメモリのPCやモバイル端末でも搭載可能で、日常的な用途に幅広く対応します。
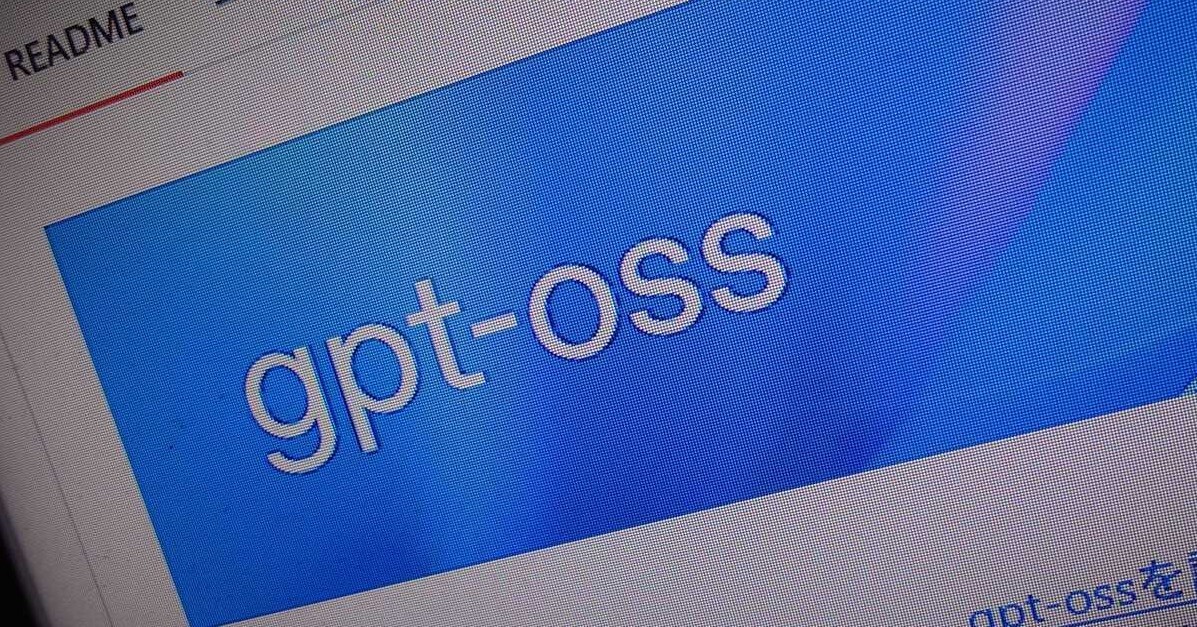
「オープンウェイトモデル」というのは、AIの頭脳の一部である「重み(ウェイト)」というデータを一般に公開する仕組みのことです。
これにより、開発者や企業はAIを自分で動かしたり、特定の目的に合わせてカスタマイズしたりすることが自由にできるようになります。
これまで自社モデルを限定的に公開してきたOpenAIにとって、今回の発表は2019年の「GPT-2」以来、実に5年ぶりとなる本格的な公開型AIモデルの提供となり、大きな方針転換と言えます。
誰もが自由に使えるようになったことで、新しいサービスやアプリケーションの開発が一層加速しそうですね。
特に注目されているのが、軽量版の「gpt-oss-20b」です。このモデルは、一般的なパソコンやスマートフォンでも動かせるほど手軽なため、AIの活用が専門家だけでなく、より多くの人々に広がるきっかけになると期待されています。
背景には、Meta社の「Llama」シリーズやGoogle社の「Gemma」シリーズといった、他社によるオープンソースAIの台頭があります。これを受け、OpenAIもこれまでの「クローズド戦略」だけでなく、開発者コミュニティと協力していく「協調路線」も取り入れていく戦略のようです。
まとめ
以上、「週刊Work&Techニュース」 2025/08/08版についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!