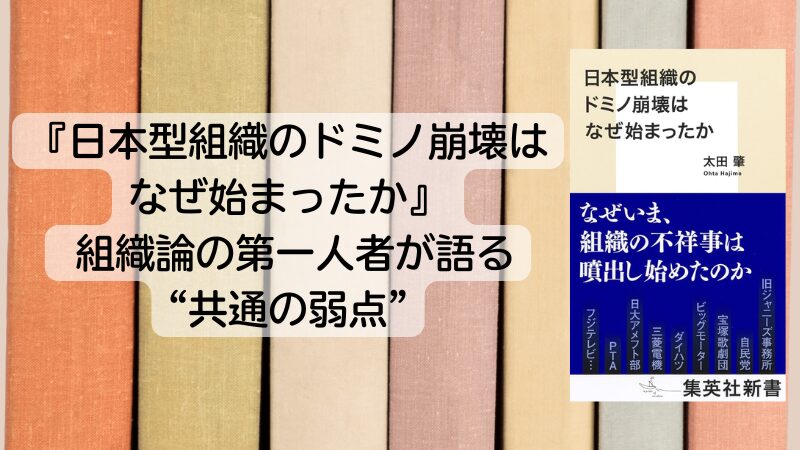
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
最近、大企業の不祥事や組織ぐるみの問題が次々と明るみに出ていますね。
なぜ今、このようなことが立て続けに起こるのでしょうか?
今回は、その謎に迫る一冊、太田肇さんの『日本型組織のドミノ崩壊はなぜ始まったか』をご紹介します。
ということで、今回は「『日本型組織のドミノ崩壊はなぜ始まったか』~ 組織論の第一人者が語る“共通の弱点”」です。
では、行ってみましょう!
注目の一冊!『日本型組織のドミノ崩壊はなぜ始まったか』をご紹介
さて、今回ご紹介する本はこちらです。
このタイトル、かなりインパクトがあります…!
なぜ今、巨大組織の崩壊が相次ぐのか?
旧ジャニーズ事務所の問題、ダイハツやビッグモーター、三菱電機や東芝といった企業の不祥事、さらには自民党の派閥解体、そして最近ではフジテレビの事例など、ここ最近立て続けに巨大組織で事件が起きています。
ここで本書は、「なぜ今になって巨大組織が崩壊するような出来事が立て続けに発生したのか」という疑問からスタートします。そして、これらの問題の裏には、「日本の組織に共通する決定的な弱点」が潜んでいると指摘します。
その弱点を鋭くあぶり出し、そして、ただ問題点を指摘するだけでなく、現代社会に合った組織の「新生」、つまり新しい組織のあり方を提言する、非常に示唆に富んだ一冊となっています。
著者は組織論の第一人者、太田肇さん
著者の太田肇先生は、経済学博士であり、同志社大学政策学部の教授でいらっしゃいます。組織論や日本人論の第一人者として知られ、これまでに約40冊もの著作を発表されています。
個人的に、とくに日本の組織については大いに興味がある分野なので、他の書籍も拝見したく思いました。
本書の構成:4つの章で解き明かす崩壊のメカニズムと再生への道
この本は、大きく4つの章で構成されています。
第1章:2023年 崩れ始めた支配構造
まず第1章では、近年、特に2023年あたりから顕著になってきた組織の「支配構造」の崩壊について分析しています。崩れ始めた支配構造を大きく3つのタイプに分類しています。
- 絶対君主型: カリスマ的なリーダーが絶対的な権力を持つ組織。
- 官僚制型: ルールや規則でがんじがらめになり、形式主義や前例踏襲が蔓延してしまう組織。
- 伝統墨守型: 古くからの慣習や「しきたり」が重視され、新しい考え方や外部からの意見が受け入れられにくい組織。
これらのタイプは一見すると異なるように見えますが、その崩壊の原因には共通して「共同体」というキーワードが隠されていると指摘します。
この「共同体」というのが、本書を読み解く上で非常に重要な概念になってきます。
第2章:共同体が物言わぬ集団に
かつて、日本の組織、例えば日本的経営と言われるものは、終身雇用や年功序列といったシステムの中で、従業員の会社への忠誠心や一体感を生み出し、高度経済成長を支える原動力ともなりました。ある意味、世界からも模範的と見られていた時期もあったわけです。
しかし、時代は変わりました。デジタル化が進み、社会全体の価値観も変化してきました。
そんな中で、組織が崩壊するようになってきた…その裏側には、事件に直接関与していない組織の構成員たちの変化があるということを明らかにします。
第3章:身近な組織に迫る危機
3章では、これまで見てきたような組織の崩壊は、なにもニュースで見るような大企業や巨大な組織だけの問題ではないと警鐘を鳴らします。
僕たちが普段関わっている、もっと身近な組織、例えば中小企業、学校、PTA、町内会、さらには家庭といった小さな集団の中にも、同じような「崩壊のリスク」は潜んでいるというのです。
我々読者は、対岸の火事を見ていたつもりが、一気に「自分ごと化」を迫られることになります。
第4章:組織の「再生」ではなく「新生」を
そして最後の第4章では、これまでに見てきたようなリスクを回避し、組織を健全な状態にしていくために、私たちはどうすれば良いのか、具体的な処方箋が示されます。
その鍵となるのが、第1章から繰り返し登場してきた「共同体」からの脱却、そして「コミュニティ」への移行である、と提言されています。
『日本型組織のドミノ崩壊はなぜ始まったか』の見どころ
大企業だけの話じゃない!日本のあらゆる「組織」の問題
まず、感じたのは「日本の組織」と捉えるスコープの広さです。
普通、会社組織について論じるときって、どうしてもその「会社」という枠の中で話が進みがちですよね。でも、この本は違います。
企業だけでなく、学校、PTA、町内会、さらには家庭まで含めた、日本のあらゆるタイプの集団、つまり「組織」全体を共通のテーマとして扱っているんです。
大企業だけを語るなら「自分には関係ない」となりますが、学校、町内会、家庭なども含めるなら、必ずどれかに所属しているといってよいわけで…そのリアルな組織の所属や関わりの体験とつなげることで、本書の問いの渦中に引き込まれることになります。
弱点の正体は「共同体」?美しく言語化された気づき
そして、日本の組織が共通して持っている「決定的な弱点」について。
僕もこれまでの経験の中で、なんとなく「日本の組織って、こういうところが息苦しいよな」「もっと風通しが良ければいいのに」と感じていた、その「何か」の正体を、この本は見事に言語化してくれたと感じています。
その弱点の正体こそが、先ほどから何度も出てきている「共同体」的な機能が悪さをしている、という指摘です。
長年のモヤモヤが晴れたような気持ちになりました。
処方箋は「コミュニティ」への移行 – ノンプロ研との繋がりも?
一方で、その問題に対する処方箋として示されている「組織を新生する方法」、つまり「共同体」をよりオープンで自律的な「コミュニティ」にしていく、という考え方。これもまた、非常に示唆に富んでいました。
この「コミュニティ」というキーワード。まさに、僕が運営している「ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会」がそうだと感じました。
この本を読んだことで、会社組織からコミュニティへという一貫した流れを通して、新たな視点や気づきを得ることができ、個人的にも非常にエキサイティングな読書体験となりました。
まとめと今後の展望
本書の中で論じられているポイントについては、まだまだ深掘りしたい点がたくさんあります。
これらの点については、また改めて、別の機会にお話しできればと思っています。
皆さんもご自身の周りの組織に照らし合わせて本書を手に取って読んでみてくださいね。
以上、「『日本型組織のドミノ崩壊はなぜ始まったか』~ 組織論の第一人者が語る“共通の弱点”」についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!


