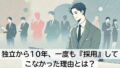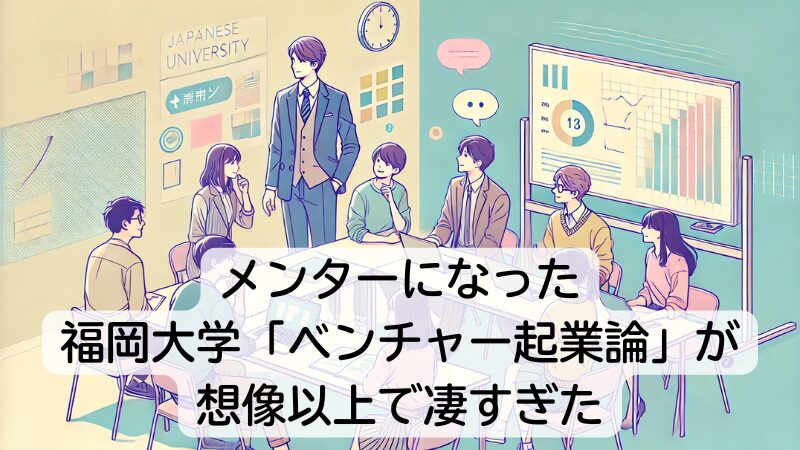
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
福岡大学の名物講義「ベンチャー起業論」のメンターに就任しました~!
プロジェクト型で学生が主体的に新規事業を創出する、その熱意と仕組みの凄さに感動。
今回は、僕が体験した初回の講義の様子や、この取り組みの魅力をたっぷりお伝えします。
ということで、今回は「メンターになった福岡大学「ベンチャー起業論」が想像以上で凄すぎた」です。
では、行ってみましょう!
福岡大学の名物講義「ベンチャー起業論」とは?
この度、福岡大学の「ベンチャー起業論」という講義で、メンターを務めさせていただくことになりました!
この「ベンチャー起業論」、普通の講義とは一線を画す、ユニークで実践的な内容が特徴です。
一般的な大学の講義は、前期・後期で授業を受け、レポートを提出したりテストを受けたりして単位を取得する形式が多いですよね。
しかし、この「ベンチャー起業論」は、それとは大きく異なります。
基本は「講義+プロジェクト活動」という構成です。
プロジェクト活動が中心に据えられていて、そのプロジェクトを成功させるために必要な知識や考え方を講義で学ぶという、実践を通じて学ぶことを重視したカリキュラムとなっています。
豪華な講師陣による講義
この素晴らしい講義の担当教授は、岡祐輔さんです。岡先生は、元々は糸島市役所で「スーパー公務員」として名を馳せた方で、現在は福岡大学でその情熱を教育に注いでおられます。以前「ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会(ノンプロ研)」にもいらっしゃいましたね。
講義には、岡先生に加えて、様々な分野で活躍されている方々が多数登壇されます。
ビジネスモデルの構築方法、事業計画書の書き方、チームで成果を出すための対話、プレゼンテーションスキルなど、新規事業開発に不可欠な実践的スキルを、その道のプロフェッショナルから直接学ぶことができるのです。
リアルの企業と連携!超実践的なプロジェクト
プロジェクト活動のほうは、履修している学生(なんと約100名!)が10のグループに分かれ、実在する企業と連携します。
そして、新たな価値創造につながるような新規事業を、学生たちが自ら考え出し、提案し、さらには実行まで目指すという、非常にチャレンジングな内容になっています。
リアルなビジネス体験が学びの場となっている…超実践的でワクワクしますよね。
1年間の挑戦:プロジェクトのスケジュール
このプロジェクトは、1年という長いスパンでじっくりと取り組まれます。そのスケジュールも、なかなかに本格的です。
- 4月15日: 最初の講義が行われ、プロジェクトが実質的にスタートします。顔合わせやガイダンスが主な内容でした。
- 4月中: 学生たちが自ら話し合いながら、10のプロジェクトチームを組成します。
- 5月まで: 各チームがどの企業と連携してプロジェクトを進めるか、マッチングが行われます。
- 5月以降: いよいよプロジェクト活動が本格化。チームで企業を訪問したり、担当者とディスカッションを重ねたりしながら、新規事業のアイデアを具体化し、実現可能性を探っていきます。
- 10月: 学内で開催されるビジネスコンテストで、これまでの活動の成果を発表します。
- 12月: 学外に開かれた交流ビジネスコンテストで、10月の発表からさらにブラッシュアップした事業計画を発表します。
これだけの活動を1年間かけて行うのですから、その密度は相当なもの…この講義は通年で8単位分にもなるそうです。
僕の学生時代にこんな授業があったら…福大の学生さんたちがめちゃくちゃうらやましいです。
学生主体の運営体制:執行部と各課の役割
さて、ここまでのお話で、「100人もの学生が10個のプロジェクトを動かし、企業とも連携して、ビジネスコンテストまで運営するなんて、先生一人でできるの?」と疑問に思った方もいらっしゃるかもしれません。
岡先生お一人では、到底回せる規模ではありません。
この「ベンチャー起業論」のもう一つのすごいところがありまして、実は、この授業全体の運営そのものも、学生たちが主体となって組織的に行われています。
まず中心となるのが「執行部」と呼ばれる組織です。代表と副代表を含む5名の学生さんで構成され、講義に関する事柄を決めたり、各組織に指示や連絡をしたりします。まさに、この講義の司令塔のような存在です。
そして、この執行部の下には、4つの「課」と、先ほど紹介した10個のプロジェクトチームが存在するという、しっかりとした組織構造になっています。
例えば、ビジネスコンテストなどのイベント企画・運営を担当する「運営課」や、この講義の活動内容や成果を学内外に広く知らせるための「広報宣伝課」といった部署があるそうです。
さらに、各プロジェクトチームには、チームをまとめるリーダーと、それを補佐する副リーダーがいます。
つまり、履修している約100名の学生のうち、20〜30名ほどは、自分たちのプロジェクトを進めるだけでなく、この「ベンチャー起業論」という大きな枠組みを円滑に運営するための役割も担っているということになります。
そして、これらの執行部、各課のメンバー、プロジェクトリーダー・副リーダーといった役割は、すべて学生たちが自発的に担っているという点です。
誰かに指示されたからやるのではなく、「自分たちがこの取り組み良くしたい」「この役割に挑戦してみたい」という意志を持った学生たちが、主体的にこの大きな仕組みを動かしています。
この規模でありながら、参加者全員が高い熱量を保ち続けられるのは、役割をもって参加する学生主体の運営体制が非常にうまく機能しているからなのでしょう。
実務家メンターとして学生をサポート
次に、今回担当させていただくことになった「メンター」という役割についてお話しします。
今年度は、僕を含めて16名の方がメンターを務められるそうです。その顔ぶれも実に多様で、20代の若手起業家から、なんと80代の経験豊富な経営者まで、様々な分野の第一線で活躍されている実務家の方々が集結しています。
僕たちメンターの主な役割は、各プロジェクトチームに1〜2名ずつ配置され、学生たちの良き相談相手となることです。
これまでのビジネス現場で培ってきた経験や知識を活かし、彼らの挑戦を側面からサポートしていく、そんな存在です。
初回の講義で感じたこと:学生たちの熱意と主体性
先日、4月15日に開催された初回の講義に参加させていただきました。
岡先生のガイダンスからはじまり、執行部や各課のリーダーを務める学生さん、僕たちメンター、そしてこれから各プロジェクトのリーダーや副リーダーとしてチームを引っ張っていく学生さんたちが集まり、それぞれ自己紹介や今後の抱負などを語り合いました。
特に僕が興味深いと感じたのは、各プロジェクトグループによるPRタイムです。
この時点ではまだメンバーがリーダーと副リーダーしか決まっていないため、「私たちのグループはこんな価値観を大切にして活動したい!」「こんな強みや想いを持った人にぜひ仲間になってほしい!」といった、彼ら・彼女らの自己紹介にはメンバー募集のアピールも含まれていました。
つまり、どのグループがどの企業と連携するか決まっていない段階ですから、グループの決定は「誰とするか」、リーダーや副リーダーの人柄、考え方、そしてグループが目指す方向性や雰囲気などによって、最初のチーム作りが進んでいくというプロセスです。
このチームビルディングによって、人やチームを見る目をやしなう機会になるというのがとても面白いと感じました。
驚きと感動:学生たちの主体性と成長意欲
さて、この初回の講義に参加して、僕は大きく心を動かされた点が二つあります。
一つ目は、参加している学生さんたちの「主体性」と「発信力」です。
役割を担っている中心は2年生や3年生ですが、皆さん本当に自分の考えを自分の言葉で、臆することなく堂々と話そうとしている姿が印象的でした。
誰かに言われたからやっているという「やらされ感」はまったく感じられず、自らこの講義に積極的に関わり、何かを学び取り、成し遂げようという意志が伝わってきました。
少し想像してみてください。
もし皆さんの職場で、突然「今日から部署横断で10個のグループを作り、新規事業を立案・提案・実行してください。まずは各グループのリーダーに立候補し、自分のチームの方針と求めるメンバー像についてプレゼンしてください」と言われたら、すぐに手を挙げて行動できるでしょうか?
それを、大学生たちがごく自然に、臆することなく実践していました。
中には、この「ベンチャー起業論」を昨年も履修した経験のある学生さんもいました。
たとえば、「昨年はプロジェクトのメンバーとして参加したので、今年はリーダーという役割に挑戦して、チームを引っ張る経験を積みたい」と語っていました。
このように、主体的に参加し、率先して物事を前に進めようとする姿勢、そして挑戦から純粋に学びを得ようとする意欲が、この授業の良い文化として毎年きちんと受け継がれているのだなと、深く感心しました。
多様な人々が交差する学びの場:越境学習の可能性
もう一つ、僕が深く感銘を受けたのは、この講義に関わる人々の「多様性」です。
- 学生: 約100名(そのうち、運営側の役割も担う学生が20〜30名)
- 講師陣: 岡先生をはじめとする、各分野の専門家や実務家の方々
- 協力企業: プロジェクトで連携する企業10社
- メンター: 僕を含め16名の多様なバックグラウンドを持つ実務家
これだけでも相当な多様性ですが、さらに、ビジネスコンテストでは、学内外から1000人規模のオーディエンスが集まるそうです。
学生たちの学びと成長を中心に置きながら、企業、実務家、教員、他の学生たち…といった多様な人々が互いに影響を与え合い、刺激し合う。
まさに、それぞれの境界線を越えて学び合う「越境学習」と「被越境学習」が、ここではダイナミックに展開されています。
そして、それが単発のイベントではなく、毎年メンバーを入れ替えながら、毎年継続的に実施される「仕組み」として機能している。
これは本当に、とてつもなく価値のある、すごいことだと思います。正直、感動すら覚えました。
他の大学も、ぜひこの福岡大学の取り組みを参考にして、どんどん真似してほしいと心から願っています。
未来への期待:糸島市100人カイギへの展開&別ミッションも
さて、この素晴らしい福岡大学「ベンチャー起業論」、早くも様々な方面への広がりを見せ始めています。
実は、僕が運営を務めさせていただいている「糸島市100人カイギ」という地域交流イベントがあるのですが、4/18の開催日にベンチャー起業論に参加している学生さんに登壇していただくことが決まりました!
100人カイギに新たな風が吹くのではないかと、とてもワクワクしています。
そして実は…僕はこの「ベンチャー起業論」において、メンター以外にもう一つ、別の重要なミッションを担わせていただくことになっています。
この件も、とてもおもしろい取り組みになっていまして、また改めて別の機会にご紹介できればと思っています。楽しみにしていてください!
まとめ
というわけで、今回は僕がメンターとして関わることになった福岡大学「ベンチャー起業論」について、その驚くべき仕組みと魅力、そして僕が初回の講義で感じた感動と期待をお伝えさせていただきました。
学生たちの熱意と、それを最大限に引き出す素晴らしい教育プログラムに、僕自身もすでに多くの刺激と学びを得ています。
これから1年間、学生さんたちと一緒に挑戦し、成長をしていきたいと思います!
以上、「メンターになった福岡大学「ベンチャー起業論」が想像以上で凄すぎた」についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!