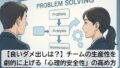みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
タスクの優先順位付けに役立つ「アイゼンハワーマトリクス」。
今回はその基本的な使い方に加え、僕自身が実践している、つい後回しにしがちな「重要だけど緊急でないこと」を進めるための、一歩進んだ活用法をお話しします。
ということで、今回は「アイゼンハワーマトリクスを使いこなす!タスクに追われる毎日から抜け出す一歩進んだ時間管理術」です。
では、行ってみましょう!
そもそもアイゼンハワーマトリクスとは?
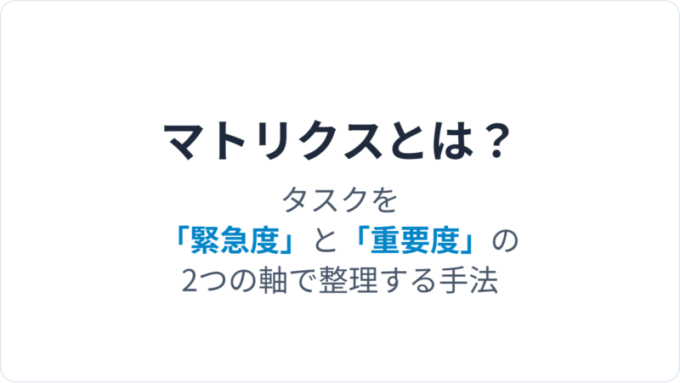
さて、皆さんは日々のタスク管理、どうされていますか?
「やることが多すぎて、何から手をつければいいか分からない!」なんて状態に陥ることもありますよね。そんな時に役立つのが「アイゼンハワーマトリクス」というフレームワークです。
これは、アメリカの第34代大統領であるドワイト・D・アイゼンハワーが用いていたとされる時間管理術がもとになっています。
彼は軍の要職を歴任する中で、膨大なタスクと難しい決断に日々直面していました。そこで、「緊急度」と「重要度」という2つの軸でタスクを整理し、優先順位をつけていたのです。
この考え方が世界的に有名になったのは、経営コンサルタントのスティーブン・R・コヴィーが、名著『7つの習慣』の中で「時間管理のマトリックス」として紹介したことが大きなきっかけです。
ちなみに、アイゼンハワー自身の言葉として有名な「私の持つ問題には2種類ある。緊急のものと重要なものだ。緊急なものは重要ではないし、重要なものは決して緊急ではない」という名言は、実はノースウェスタン大学のジェームズ・ロスコー・ミラー総長の発言がもとになっているそうです。ちょっとした豆知識ですね。
具体的には、タスクを以下の4つの領域に分類して整理します。
4つの領域でタスクを分類する

アイゼンハワーマトリクスでは、タスクを「緊急かどうか」と「重要かどうか」の2つの軸で分け、4つの象限に分類します。
第1領域:緊急かつ重要 (Do)
これは「今すぐやるべきこと」です。
例えば、締め切りが迫ったプロジェクト、クライアントからの急なトラブル報告への対応などが当てはまります。誰が見ても、すぐに対応が必要だと分かるタスクですね。
第2領域:重要だが緊急ではない (Schedule)
ここが実は、あなたの将来を創るための最も大切な領域です。「長期的な目標達成に必要なタスク」がここに含まれます。
例えば、新しいスキルを学ぶための自己啓発、事業の将来を見据えた戦略立案、健康のための運動習慣などです。
緊急性がないため、ついつい後回しにされがちなのが悩ましいところです。
第3領域:緊急だが重要ではない (Delegate)
これは「自分じゃなくてもできること」です。
電話の取次ぎや、定型的な事務作業など、一見すると急ぎで対応が必要そうに見えても、あなたの目標達成には直接つながらないタスクが分類されます。
可能であれば、他の人やコンピューターなどの道具にお願い(Delegate)するのが賢明です。
第4領域:緊急でも重要でもない (Delete)
最後は「やる必要のないこと」です。
目的のないネットサーフィン、参加しても意味のない会議、なんとなく続けているだけの惰性的な活動などがこれにあたります。思い切ってやめる(Delete)ことで、大切な時間を確保できます。
「重要でない」を撲滅したあとのタスク管理術
さて、皆さんはこの4つの領域、どのように埋まっていますか?
僕自身の話をすると、第3領域(緊急だが重要ではない)と第4領域(緊急でも重要でもない)は、かなり意識して撲滅できています。
もちろん、日々の業務の中で細々したタスクは発生しますが、それらは一瞬で終わらせるか、そもそも「やらない」と決めたり、やらなくて済む仕組みを作ったりしています。
最近で言うと、消費税の納税や法人の役員重任の手続きといった、やらなければいけないけれど定型的な作業は、さっと済ませました。
その結果、僕のタスクリストはほとんどが「重要エリア」、つまり第1領域と第2領域のタスクで占められています。あとは、その中で「緊急性が高いか、そうでないか」という違いだけです。
「後回し」を防ぐ秘訣は「締め切り」を決めること
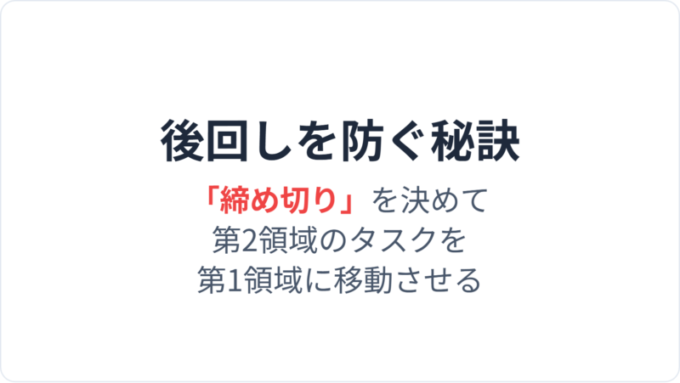
ここで問題になるのが、先ほども触れた第2領域「重要だが緊急ではない」タスクへのアプローチです。
自己投資や新しい企画の準備など、将来のために大切なことほど、目の前の緊急タスクに追われて後回しになりがちですよね。
僕がこの問題に対して実践している、とてもシンプルで強力な方法があります。それは、「自分で締め切りを決めてしまう」ことです。
締め切りを設定した瞬間、そのタスクは「重要だけど緊急ではない」第2領域から、「重要かつ緊急」な第1領域へと移動します。つまり、意図的に緊急度をMAXまで引き上げるのです。
例えば、このVoicyでの毎日の放送もそうです。
情報発信は、長い目で見れば集客やリスナーとの関係構築につながり、僕自身の学びや思考の整理にもなる、非常に重要な活動です。しかし、今日やらなくても誰にも怒られない、緊急性の低いタスクでもあります。
もし「いつかやろう」と思っていたら、きっとズルズルと後回しになっていたでしょう。でも、僕は「毎日朝6時に放送する」と決めています。
こうすることで、毎日必ず締め切りがやってくる「緊急度MAX」のタスクになるわけです。
イベントドリブンで自分を追い込む(笑)
この「締め切り設定術」は、他のことにも応用しています。
新しい講座やイベントを企画するときも、「完璧な中身ができてから告知しよう」と考えると、いつまで経っても始まりません。だから先に「○月○日に開催します!」と宣言してしまう。
最近始めた「生成AI講座」や「学びのコミュニティづくり講座」も、開催日という締め切りが先に決まりました(というか、決めました)。
それに合わせてコンテンツを準備することで、形にすることができたのです。
ノンプログラマー向けのコミュニティ「ノンプロキャンプ」も、まさにそうやって始まりました。日程と会場が決まれば、物事は一気に動き出します。
ちょうどこのところ、複数の企業研修と大学院での非常勤講師の集中講義が重なっていて、正直なところ、かなりしびれるスケジュールになっています(笑)。
「さすがにこれはやり過ぎたかな…」と反省することもありますが、こうやって自分を良い意味で追い込むことで、重要なことを確実に前に進めることができています。
もしあなたが、「大事なことほど後回しにしてしまう…」と悩んでいるなら、ぜひこの「自分で締め切りを決める」という方法を試してみてください。少し勇気がいるかもしれませんが、きっとあなたの行動を力強く後押ししてくれるはずです。
まとめ
以上、「アイゼンハワーマトリクスを使いこなす!タスクに追われる毎日から抜け出す一歩進んだ時間管理術」についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!