
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
学びのコミュニティへの参加を迷っていませんか?
この記事では、Voicyに寄せられたリアルな声をもとに、コミュニティがもたらす価値や、運営を成功に導くヒントを、皆さんと一緒に考えていきます。
ということで、今回は「学びのコミュニティの多大な意義とは?Voicyに寄せられた声から探る、学びと成長のヒント」です。
では、行ってみましょう!
- #177 学習コミュニティを活用するその多大なる意義とは
- #197 働くの価値は上がらないと気づいてから越境学習にたどり着くまで
- #331 コミュニティ発展の5段階から見るノンプロ研の現在地
- #465 書評「コミュニティ・オブ・プラクティス」その1: 今実践コミュニティを学ぶ意義とは
- #466 書評「コミュニティ・オブ・プラクティス」その2: 知識と情報の違いは何か
- #467 書評「コミュニティ・オブ・プラクティス」その3: 実践コミュニティの3つの構成要素とは
- #468 書評「コミュニティ・オブ・プラクティス」その4: 実践コミュニティの7つの設計原則
- まとめ:たくさんのコメント、ありがとうございました!
#177 学習コミュニティを活用するその多大なる意義とは
古谷さん
今まで学習コミュニティに入ったことがありませんでした。したがってノンプロ研に入るとき、かなり迷いました。しかし「はじめてのコミュニティ活用講座」に出会ったおかげで、一歩踏み出すことができました。期待以上にすばらしい講座です。本当にありがとうございます😊
こちらこそ、本当にありがとうございます!古谷さんのように、初めてコミュニティに参加するときは、誰でも不安や迷いがありますよね。その一歩を後押しできたこと、とても嬉しく思います。
この放送で紹介した「はじめてのコミュニティ活用講座」は、ノンプロ研に入られた皆さん全員にご紹介している講座です。コミュニティでどう行動すればいいか、講師のレクチャーを受けながら学び、実践に移すことができます。
そして、この講座は8月から新シーズンがスタートするのですが、なんと講師は古谷さんに担当いただくことになりました!
講座で一歩を踏み出した方が、今度は次の人の一歩を後押しする側になる。これぞコミュニティの素晴らしい循環だなと感じています。古谷さん、どうぞよろしくお願いします!
#197 働くの価値は上がらないと気づいてから越境学習にたどり着くまで
古谷さん
みんなが生き生きと働ける世界を作ろうとしているのが伝わってきました!
はい、ありがとうございます!この回では、僕が直面した課題についてお話ししました。
以前は、ノンプログラマーの皆さんにスキルを身につけていただくため、教材開発や講座開催に注力していました。しかし、個人がスキルアップしても、それを受け入れる会社の組織が変わらなければ、せっかくのスキルを活かせないという現実に気づいたんです。
「みんなが生き生きと働ける世界」のためには、個人の支援だけでなく、組織自体を変えていくアプローチが必要です。
これは本当に難しい課題で、この放送から2年経った今も、あの手この手で試行錯誤を続けています。
#331 コミュニティ発展の5段階から見るノンプロ研の現在地
古谷さん
2023年のリスキリングブーム、あの時「今が勝負だ!」っていう気持ちが伝わってきました!
この放送では、『コミュニティ・オブ・プラクティス』という書籍で紹介されている「コミュニティ発展の5段階」と、ノンプロ研の歩みを照らし合わせてお話ししました。
2023年はリスキリングという言葉が大きな注目を集め、僕たちにとっても「今が勝負だ!」という思いで活動していましたね。
ただ、正直なところ、このブーム以降の2年間は、決して明るい成果が出たわけではなく、今でも暗中模索であの手この手でトライしているというところです。
#465 書評「コミュニティ・オブ・プラクティス」その1: 今実践コミュニティを学ぶ意義とは
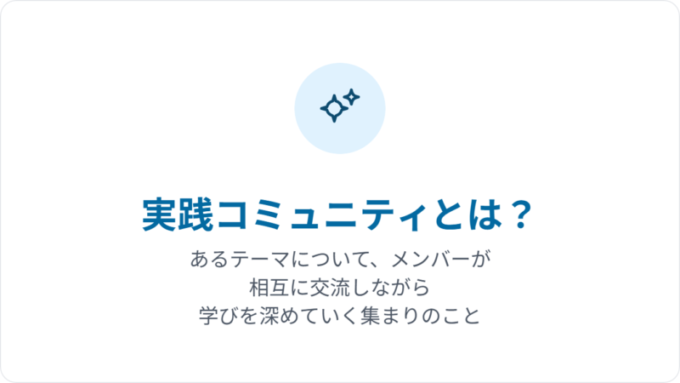
ichihukuさん
コミュニティづくり講座開始に伴い視聴しました。ノンプロ研内ではよく聞く「実践コミュニティ」という言葉、すごく好きなんですよね。なんだかいつもやる気が出ます。私はコロナ過以降にこの言葉を知りましたが、20年以上前に書かれた本に出てきているということは、言葉は知らずとも「実践コミュニティ」の形としては存在していたということなんですね。
素晴らしい洞察ですね、ありがとうございます!
おっしゃる通り、「実践コミュニティ」という言葉自体は比較的新しいかもしれませんが、その概念は、人類の歴史とともにあったと言ってもいいかもしれません。
あるテーマに関して相互に交流しながら学び合う集まり、それが実践コミュニティです。
例えば、農耕時代に「もっと効率の良い農作業の仕方をみんなで考えよう」という集まりがあったとしたら、それは立派な実践コミュニティです。
昔からある人々の営みに名前がつき、現代の僕たちが活用できるように概念化されたものなんですよね。
#466 書評「コミュニティ・オブ・プラクティス」その2: 知識と情報の違いは何か
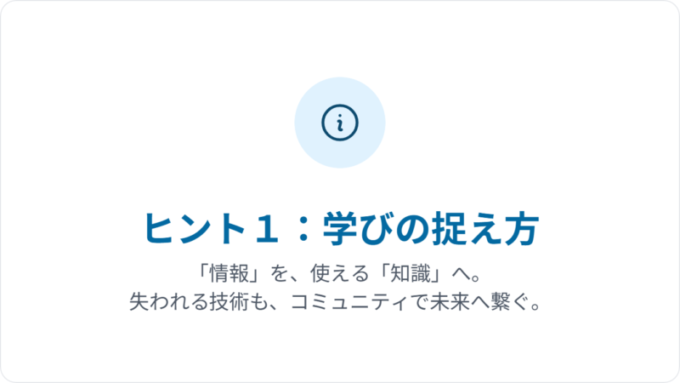
ichihukuさん
コミュニティづくり講座参加で実践コミュニティ関連のVoicy聞きなおしています。「知識と情報の違い」納得です。例えば私のAIの知識はまだ「情報」の段階で、「知識」とはなっていないんだなと思います。ただ、以前は「情報」もなかなか入ってこなかったのが、ノンプロ研に参加しているおかげで徐々に「情報」から「知識」へ変換できる環境があるので、それはとても良かったなと思っています。
「情報」と「知識」の違い、的確に捉えていただき嬉しいです。
簡単に言うと、「知識」とは、人の中に存在していて、いつでも使える状態になっているものですね。
ノンプロ研のような実践コミュニティの良いところは、個人の経験を知識に変えるだけでなく、その「知識」をメンバー間で共有できる点にあるんです。
ichihukuさんがAIの「情報」を「知識」に変えていくプロセスを、コミュニティとして応援できるのは素晴らしいことだと思います。
古谷さん
大工さんの話、とても興味深かったです。僕も建築現場で働いていますが、これまで現場で身につけてきたちょっとした技術は、その会社がもし潰れてしまったら無くなってしまうので、もったいないなと感じました。
ありがとうございます。まさに、実践コミュニティの価値はそこにあります。
個人が持つ「ちょっとした技術」、いわゆる暗黙知も、コミュニティで共有すれば、個人の記憶や所属する会社という枠を超えて生き続けることができます。
会社がもしなくなったとしても、実践コミュニティさえ残っていれば、貴重な技術や知識は未来へ繋がっていく。そう考えると、コミュニティの可能性は無限大ですよね。
#467 書評「コミュニティ・オブ・プラクティス」その3: 実践コミュニティの3つの構成要素とは
ichihukuさん
友人たちと歌うサークルを立ち上げています。40名声かけて全員が参加してはじまったのですが、実際に練習しているのはほぼ半数で、少しずつ改善しながら運営しています。当初は作業が集中してほんとしんどかったです。意見をとりいれても実行する人はいるわけで、試行錯誤の毎日ですね。
非常に興味深い事例をありがとうございます。
どんなにうまくいっているコミュニティでも、課題は必ずありますし、運営は試行錯誤の連続ですよね。特に、一部の人に作業が集中してしまうのは「あるある」です。
こういった理論をうまく活用しながら、少しずつ良い活動にしていく、そのプロセス自体がコミュニティ運営の醍醐味なのかもしれません。
#468 書評「コミュニティ・オブ・プラクティス」その4: 実践コミュニティの7つの設計原則
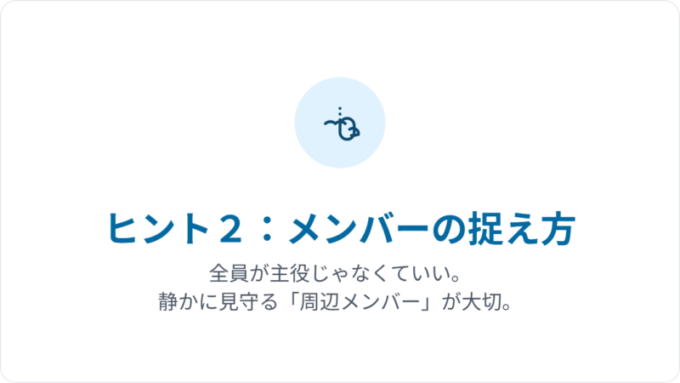
ichihukuさん
歌のサークルを運営していますが、すごく参考になりました。40名のメンバーの内、半数程度しか練習に参加していないのですが、参加できないメンバーもグループLINEは読んでいそう。「周辺メンバー」という概念がすっかり抜けていました。この放送もう1回聞き直したいと思います。サークル運営にも使えそうなアイデアありそうです。
そうなんです。「周辺メンバー」という存在はとても重要です。
運営側としては、どうしても全員に活発な「コアメンバー」でいてほしいと願ってしまいがちですが、実践コミュニティは自発的な参加が基本。
参加の度合いはメンバー自身が決めるものです。半数くらいが活発でなくても、それはごく自然なこと。「そういうものだ」と捉えるだけで、運営者の気持ちも楽になりますよね。
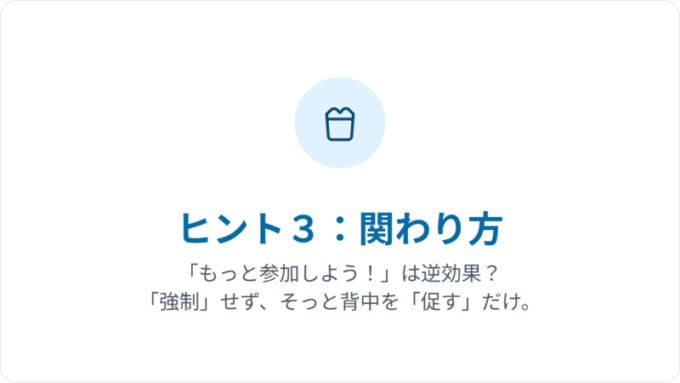
な~さん
ichihukuさんのコメントが印象的なので聞いてみた🦻
さまざまなレベルの参加を奨励するみんなに強く参加を求めてしまいがちだな・・・と思った。強く求めれられて、参加できないと、どんどん足が遠のきますよね。
重要なご指摘、ありがとうございます。まさに、その通りですね。
良かれと思って「もっと参加しようよ!」と強く働きかけると、かえって相手を遠ざけてしまうことがあります。
大切なのは、いつでも参加できる「機会」があることを伝え続けること。そして、誰かが「ちょっと一歩踏み出してみようかな」と思ったその瞬間を逃さず、そっと背中を押してあげること。
この絶妙な「促し方」ができると、コミュニティはもっと心地よい場所になるはずです。
まとめ:たくさんのコメント、ありがとうございました!
今回は、Voicyに寄せられたたくさんのコメントをご紹介させていただきました。
たくさんのコメント、本当にありがとうございました!また次回のコメント返し大会も、楽しみにお待ちいただければと思います。
以上、「学びのコミュニティの多大な意義とは?Voicyに寄せられた声から探る、学びと成長のヒント」についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!


