
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
ひょんなきっかけから、僕の息⼦(小学校3年生)がノンプロ研に⼊会することになりました。
やってみてどうだったか、そして、子どもの可能性を広げるための得られた気づきについてお話しします。
ということで、今回は「小3の息子が大人の学び場「ノンプロ研」に入会!子どもの可能性を狭めていたのは大人だったと気づいた話」です。
では、行ってみましょう!
子どもを社会から切り離してしまってはいないか?
皆さん、「ここは⼤⼈の場所だから」という理由で、⼦どもを無意識のうちに社会から切り離してしまっていることって、結構あるんじゃないかなって思うんです。
でも、そうやって⼤⼈と⼦どもを切り離してしまうことが、本当に良いことなんだろうか…と最近感じることがありました。
今日は、僕が主宰する大人の学びのコミュニティ「ノンプロ研」で実際に起こった、一つのエピソードをお伝えできればと思います。
それは、僕の⼩学3年⽣の息⼦がノンプロ研に⼊会してみた、というお話です。
きっかけはオフラインイベントへの参加
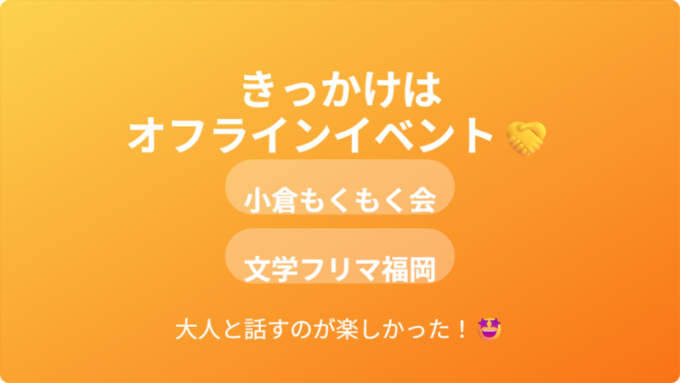
なぜ、そんな流れになったのか。
ここ最近、僕が住む福岡でノンプロ研のオフライン活動がいくつかありました。一つは小倉で開催したオフラインのもくもく会。そしてもう一つが、先週博多で開催された文学フリマ福岡です。
ノンプロ研の正式名称は、「ノンプログラマーのためのスキルアップ研究会」。
大人が学び合うコミュニティなので、基本的にはメンバーは大人しかいません。
ですが、今回は都合により、上記2つのイベントに息子を連れて行かざるを得なくなったんですね。
幸い、うちの息子は大人と会話することに物怖じしないタイプで、むしろ好きな方でした。それに、イベント中に騒いだりせずにうまくやってくれるだろう、という信頼もあったので、何とかなるかな、と。
そして当日、ノンプロ研の皆さんは、息子のことを本当に温かく迎え入れてくれました。それが本人もすごく嬉しかったようで、どちらのイベントでも、その後の懇親会まで参加して、大人の皆さんとごく普通に話をして楽しんでいたようです。
大人が学ぶ姿を間近で見るということ
そんな息子の姿を見て、僕はふと、こういった⼤⼈が自発的に学んだり、好きなことに打ち込んだりする環境に⼦どもが参加するのは、教育としてすごく良いことなんじゃないかな、と感じました。
「ここは⼦どもが来るべき場所じゃないから」と最初から切り離してしまうのではなく、⼀⼈の⼈間として⼀緒に楽しんだり学んだりしよう、と受け入れる。
そうすることで、⼦どももすごく喜んでくれるし、そこから多くのことを学んでくれる。そんな姿を、息子は見せてくれたように思います。
オフラインイベントを通じて、息子の中で「ノンプロ研、なんだか面白そうだな」という熱が、だいぶ上がってきたのを感じていました。
その時、僕の中に一つのアイデアが浮かんだんです。
「いっそのこと、この子をノンプロ研に入会させちゃおうか」と。
家族会員制度で、いざ入会!
ノンプロ研には「ファミプロ」という、月に一度、家族や子どもたちも一緒に参加できるイベントがあります。
ただ、それ以外の通常のイベントに参加したり、メンバーが交流するSlackに子どもたちが入ったりすることは、これまでしてこなかったんですね。
でも、ノンプロ研にいるのは、変な大人は一人もいなくて、むしろ素敵な方ばかりです。それに、親である僕が基本的には見守っていられる。きっと、大丈夫だろう。
そう思い、ノンプロ研の「アイデア会議」というSlackチャンネルに、「試しに息子を入会させてみたいのですが…」と投げてみたところ、皆さんから「ぜひぜひ!」「ウェルカム!」という温かい反応をいただきました。
そこで、満を持して行動に移すことにしました。
ノンプロ研には、これまであまり使われていなかった「家族会員」という制度がひっそりと存在します。
通常は⽉々5,500円でご参加いただいているのですが、どなたかが会員として⼊会されている場合、そのご家族は⽉々3,300円で⼊れる、という制度です。
もともとこの制度は、メンバーの配偶者の方や、高校生・大学生くらいのお子さんを想定して用意していたのですが、今回、これを小学3年生の息子に適用してみよう、ということになったのです。
大人も戸惑う手続きを、ゲームのようにクリアしていく息子
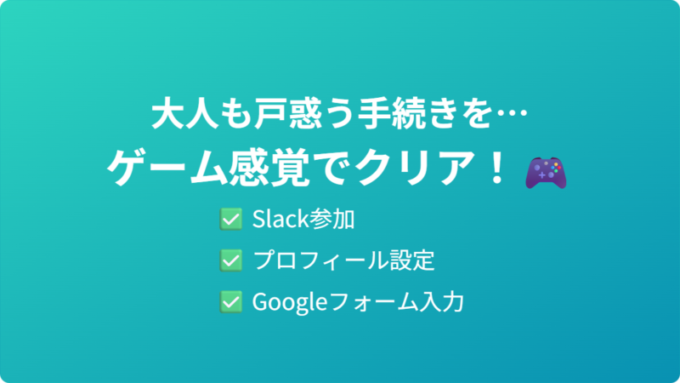
早速、ノンプロ研の運営メンバーにお願いをして、息子のメールアドレス宛に招待メールを送ってもらいました。
ノンプロ研に入会すると、まず最初にいくつかのチュートリアルをクリアする必要があります。
- Slackワークスペースへの参加
- プロフィールの設定
- ノンプロ研のGoogleカレンダーの登録(希望者のみ)
- 自己紹介用Googleフォームの入力・送信
これは、ITツールに慣れていない大人の方だと、結構戸惑う手順だったりします。
息子のメールアドレス宛に届いた運営担当の方からのメールを見ながら作業を始めていきました。
すると、息子から「ここ、どうすればいいの?」と質問されたのは、ほんの2、3回くらい。あとは、自分でどんどん説明を読んで、あっという間にすべての手続きを完了させてしまったのです。
その姿は、まるで新しいゲームを始めて、次のステージに進むために夢中でクエストをこなしていくかのようでした。ずんずんと作業を進めていく様子に、不安なんてどこにもない感じ。
むしろ、ようすを見ている僕の方が「すごいな…」と感心してしまうほど、頼もしかったですね。
無事に自己紹介がSlackに投稿されると、メンバーの皆さんから「よろしくね!」「すごいね!」と、とても優しく温かいコメントがたくさん寄せられました。みんな、本当に暖かいなと、僕も嬉しくなりました。
小3部長の爆誕。「ロブロ部」立ち上げへ
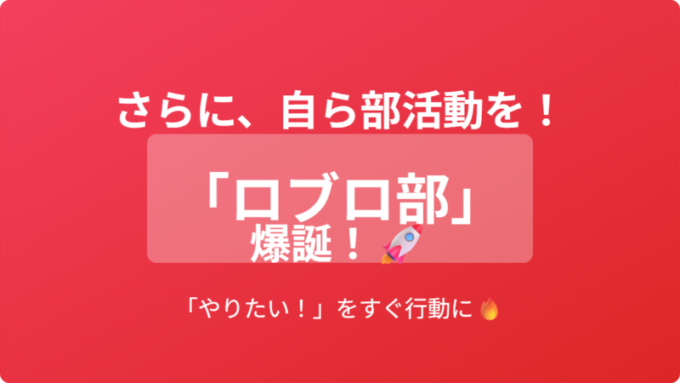
さらに驚いたのは、その後のことです。
息子が僕のところにやってきて、こう提案してきたんです。
「ノンプロ研に、部活動として『ロブロ部』を立ち上げたい」と。
Roblox(ロブロックス)は、息子が今一番ハマっているゲームです。その部活動を自分で作りたい、と言い出したんですね。
彼は運営担当のきのぴぃさんに、Slackで直接メンションをつけて「部活動を作りたいです」と質問し、申請用のGoogleフォームを教えてもらうと、すぐさま必要事項を入力して、見事「ロブロ部」を立ち上げてしまいました。
これからどんな活動をしていくのか、まだ僕にも分かりませんし、今のところメンバーの集まりは芳しくはなく…どうするのかなという感じではあります。
でも、自分が「やりたい!」と感じたそのエネルギーに素直に従って、すぐに行動に移す。その姿には、正直、僕すらも衝撃を受けてしまいました。
子どもの可能性に「壁」を作っていたのは、大人だった
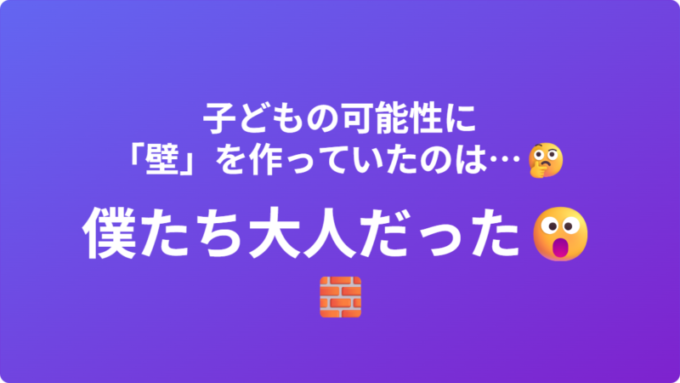
こうして一連の出来事を振り返ってみると、僕たち大人は、どうやら子どもの活動範囲に「壁」を作りたがりすぎなのかもしれないな、と感じました。「ここは⼦どもの来るところじゃない」と、無意識のうちに決めつけてしまっている。
今回の経験を通して僕が確信したのは、⼦どもの活動範囲を大人の都合で限定するのは、本当にもったいない、ということです。
ちゃんと大人の世界だったとしても、子どもはそこで過ごすことができるし、それを体験して学び、さらに心から楽しむこともできる。
もちろん、危ない目に遭わせてはいけません。でも、「ここの場では、こういう部分に気をつけて見守っていれば大丈夫」という大人の目が行き届いているのであれば、子どもを社会の境界線の外に置く必要は全くないんじゃないかな、と。そんなふうに思いました。
これから、息子がノンプロ研でどんな活動をしていくのか、まだ未知数なところはあります。
でも、素敵な大人の皆さんが支えるコミュニティの中で、自分の「やりたいこと」を追求していくというのは、彼にとって、かけがえのない経験になるはずです。
またこのお話に続報がありましたら、皆さんにもお伝えできればと思います。
まとめ
以上、「小3の息子が大人の学び場「ノンプロ研」に入会!子どもの可能性を狭めていたのは大人だったと気づいた話」についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!

