
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
楽しい夏休みですが、子どもたちにとって憂鬱なのは「宿題」ですよね。
夏休みの宿題に苦戦する息子の姿から、AI時代における「覚える」「書く」ことの意味と、子供の好奇心を育む学びの本質について考えてみました。
ということで、今回は「子供の「漢字嫌い」は悪いこと?宿題を通して見えた、これからの学びのカタチ」です。
では、行ってみましょう!
夏休みの宿題、立ちはだかる「漢字の壁」
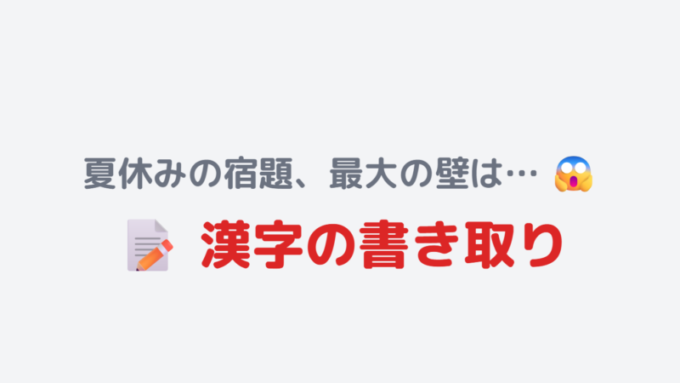
夏休みも終盤に差し掛かり、うちの息子が宿題と格闘しています。決して難しい問題に頭を悩ませているわけではなく、どうにも「やる気が起きない」という、なんとも親としては悩ましい状況です。
理科は早々に片付け、算数も比較的スムーズに終わらせました。しかし、社会と国語が手付かずで残っているんです。特に国語の、漢字を何度も書く問題が彼の行く手を阻んでいます。
「どうして社会が進まないの?」と聞いてみると、返ってきた答えは「漢字を書かなくちゃいけないから」。なるほど、原因はそこでしたか。
息子は漢字を読むのは比較的得意なようで、難しい専門書は別として、テレビのテロップやポケモンの公式サイトなど、一般的な文章であれば、ふりがながなくても大体読めています。ただ、「書く」こと、特に辞書などの助けを借りずに書くのはかなり苦手意識があるよう…。
大人だって、何も見ずに漢字をスラスラ書けますか?
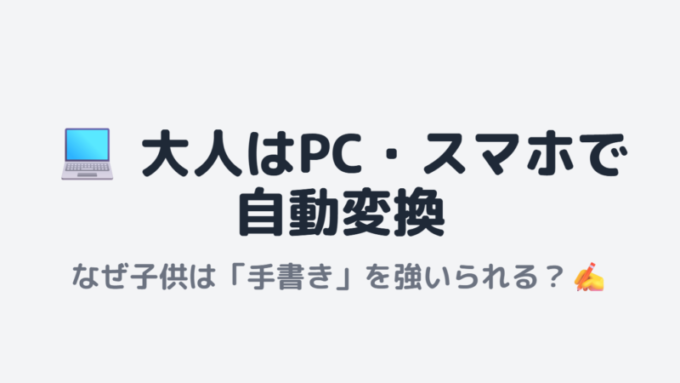
ここで、ふと思ったんです。この記事を読んでくださっている大人のみなさん、何も見ずに漢字をスラスラ書けますでしょうか?
もちろん、自分の名前や住所など、日常的に書く文字は問題ないでしょう。でも、仕事のメモやちょっとした手紙で、「あれ、あの漢字ってどう書くんだっけ?」と手が止まってしまう瞬間、ありませんか?
僕も正直、よくあります。
現代の僕たちは、パソコンやスマートフォンで文章を作成するのが当たり前になりました。
キーボードを叩けば、賢い日本語入力システムが次々と変換候補を出してくれます。その中から正しいものを選ぶだけで、文章は完成します。つまり、漢字を正確に「覚えて」いなくても、なんとかなってしまう時代なんです。
もちろん、漢字を知らないよりは知っている方がいいに決まっています。でも、何も見ずに書けないことで、日常生活や仕事で致命的な損失を被るかというと、正直なところ、ほとんどないのではないでしょうか。
では、なぜ子供たちは、今もなお、何も見ずに漢字を覚えて書く訓練を続ける必要があるのでしょうか。
人間の脳は、そもそも「覚える」のが苦手だった
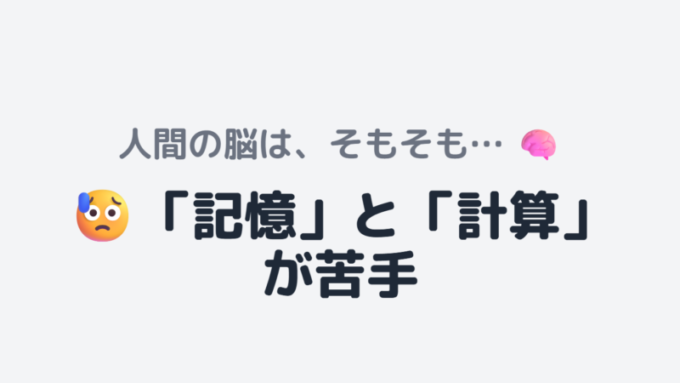
最近は脳の研究が進み、人間の思考のメカニズムが少しずつ解明されてきました。『まちがえる脳』(岩波新書)という興味深い本があります。
この本によると、脳内の信号伝達は本質的に不確かで確率的なものであり、人間が「間違える」のは、ある意味で避けられないことなのだそうです。
そして、脳の仕組みから見ると、「記憶」と「計算」は、人間が苦手とすることの双璧なのだとか。
たしかに、社会活動、こと仕事においては記憶と計算は重要な能力といえます。だからこそ、それらの能力を鍛えることが教育のカリキュラムの中心に据えられてきたのだと思います。
しかし、僕たち人間はこの「苦手」を克服するために、コンピューターという強力な道具を生み出しました。
テクノロジー社会と教育現場の大きなギャップ
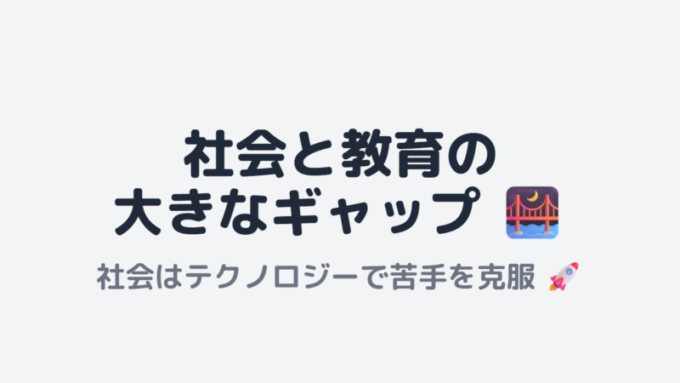
現代社会では、人間の苦手を補うテクノロジーがごく当たり前に使われています。
一昔前まで、データの「記憶」はフロッピーディスクやハードディスクが担っていましたが、今ではクラウドに保存するのが主流です。複雑な「計算」も、電卓から表計算ソフトのExcelへと進化し、私たちの仕事を助けてくれています。
社会は、テクノロジーの力を借りて人間の弱点を克服し、どんどん先へ進んでいる。
それにもかかわらず、教育の現場では、子どもたちに「道具は使わない」という前提で、苦手な記憶と計算をひたすら訓練させ、それが正確にできるかどうかで評価を下している。
このギャップは、少し奇妙に思えませんか?
もちろん、「読み・書き・そろばん」と言われるように、社会生活を送る上での基礎的な能力は不可欠です。教育において、得意な分野を伸ばすだけでなく、苦手な分野を克服しようと努力することにも、一定の意義はあるでしょう。
しかし、その一方でデメリットも大きいのではないかと感じています。
苦手なことを無理やりやらせ続けることで、「勉強は嫌なことだ」「辛く苦しいものだ」というネガティブなイメージを植え付けてしまう。あるいは、「自分はできないダメなやつだ」と自信を失わせてしまうかもしれません。
さらには、「好きなことや得意なことより、苦手なことに向き合うことこそが素晴らしい」という一種の思い込みを育ててしまったり、「間違えてはいけない」と考えるあまり、新しいことへの挑戦をためらう姿勢につながったりする可能性もあります。
最近話題になった「AIコピペ宿題」の問題も、この根深い課題の表れかもしれません。学びの本質を探求するのではなく、「とにかく答えさえ出せば、どんな手段を使ってもいい」という考え方を定着させてしまうリスクもはらんでいます。
以前、コミュニティ「ノンプロ研」の家族で参加できる「ファミプロ」のイベントで、画像生成AIを使って「おたすけロボット」をテーマに絵本を作るという企画がありました。
その時、何人かの子どもたちが「宿題を代わりにやってくれるロボット」を考案したんです。
それを見て、「そのアイデア出るよなあ」と、思わず納得してしまいました。
「好き」こそが最強の学習エンジン
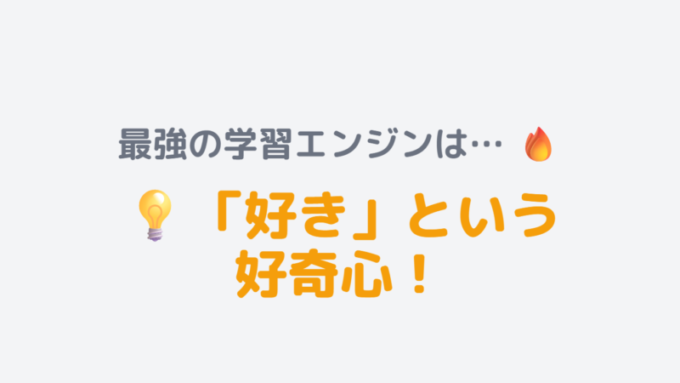
では、私たちはどうやって子供たちの学びをサポートしていけばいいのでしょうか。そのヒントは、やはり「好きなことへの探求」にあると僕は考えています。
うちの息子は今、Roblox(ロブロックス)というゲームに夢中です。ゲームのやり過ぎは親として気になるところですが、先日、とても感心したことがありました。
彼がゲーム内でのお金の単位について話していた時のことです。Robloxでは、「k(キロ)」や「M(ミリオン)」、「T(トリリオン)」といった単位が使われます。
- k (kilo): 1,000 (千)
- M (million): 1,000,000 (百万)
- B (billion): 1,000,000,000 (十億)
- T (trillion): 1,000,000,000,000 (兆)
ある日、息子が「この『T』ってどういう意味?」と聞いてきました。そこで、「1兆のことだよ」とそれぞれの単位の意味を説明してあげると、彼はすんなり理解し、日毎の会話の中で当たり前のように使うようになりました。
欧米では数字を3桁ごとに区切るのが一般的ですが、日本では「万・億・兆」と4桁ごとの区切りですから、日本人にはとっつきづらい部分があります。
もし、これらの単位を学校の授業で「覚えなさい」と強制されていたら、彼はきっと嫌いになっちゃっていたのではないかと思います。
結局のところ、子どもは自分の好きなことや興味のあることに関連していれば、驚くほどの好奇心を発揮し、勝手に学んでいくものだなと感じます。そして、そのようにして得た知識は、定着率も非常に高い。
まとめ: これからの時代、大人が子供にしてあげられること
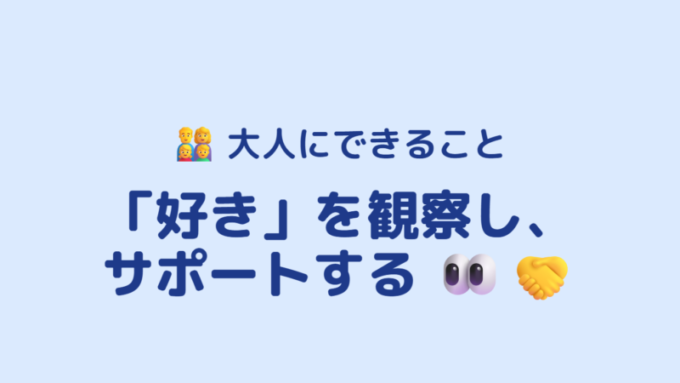
これからの時代を生きる子どもたちに対して、僕たち大人ができることは何でしょうか。
それはきっと、「この子は何が好きなんだろう?」と日々の姿をよく観察し、彼らが「もっと知りたい!」と思った時に、その探究心に寄り添い、サポートしてあげること。そして、「その好きなことの先には、どんな可能性があるんだろうね」と、一緒に未来を考えてあげることなのかもしれません。
以上、「子供の「漢字嫌い」は悪いこと?宿題を通して見えた、これからの学びのカタチ」についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!


