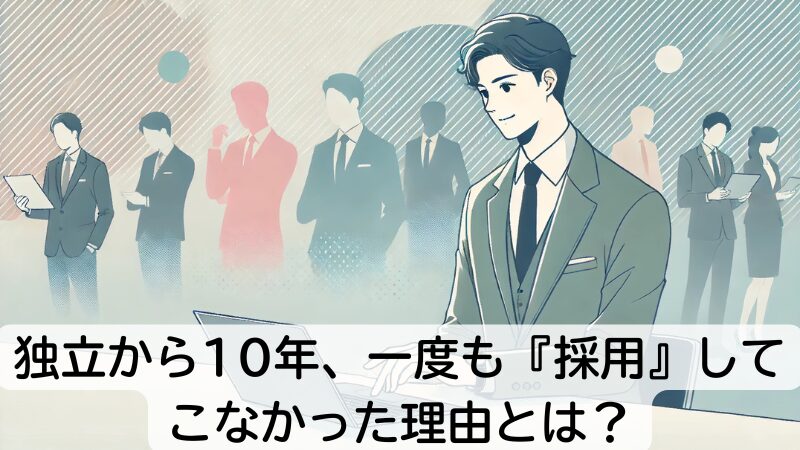
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
独立して早10年。実はこれまで一度も「採用」をしてきませんでした。
その理由についてお話しします。
ということで、今回は「独立から10年、一度も『採用』してこなかった理由とは?」です。
では、行ってみましょう!
僕が運営する2つの組織:プランノーツとノンプログラマー協会
まず、僕がどんな活動をしているか、少しだけ自己紹介させてください。僕は株式会社プランノーツという会社と、一般社団法人ノンプログラマー協会という2つの組織を運営しています。
この2つの組織、実はどちらも正式な所属メンバーは僕一人だけなんです。
「え、一人でどうやって回してるの?」って、よく聞かれます。特にコミュニティ「ノンプロ研」の運営は、会員さんも180人以上とたくさんいらっしゃいますし、イベントや講座も頻繁に開催しているので、「ひとり社長」ということを不思議に思われるかもしれませんね。
「採用しない」経営の裏側:コミュニティ運営の秘密
では、どうやって運営しているのか。その秘密は、「副業」という形で、コミュニティのメンバーさん自身にお仕事をお願いしている点にあります。
具体的には、こんなお仕事です。
- メンバーの入退会管理
- イベントの登録管理
- イベントの準備や運営サポート
- イベントや講座の動画編集
- 講座の運営・準備
- 講座の講師や運営サポート
- 経理業務
- 記事執筆
ざっと挙げただけでもこれだけあります。これらのお仕事を、現在20名以上のメンバーさんに、それぞれの得意なことや関心に合わせて少しずつ分担して担当してもらっています。
おかげさまで、今のところ大きな問題もなく、非常にスムーズに運営できていると感じています。本当にメンバーの皆さんには感謝しかありません。いつもありがとうございます!
なぜ10年間、採用してこなかったのか?
さて、本題です。独立してから10年間、「社員は増やさないの?」といったお声がけは、何度かいただいてきました。自分としても、採用について考えたことはあります。
その度に、僕なりに「もし採用したらどうなるだろう?」と想像してみるんです。
採用して、新しい仲間が増えたら、きっと色々な提案をしてくれるでしょう。
僕が「いいね、その方向でやってみようか」と確認して、フィードバックをする。
そして実際にGOサインを出して、そのプロセスや成果をチェックして、またそれについてフィードバックをして…。
…うーん、こうやって想像するだけで、なんだかすごく「モヤモヤ」するんですよね。
採用を想像したときの「モヤモヤ」の正体
この「モヤモヤ」の正体は、一体何なのでしょうか。僕なりに分解してみると、いくつかの理由が見えてきました。
マネジメントの手間という現実
まず一つ目は、単純にマネジメントの手間がものすごく増えるだろうな、という点です。
人を雇うということは、その人の仕事ぶりを見て、方向性を確認し、適切にフィードバックを与え、成長をサポートする責任が生じます。
僕一人の会社であれば、何かを決めるのも、実行するのも、全部自分の責任と判断でスピーディーに進められます。でも、社員がいるとなると、そうはいきません。コミュニケーションコストも、意思決定のプロセスも、格段に複雑になります。
失敗のリスクは誰が負うのか?
二つ目のモヤモヤは、リスクと責任の所在についてです。
もし、採用した社員の方にお願いした仕事がうまくいかなかったら、その責任は誰にあるのでしょうか?
僕の指示が悪かったのかもしれない。その方の能力や経験が、たまたまその仕事には足りなかったのかもしれない。あるいは、外部環境やタイミングが悪かっただけかもしれない。原因を特定するのは非常に難しいですし、誰か一人や一つのことだけに原因を押し付けることはできません。
しかし、その活動によって生じた損失、たとえば売上にならなかったとか、余計なコストがかかったとか、そういった金銭的なダメージは、最終的には会社がすべて負担することになります。
僕の会社は一人社長なので、つまり僕が全責任を負うわけです。一方で、社員の方には、成果が出なかったとしても、約束した給料を支払わなければなりません。
もちろん、失敗から学ぶことはたくさんあります。「次に同じ失敗を繰り返さないためにはどうすればいいか」、僕はその損失の痛みをもって、本気で考えざるを得ません。それは経営者としての貴重な学びです。
でも、その当事者である社員の方は、同じように「本気で」考えてくれるでしょうか?
もちろん、真摯に反省してくれる方もいるでしょう。でも、給料が保証されている状況で、僕と同じだけの危機感や当事者意識を持って、失敗の原因を自分事として捉え、次に活かそうと考えてくれるだろうか…と考えると、少し疑問符がついてしまうのです。
成功の果実は誰のもの?モチベーションの源泉は?
三つ目は、成功した場合の報酬とモチベーションについてです。
では逆に、仕事がうまくいって大きな成果が出たとしましょう。その場合、一番「儲かる」のは誰でしょうか?
それは、会社です。つまり、僕です。もちろん、インセンティブ制度などを設けることはできますが、基本的には社員の方の給料が、成果に応じてすぐに何倍にもなる、ということは稀でしょう。会社の利益が増えた分が、直接的に社員の方の報酬に大きく反映されるわけではありません。
それでも、人はやる気になるのでしょうか?本気で「会社の成功=自分の成功」と捉えて、頑張ってくれるのでしょうか?
もしかしたら、「社員を本気にさせる」ための、また別のマネジメント活動(たとえば、評価制度を工夫したり、社内イベントで盛り上げたり…)が必要になってくるのかもしれません。でも、それってなんだか、また「モヤモヤ」するんです。
金銭的な報酬のために、生活の安定のために働く。それは決して悪いことではありません。でも、その働き方において、個人としてリスクを取っていない状況で、果たして本当に大きな学びや成長が得られるのだろうか?
仕事に対する「本気度」はどこから生まれるのだろうか?そんなことを考えてしまいます。
採用が僕にとって魅力的な選択肢ではない理由
こうした「モヤモヤ」を総合的に考えると、僕にとって「採用」という選択肢は、経営上のリスクが大きすぎる割には、リターン(単に金銭的なものだけでなく、組織としての成長や価値創造の可能性も含めて)がそこまで魅力的には感じられない、というのが正直なところです。だから、これまで10年間、採用をしてこなかったのです。
もちろん、これはあくまで僕個人の考え方で、世の中には、素晴らしい社員の方々と一緒に、大きな成功を収めている会社さんがたくさんあります。
ですから、僕の考え方が唯一の正解だとは全く思っていませんし、異論反論も当然あると思います。
日本型組織と「面倒を見る」義務
そんな風に考えていたとき、最近読んだある本の一節が、僕のこの「モヤモヤ」の正体を、とてもうまく表現してくれているように感じました。
それは、経営学者の太田肇さんの著書『日本型組織のドミノ崩壊はなぜ始まったか』の中の一節です。少し引用させていただきます。
会社も含めた日本型組織の性質として
一度場の中にはいってしまうと、よほどのことがないかぎり、その場の中で救われるという利点をもっている。大学に入学すると、よほどの成績でないかぎり卒業できるし、その場の長となったものは場の成員の『面倒をみる』ことが暗黙のうちに義務づけられるのである
これを読んだとき、「あー、まさにこれだ!」と膝を打ちました。
「面倒を見る」ことへの疑問符
日本の会社組織において、従業員として所属するということは、「その組織にいれば、よほどのことがない限り、生活は保障される」という安心・安全を期待することと、ほぼ同義になっているように思います。それは、これまでの日本の雇用慣行や社会の仕組みが、長らくそうであったから、ある意味当然のことなのかもしれません。
そして、その組織の長、つまり経営者には、「場の成員の『面倒をみる』」という暗黙の義務が発生する。
この「面倒をみる」という言葉には、単に給料を払うということだけでなく、もっと広い意味合いが含まれているように感じます。たとえば、仕事をやらせる、成果を出させる、時には、やる気のなさや能力の低さといった課題に対しても、なんとかする…。そういったことまで含めて「面倒をみる」ことが、採用する側の責任として、半ば前提になってしまっているのではないか。
その前提の上で、本当に価値ある仕事、創造的な仕事、メンバー一人ひとりが自律的に考えて動くような組織運営が、果たして可能なのだろうか?
もちろん、それを実現している素晴らしい会社もあると思います。でも、仕組みとして「やりづらい仕組みなのでは?」と、僕には思えてしまうのです。
だから僕は、今のところ「採用しない」という選択をしています。その代わりに、コミュニティのメンバーさんたちと、対等なパートナーとして、それぞれの得意なことを持ち寄りながら、一緒に楽しく、価値ある活動を作り上げていく。そんな形が、僕にとっては一番しっくりくる働き方なのかもしれません。
皆さんの働き方や組織運営について考えるきっかけになれば嬉しいです。
まとめ
以上、「独立から10年、一度も『採用』してこなかった理由とは?」についてお伝えしました。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!


