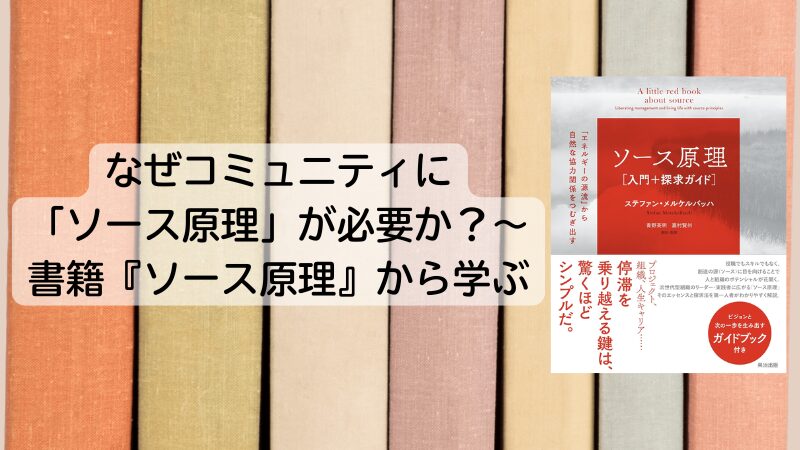
みなさん、こんにちは! タカハシ(@ntakahashi0505)です。
なぜ「お金」や「役割」がなくともエネルギッシュに活動できるのか…?
今日は、僕がコミュニティの運営における鍵として注目している「ソース原理」という考え方について、一冊の素晴らしい本をきっかけにお話ししたいと思います。
ということで、今回は「なぜコミュニティに「ソース原理」が必要か?~書籍『ソース原理』から学ぶ」です。
では、行ってみましょう!
なぜ今、ソース原理に注目するのか?
僕がなぜこれほどソース原理に惹かれているのか。
それは、僕が主宰しているノンプログラマーのためのスキルアップコミュニティ「ノンプロ研」の活動を、とてもうまく説明してくれる理論なのではないかと思っているからなんです。
ノンプロ研では、参加者の皆さんが自発的に勉強会を企画したり、イベントを運営したりと、たくさんのエネルギーを注いでくれています。
でも、そこには金銭的な報酬のような、はっきりとした「リワード」があるわけではありません。
それなのに、なぜこれほどまでにパワフルな活動が次々と生まれるのか? この長年の疑問に、スッと答えをくれたのが「ソース原理」でした。
今日はその魅力を、書籍を元にご紹介しますね。
「リスクをとった1人」に目を向ける『ソース原理』
今回ご紹介するのは、英治出版から2024年10月に発売されたステファン・メルケルバッハ氏の著書『ソース原理[入門+探求ガイド]――「エネルギーの源流」から自然な協力関係をつむぎ出す』です。
実は、「ソース原理」については、『すべては1人からはじまる』という書籍も先に邦訳が出ていて、どちらも素晴らしい本です。ただ、少し解説のニュアンスが違う部分もあるので、両方を読み比べて、自分にしっくりくる部分を取り入れるのが良いかもしれませんね。
さて、この本で語られる「ソース原理」とは、一言でいうと「ソースパーソンの振る舞い方、ソースの活かし方を説明するもの」です。
「ソース」と「イニシアチブ」とは?
ここで、いくつか大事なキーワードが出てきます。
- イニシアチブ: アイデアや直感、インスピレーションから始まった「取り組み」のこと。プロジェクトや事業、コミュニティ活動などがこれにあたります。
- ソースパーソン: イニシアチブについて、自らリスクを取って最初の一歩を踏み出した人のことです。
- ソース: ソースパーソンのこと、もしくはそのイニシアチブの根源となるビジョンや価値観のことです。
つまり、誰かの「こんなことをやってみたい!」という情熱から始まった取り組み(イニシアチブ)には、必ずその源泉となるビジョン(ソース)と、それを始めた人(ソースパーソンまたはソース)がいる、という考え方ですね。
この本は、その「ソース」という創造の源に目を向けることで、人や組織のポテンシャルを最大限に引き出す方法を教えてくれます。
構成は、理論を学ぶ[入門編]と、実践的なワークに取り組む[探求ガイド編]の2部構成になっています。
書籍の構成を覗いてみよう[入門編]
まずは[入門編]がどんな内容か、少し詳しく見ていきましょう。
Part 1:ソースとつながる
ここでは、「ソースは誰なのか?」「ソースパーソンの役割とは?」といった、ソース原理の基本的な概念が丁寧に解説されています。
また、ソースパーソンになる方法、そのふるまいについて、イニシアチブの次のステップを明確にするための方法、さらには障害となりえる要因などについて書かれています。
Part 2:ソースのレスポンシビリティを共有する
次に語られるのが、「レスポンシビリティ」の共有です。
レスポンシビリティというと、「責任」や「責務」と訳されがちで、少し重たいイメージがあるかもしれません。
でも、ソース原理でいうレスポンシビリティは、もう少し温かいニュアンスを含んでいます。どちらかというと、「託されたもの」に近い感覚ですね。
イニシアチブは、ソースパーソン1人だけでは大きくなりません。その想いに共感し、手伝ってくれる仲間、「サブソース」と呼ばれる人たちが現れます。
その仲間たちと、どうやってプロジェクトの「レスポンシビリティ」を分かち合い、エネルギーを効果的に注ぎ込んでいくか。その具体的な方法が示されています。
Part 3:ソースを受け渡す
そして、プロジェクトや組織が成長していく上で非常に重要になるのが、「ソースの受け渡し」です。
ソースパーソンが、いつまでもその役割に留まるのではなく、適切なタイミングで次の人に引き継いでいく。会社で言えば事業承継のような話ですね。
どうすればスムーズに、そして健全にバトンタッチができるのか。損得勘定ではなく、自分の内なる感覚を信じることの大切さが説かれています。
自分のプロジェクトを深く見つめる[探求ガイド編]
後半の[探求ガイド編]は、ソース原理の創始者であるピーター・カーニックが開発した「ソースワーク」という講座を、本の上で簡易的に再現するという、とても実践的なパートになっています。
こちらは裏表紙からスタートするという、凝ったつくりになっていますね。
構成としては、解説を読み、用意されたワークに取り組むことで、「ソース原理」という新しいレンズを通して、自分自身が関わっているプロジェクトや人生そのものを見つめ直すことができます。
その旅(ソースジャーニー)は、以下のようなステージで構成されています。
- ステージ 0 準備: まずは自分の価値観を明確にするところから始まります。
- ステージ 1 コール: アイデアや直感、ひらめきを受け取ります。
- ステージ 2 コールに応える: リスクを取って、最初の一歩を踏み出します。
- ステージ 3 旅を始める: 次の一歩を明確にして、着実に歩みを進めます。
- ステージ 4 盟友たち: 仲間とレスポンシビリティを共有します。
- ステージ 5 ドラゴンと向き合う: ソースが陥りがちな「病理」、つまり課題や困難と向き合います。
- ステージ 6 帰り道: 自分自身と向き合い、全体のバランスを取り戻します。
- ステージ 7 次の旅へ: イニシアチブの終わりと、次の世代へのソースの受け渡し。
特に最初のワーク、「大切にしている価値観を表すキーワードをリストから7つ選び、重要な順に並べる」というのは、自分自身の「ソース」を探る上で、とてもパワフルな問いかけだと感じました。
最も心を動かされた「愛の原則」
入門編の最後に置かれたエピローグで、著者は問いかけます。
「なぜ、この本の表紙は赤いのか?」
そう、実際に日本語版の書籍の表紙も赤のデザインになっています。
その答えこそ、僕がコミュニティ運営においてソース原理が有効だと確信した理由であり、ノンプロ研の講座カリキュラムにも取り入れたいと思った核心部分でした。
その答えとは…赤は「愛」の色だから、です。
自分の内側から湧き上がる直感に耳を傾け、失敗するかもしれないリスクを取って、新しい取り組み(イニシアチブ)を始める。協力者を集め、次に何をすべきか悩み、探求する。
この一連の活動の根源にあるエネルギーは、一体何なのでしょうか。
それは、地位や名誉、お金といった外部からの報酬ではありません。
それを言葉で表そうとするなら、たしかに「愛」という表現がマッチするように思えます。
「これが好きだから、やりたい」
「この仲間たちが大切だから、貢献したい」
「この活動が世の中のためになると信じているから、広めたい」
そういった、純粋で温かいエネルギーこそが「ソース」の正体であり、それによって動く人や組織が増えていけば、世界はもっと良くなるはずだ。著者はそう語りかけてくれます。
そして、そのようなエネルギー源を持って活動できること自体が、とても幸せなことなのだと。
まとめ
以上、「なぜコミュニティに「ソース原理」が必要か?~書籍『ソース原理』から学ぶ」についてお伝えしました。
もしあなたが、コミュニティ運営やチームビルディング、あるいはご自身のプロジェクトの進め方に悩んでいるなら、この「ソース原理」という考え方は、きっと大きなヒントを与えてくれるはずです。ぜひ、手に取ってみてくださいね。
引き続き、みなさんがいきいきと学び・働くためのヒントをお届けしていきます。次回をお楽しみに!
この話を耳から聴きたい方はこちらからどうぞ!


